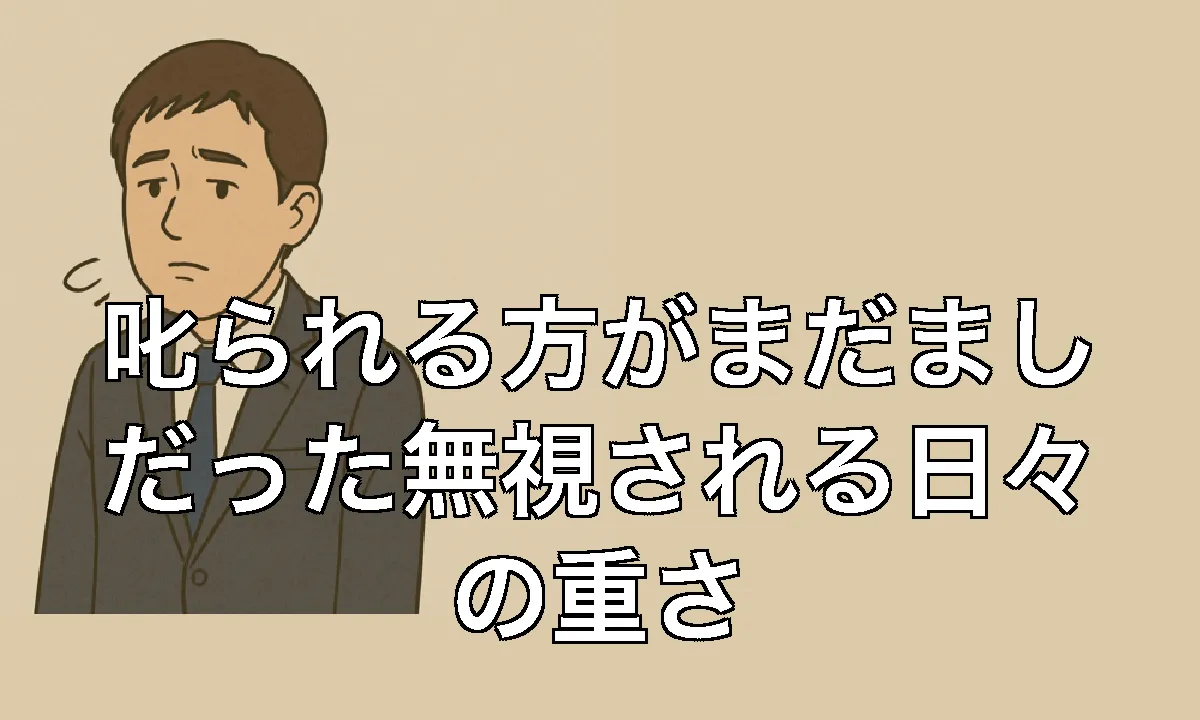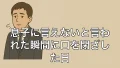言葉がないことの恐怖に気づいた瞬間
「あ、これはもう、相手にされていないな」と気づく瞬間は、叱られたときよりもずっと胸に刺さる。声を荒げられたときには、こちらに怒りが向けられている分、まだ“そこに自分がいる”という実感がある。しかし、無視されると、まるで自分が空気になったような虚しさに襲われる。司法書士という仕事は、基本的に静かな空間で黙々と作業を進める場面が多い。けれど、それが「誰とも関われない沈黙」になったときの居心地の悪さは、なかなか筆舌に尽くしがたい。
怒鳴られるのはまだ存在を認められている証拠
若い頃、野球部で監督に怒鳴られた記憶が今も鮮明に残っている。とにかく声がでかくて、ミスすればすぐ怒鳴られる。でも、不思議とあの怒鳴り声が、今は恋しいとすら思う。あのときは、悔しくて涙をこらえながらグラウンドを走っていたけれど、「お前に期待してるから怒ってるんだ」と言われた一言で救われた。今、誰にも声をかけられない日々の中で、自分が存在しているかどうか、わからなくなることがある。それに比べたら、怒られることはまだ希望だったのかもしれない。
元野球部の声出し文化と今の静けさのギャップ
「いけます!」「お願いします!」と声を出すことが日常だった部活時代。ベンチの声出しが勝利を引き寄せる、なんて本気で信じていた。あの頃の声の多さは、仲間の存在を常に感じさせてくれていた。今、司法書士として書類を黙々と処理する日常は、その正反対だ。とにかく静かで、声を出す機会が少ない。事務員との会話も必要最低限。「お願いします」すら言われない日があると、自分の存在意義が消えていくようで、居たたまれなくなる。
ミスを責められるよりも心に残るのは「無言」だった
たとえば、ある登記の確認でこちらが記載を誤ったことがあった。以前の事務員は「あれ、違ってませんか?」とすぐに声をかけてくれた。しかし、今の事務員は何も言わず、訂正された書類がそっと机の上に置かれていただけだった。何も言われないほうがつらかった。「この人、もう私に期待していないんだな」と感じてしまったから。叱られた方がどれだけ気が楽だったか。その日一日、机の前で重苦しい気持ちを抱えたままだった。
司法書士という仕事の中で感じる孤立
地方で一人事務所を構えて十数年。最初はやる気に満ちていたけれど、年月が経つにつれて、どんどん孤独が染み込んでくる。相談者が来て、登記をして、帰っていく。その繰り返しの中で、誰かと本音で話す時間がほとんどないことに気づいた。たとえ隣に事務員がいても、壁のような無言が空間を支配している。業務は回っているけれど、心が置いていかれているような感覚がある。
事務員との距離感に悩む日々
事務員は真面目に働いてくれている。でも、それ以上の関係が築けない。こちらが話しかけても「はい」とか「わかりました」だけ。もちろん業務上は問題ない。でも、日々を共にする人間として、その“会話のなさ”が重たくのしかかる。気づけば、自分ばかりが空気を読んで、話しかけるタイミングを図っている。けれど、それも面倒になってしまい、やがて無言が日常になる。誰かと一緒にいるのに、ひとりぼっちのような感覚。それが一番つらい。
一人事務所の会話不足と感情の行き場
「お疲れさまです」と朝言って、あとは必要最低限の会話だけ。沈黙が当たり前になり、気づけば一日中、声を出さない日もある。業務がうまくいっても、誰かに褒められるわけでもない。ちょっとした愚痴や不安を話したくても、そのタイミングが見つからない。帰り道、コンビニのレジで「袋おつけしますか?」と聞かれて、それだけでホッとすることがある。誰かに話しかけてもらえることの、ありがたさを痛感する。
独身男性司法書士にとっての「誰にも頼れない」感覚
家に帰っても誰もいない。夕飯はコンビニ弁当。テレビをつけても、笑い声がむなしく響くだけ。仕事で失敗しても、喜ばしいことがあっても、共有する相手がいない。しかも、司法書士という肩書きゆえに「ちゃんとしている人」として扱われることが多く、弱音を吐ける相手がほとんどいない。怒られるどころか、誰にも何も言われない日々の中で、心は少しずつすり減っていく。そのつらさは、表に出しづらいからこそ、深く残る。
無視されることへの耐性は育たない
時間が経てば慣れると思っていた。けれど、人から無視されることに慣れることはなかった。人は言葉で生きている。黙っていれば伝わることなんて、実はそう多くない。だからこそ、声をかけられない、返されない、その度に胸がきゅっと締め付けられる。怒られることが日常だったあの頃が、いまは眩しい。
時間が解決しないタイプの心の擦り減り
「そのうち慣れるよ」「気にしすぎだよ」と何度も言われた。でも、自分の存在が透明になっていくような感覚は、時間が経っても薄れなかった。むしろ、積み重なっていった。誰かと話したいと思っても、その“誰か”がいない現実に向き合うのがつらい。慣れるのではなく、麻痺していく。でも、心の中ではずっと、「誰か話しかけてくれないかな」と期待している。
繰り返される「またか」という無反応
書類を手渡しても無言。挨拶しても小さなうなずきだけ。そのたびに、「ああ、まただ」と思うようになった。決して悪意があるわけではないと分かっていても、何も返ってこないことに心は反応してしまう。積もり積もった“無視の記憶”が、ちょっとした出来事で一気に噴き出すこともある。ある日、何気なく言われた「え?今言いました?」の一言に、思わず笑ってごまかすしかなかった。
小さな会話が救いになる
ふとした瞬間の「おつかれさまです」や、「寒いですね」といった言葉が、心をあたためてくれる。忙しさの中で流れがちな言葉こそ、孤独な心には沁みる。無視されることの痛みに耐える中で、小さな一言の重さを、身にしみて感じている。
近所のおばあちゃんのひとことに泣きそうになった話
ある冬の朝、事務所の前を掃除していると、近所のおばあちゃんが「いつもきれいにしてるね、えらいね」と声をかけてくれた。それだけのことなのに、胸がいっぱいになった。声をかけられるだけで、こんなに救われるんだと、自分でも驚いた。誰かの一言が、乾いた心に染み込む。無視され続けていたからこそ、余計にその言葉が光って見えた。
「ありがとう」と言われることの価値を噛みしめて
最近では、「ありがとう」と言われると、思わず「そんなことでいいんですか」と返したくなる。誰かの役に立てた、それを言葉にしてもらえた、それだけで救われる。日々、何も言われずに働いていると、自分が何をしているのかすら分からなくなることがある。だからこそ、「ありがとう」というたった一言が、自分を肯定してくれる。そして明日も、もう少しだけ頑張ろうと思えるのだ。