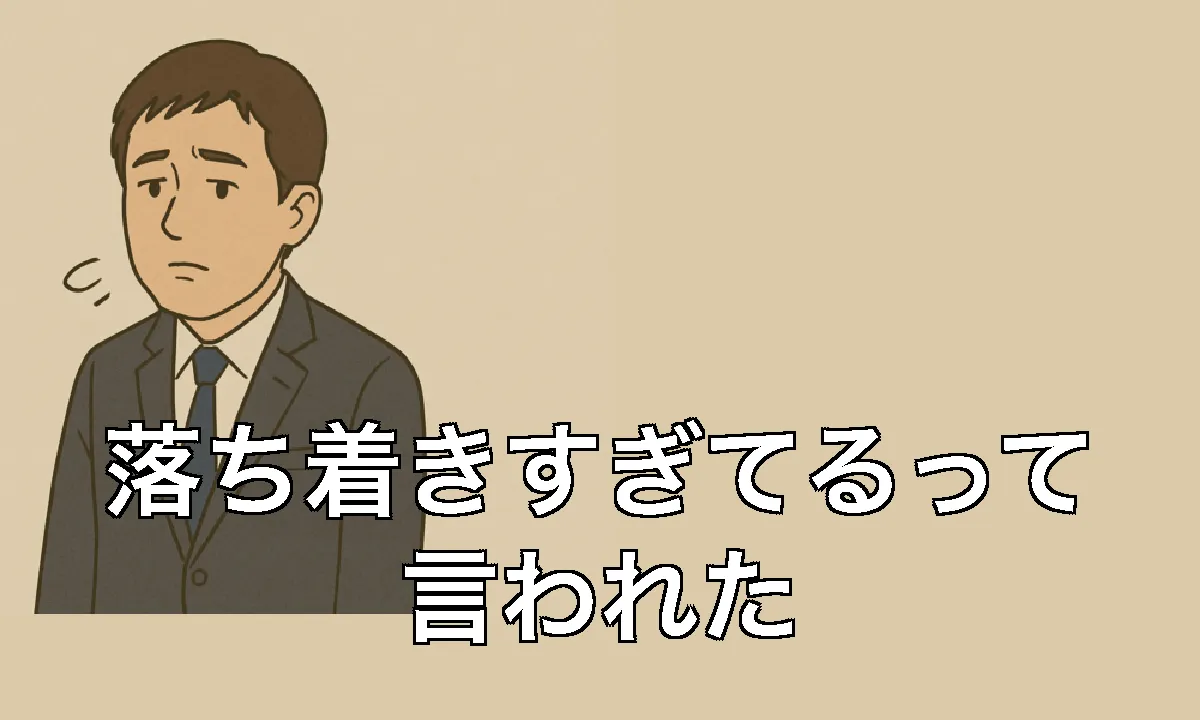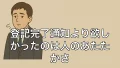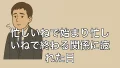落ち着いてるって褒め言葉なのか
「先生って、ほんと落ち着いてますよね」――何度か言われたことがある。そのたびに、ありがたいような、ちょっとモヤモヤするような気持ちになる。確かに、感情をあまり表に出すタイプではない。怒鳴ることも、笑い転げることも少ない。けれど、それって褒められてるのか、それとも距離を置かれてるのか、微妙だ。落ち着きって、どこか「面白みがない」「近寄りがたい」とも紙一重だ。
静かに見えることと冷たく見えることの紙一重
司法書士という職業柄、淡々と書類を処理し、冷静な判断を求められる場面が多い。だからこそ、感情を抑える癖がついてしまったのかもしれない。でも、あるときお客さんから「先生、何考えてるか全然わかんないですね」と言われたとき、ちょっとショックだった。無表情=安心ではなく、無関心と受け取られることもある。こちらとしては内心バタバタしてるのに、伝わらないのは歯がゆい。
一人で過ごす時間が多い職業の弊害
この仕事、基本的に孤独だ。事務所にいる時間のほとんどは、私ひとり。事務員さんもいるけれど、業務が被ることは少ないし、話す機会も限られている。だから、感情を交わす訓練がない。話し相手がいない生活は、自分のテンションの基準を見失う。野球部時代のように、声を出して励まし合う場なんて今はない。「落ち着きすぎてる」のではなく、もはや「動かされることがない」だけかもしれない。
元野球部の気合いはどこへいったのか
高校時代は野球部で、声が枯れるまで応援した。エラーすれば泣いたし、勝てば抱き合って喜んだ。あの頃の自分を思い出すと、今の私はまるで別人だ。司法書士になってから、あんな感情の爆発を見せたことがあるだろうか。ない。どこかで「士業らしくあれ」と自分を鎮め続けてきた結果なのかもしれない。でも、心はまだあの頃のまま、熱くなりたいと思っているのに。
士業ってそんなに冷静さを求められてるのか
司法書士のイメージは「正確・冷静・寡黙」。もちろん間違っていない。でも、そのイメージを守りすぎて、人間らしさを見失ってはいないだろうか。現場では人の悩みや不安に触れることも多いのに、こちらが感情を出さないことで、逆に壁を感じさせてしまっている気がする。プロとしての落ち着きと、人としての温度感。そのバランスを取り損ねているのではと感じる日もある。
感情を表に出さないのがプロって風潮
「感情を出す=不安定」「感情を抑える=安心感」というのが、いわゆる“士業っぽさ”かもしれない。でも、それって本当に正しいのか。相談に来た依頼者が泣きそうな顔をしていても、こちらが何も表情を動かさなければ、どれだけ冷たく映るだろう。むしろ、こちらも一緒に悩んだり、怒ったり、共感したりする方が、ずっと信頼されるんじゃないか。感情はプロ意識の敵じゃない。
共感より正確性?それでも心はある
登記の手続きひとつにしても、感情を挟む余地なんてない。でも、その背景には相続、離婚、借金、再出発など、人のドラマが詰まっている。そのドラマに対して、少しでも心を寄せることができなければ、この仕事はただの作業になってしまう。共感しすぎて業務に支障が出るのは本末転倒だが、無感情であることが求められているわけではない。私たちはAIじゃないのだから。
落ち着きの裏側にある本音と疲労
落ち着いて見えるというのは、外からの評価に過ぎない。その内側では、時間に追われ、書類に追われ、クレームに耐えている日々がある。そういうときほど、人は無表情になる。余裕がないとき、人はむしろ“静か”になるのだ。だからこそ、「落ち着いてる」と言われると、少し皮肉にも感じてしまう。本当は、もうちょっと誰かに心配してほしいくらいなのに。
黙ってるのは平常心じゃなくて限界
ある日、予定外の相続登記が3件も飛び込んできた。頭が真っ白になったが、顔は一切変えずに「承知しました」と答えた。すると、「先生、やっぱり落ち着いてますねぇ」と褒められた。いや、違う。本当は帰って枕を抱えて叫びたい気持ちだった。でも、そんなことできるわけもなく、無表情で乗り切るしかなかった。平常心ではなく、感情を出す余力がないだけだった。
本当は叫びたい午後三時の電話
午後三時、ちょうどおやつでも食べようかというときに、法務局からの電話。内容は「補正のお願いです」。あの言葉の破壊力は、何度聞いても慣れない。静かに「かしこまりました」と返事をする。でも心の中では、「またかよ!」と叫んでいる。それでも外から見れば「冷静な先生」。違うんだ、心は決して穏やかではないんだ。これが“落ち着きすぎてる”と見える現実だ。
事務員さんの一言に救われることもある
そんなある日、うちの事務員さんがふと言った。「先生って、何があっても落ち着いてるから、安心します」。その言葉に、正直救われた。誰かがそう見てくれているなら、それはそれで役割かもしれない。無表情でも、無関心ではない。冷静に見えても、心は動いている。少しでも、周りに安心感を与えられているなら、それは“落ち着きすぎてる”私の意味なのかもしれない。
「先生っていつも落ち着いてますよね」って笑顔
事務員さんの笑顔に、「それって良いことですかね?」と照れ隠しのように聞いてみた。すると「だって、先生が焦ってたら私も焦るし」と言われた。ああ、そうか、落ち着いてることには意味があるんだと、少しだけ自信が持てた。無表情でも、無口でも、誰かの支えになっているなら、悪くない。見せない感情のなかにも、伝わるものがあるのかもしれない。
自分のキャラが固まりすぎてる息苦しさ
ただ、落ち着いた人間像が固定化されすぎて、少し息苦しくなるときもある。たまには冗談を言ってみても、「先生がそんなこと言うなんて珍しいですね」と言われる。もう、自分で自分のキャラを縛っている気がする。自然体って、案外むずかしい。人前では“落ち着いた司法書士”を演じながら、家に帰るとテレビ相手に大声でツッコミを入れてる、そんな裏表が自分にはある。
落ち着きキャラを脱ぐ勇気はあるのか
落ち着いている自分が好きなわけじゃない。ただ、それが求められているから、そうしているだけ。でも時々、ありのままの自分を出せたら楽だろうなと思う。大声で笑ったり、泣いたり、愚痴をこぼしたり。そういう姿も、誰かに見せられるようになったら、もう少しこの仕事も、人生も、楽になるのかもしれない。
ときには取り乱したっていいじゃないか
「取り乱してはいけない」「感情を出してはいけない」そんな思い込みに縛られて、長い間生きてきた。でも、感情を出すことが弱さじゃないとしたら?ときには焦ってもいいし、泣いてもいいし、怒ってもいい。むしろ、そうすることで人間らしさが伝わるのなら、それは信頼の形かもしれない。落ち着きすぎてる自分から、少しずつでも解放されていきたい。
同じように悩んでる誰かの背中を押すために
この記事をここまで読んでくれた誰かが、「ああ、自分だけじゃないんだ」と思ってくれたらうれしい。感情を抑えすぎて苦しくなっている人がいたら、声を大にして言いたい。「落ち着きすぎてても大丈夫。あなたにもちゃんと感情があるし、それは弱さじゃない」と。誰かの心が少しでも軽くなるなら、今日の疲れも報われる気がする。