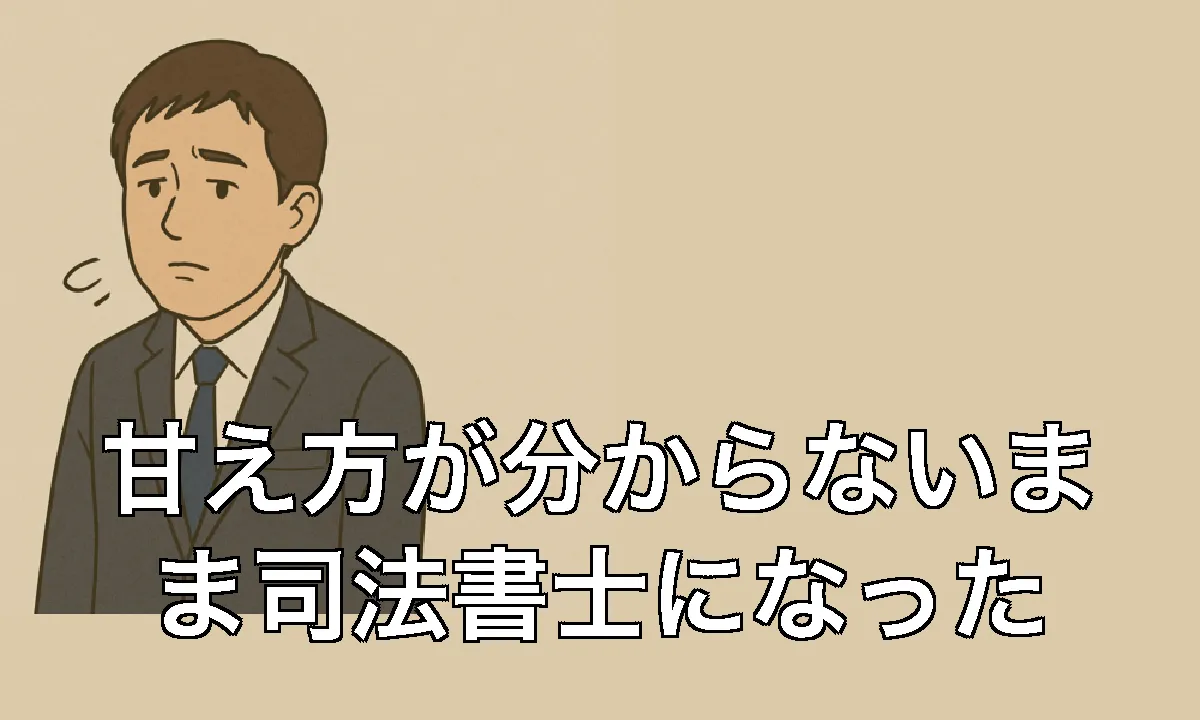甘え方が分からないまま司法書士になった
甘えられない性格ができあがった背景
「甘えるって、どうやるんですかね」なんて冗談めかして言ったことがあるけれど、本音だった。子どもの頃から「しっかりしてるね」と言われるたび、ほんの少しずつ肩に荷物を積まれていった気がする。甘えることは、迷惑をかけること。そう刷り込まれて生きてきた。司法書士という立場になればなるほど、その性格が拍車をかけてくる。頼られることには慣れていても、頼ることには異常に不器用だ。
子どもの頃から「しっかり者」だった
実家では末っ子だけど、なぜか一番大人びていた。親が忙しくしていたこともあり、空気を読んで「大丈夫」と言うのが癖になっていた。たとえ辛くても泣くのはあと、話すのもあと。兄がトラブルを起こしたときも、なぜか自分が謝っていた記憶がある。「甘える=面倒をかけること」だと子どもながらに理解していたのかもしれない。
親の顔色をうかがう癖が抜けない
大人になってもその癖は消えず、人と接するときはつい顔色を読んでしまう。事務員とのやり取りでもそう。頼みごと一つするにも、「忙しいかな」とか「言ったら悪いかな」と考えてしまう。結局、自分で全部抱え込んでしまう。これは完全に悪い癖だとわかっているのに、治せない。
「頼ると迷惑」という思い込み
「これお願いできますか?」の一言が、どうしても言えないときがある。頭ではわかっていても、口から出すのに時間がかかる。頼ることを「甘え」と捉え、それが相手にとって重荷になると勝手に思い込んでしまう。だから、つい「自分でやるか」と処理してしまう。その積み重ねが、どっと疲れとして返ってくる。
司法書士という職業の性質
司法書士は「頼られる」仕事だ。依頼人からの相談は同業者や金融機関、行政からもさまざまな期待が寄せられる。「この人に任せておけば大丈夫」と思われるよう、常に冷静であることを求められる。それはつまり、弱みを見せる場所がないということでもある。
人に弱みを見せられない業務の連続
登記でトラブルがあったとき、本当は誰かに相談したい。だけど「自分のミスかもしれない」と思うと、口をつぐんでしまう。調べて、調べて、確認して…独りで抱えたまま夜が更けていく。誰にも弱音を吐けず、ただ「次は気をつけよう」で終わってしまう。
「先生」と呼ばれることのプレッシャー
「先生」なんて呼ばれても、こっちは未だに半人前の気分だ。でも呼ばれる側としては、それに応えないといけない。どこかで「甘えてはいけない」と無意識に思っている自分がいる。肩の力を抜くのが下手くそで、まるで甲子園を目指してた頃の自分みたいに、常に全力投球している。
事務員一人でも頼れない日々
今、事務所には事務員が一人。仕事は丁寧でとても助かっている。だけど、全部を任せられるわけじゃないという妙な遠慮がある。自分が口出ししすぎてるのも自覚している。それでも「甘えたいのに甘えられない」が、こんな近くの人間関係にも顔を出している。
任せたいけど任せられない
「これお願いしても大丈夫かな…」そう思いながら仕事を振るタイミングを逃すことが多い。結果、気づいたら自分でやってしまっている。相手の能力やスキルじゃなく、自分の遠慮が原因。これって、相手にとっても失礼だよなと思うこともある。
自分でやったほうが早いという呪縛
時間がないからこそ「自分でやった方が早い」が口癖になってしまった。でもそれって、本当は誰にも頼れない不器用さの裏返しだと思う。時短のためじゃなく、不安を見せたくないだけ。それが分かっていても、つい同じループにハマってしまう。
「お願い」を伝える難しさ
頼むときに「すみません」「お手数ですが」と前置きが多くなってしまう。言葉の選び方ひとつに時間がかかる。だから億劫になって、最後には「やっぱりいいや」となる。この小さな“甘えられなさ”が、積もるとストレスになる。
プライベートでも甘え下手
恋愛も同じだった。付き合っている相手にすら、弱音を吐けなかった。疲れていても「平気」と言ってしまう。甘えるどころか、素直になることすら難しい。そんな自分に相手が呆れてしまうのも、今では理解できる。
恋愛が続かないのは性格のせいか
相手に心配をかけたくないという気持ちが強すぎて、何でも「大丈夫」で済ませてしまう。だけど、それは壁を作っているのと同じ。甘えることができない人は、恋愛にも向いていないのかも…なんて考えると、またひとつ遠ざかる。
弱音を見せられないままフェードアウト
一緒にいた頃は本当に楽しかった。けれど、何かあったときに「相談すればよかったね」と言われて初めて、自分が何も見せてなかったことに気づいた。自分のことを相手に隠している限り、信頼関係なんて築けるはずがない。
甘えるというより我慢してしまう
どこかで「我慢する自分」に安心しているところがある。誰にも迷惑かけず、すべてを引き受ける自分。けれど、それではどこにも逃げ道がない。甘えられないまま大人になったことが、こんなにも生きづらいとは思わなかった。
本音を言える場所がない
愚痴を言う相手がいない、というより、愚痴の言い方を忘れた。友人とも疎遠になり、同業者とは業務連絡ばかり。気軽に「疲れた」と言える相手が、今の自分にはいない。
同業者同士でも本音は言いづらい
飲み会や会合に参加しても、話題は「忙しい自慢」か「業績話」。誰がどれだけ案件抱えてるか、みたいな空気が漂う。そんな中で「最近ちょっとしんどくてさ」と言える空気ではない。本音はいつも喉の奥で詰まってしまう。
「忙しいアピール合戦」に疲れる
本当は余裕がある日もある。けれど「暇だ」と言うと仕事ができない人に思われそうで、つい「バタバタしてます」と返してしまう。忙しいと言うことが、評価を守る手段になっている。これも一種の甘えられなさかもしれない。
仕事の愚痴が言える関係がうらやましい
ランチで他業種の人たちが「また上司がさ〜」と笑いながら話してるのを見て、羨ましいと思うことがある。弱音や愚痴を出せる相手がいるって、すごいことなんだなと気づく。自分にも、そんな相手がほしい。
甘えることに罪悪感を持たないために
甘えることは「迷惑」ではなく、「信頼」の表現かもしれない。そう考えられるようになってから、少しずつ考え方を変えてみている。ほんの小さなことから始めてみることにした。
小さな「お願い」から始める
いきなり頼るなんて無理だ。だからまずは「今日、これやってもらっていい?」と一言伝えることから始めた。大げさに言えば、これは自分にとって革命だった。相手の反応を見て、「あ、頼ってもいいんだ」と思えるようになった。
「手伝ってもらうこと」は弱さじゃない
むしろ、それはチームで動いている証拠。信頼しているから頼めるということだ。ひとりで全部抱え込むより、結果として相手も安心して働ける環境が生まれる。これは司法書士事務所でも、恋愛でも同じことなのかもしれない。
聞いてくれる人を見つける
聞き上手であることと、聞いてもらうことは別物だ。愚痴や弱音を受け止めてくれる相手がひとりいるだけで、人は随分楽になる。同業者でなくてもいい。ときにはSNSのつながりでもいい。
同業者でなくてもいい愚痴が言える相手
ある日、昔の野球部仲間と電話をした。「お前、頑張ってるな」って言われて泣きそうになった。甘えられるのは、相手の理解度じゃない。自分が心を開けるかどうか。それに気づいたとき、少し肩の荷が下りた気がした。