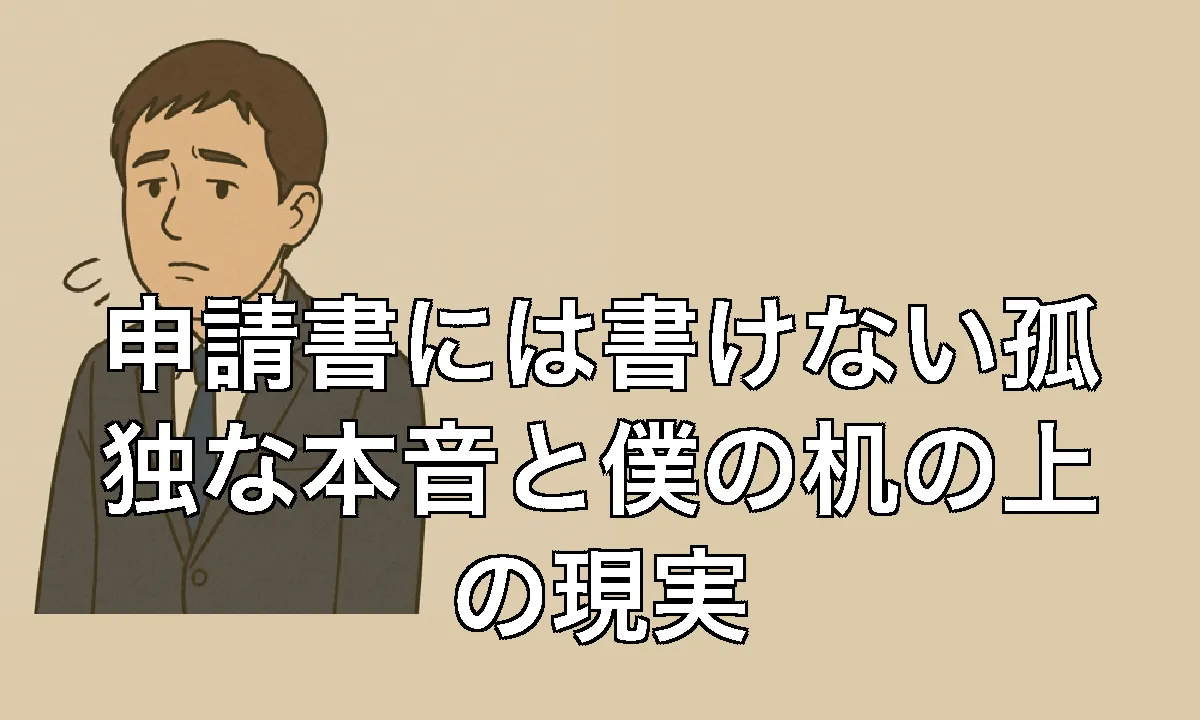誰にも見せない申請書の裏側
申請書を前にするとき、僕の頭の中は仕事の正確さと期限のことでいっぱいになる。誰のための書類か、どうすればミスを減らせるか、そればかりだ。だけど、ふと手が止まる瞬間がある。そこに記された名前の背後に、どんな人生があるのか。そのことを考え出すと、僕の中の「人としての感情」がうっすらと顔を出してくる。だけど、そんな気持ちは書面には残せない。申請書には余白がない。孤独も、心配も、うれしさも、記載欄の外だ。
形式美のなかに埋もれる気持ち
僕らの業界は、とにかく「正確さ」や「整然さ」が求められる。書式に間違いがあれば受理されないし、日付や印鑑の位置ひとつでもアウトになる。そんな厳密な世界で日々生きていると、だんだんと自分の感情を排除するクセがついてくる。けれど、時折ふと手元の申請書を見て、「この方も家族のことで悩んだんだろうな」とか「急いでいて疲れてるのかもしれないな」と、勝手に物語を想像してしまう。それは間違いなく、僕自身の孤独から来る投影なんだと思う。
書式に沿うほど遠ざかる人間らしさ
正確な書類が求められる職業の中で、人間くささを出すのはとても難しい。申請書に感情を挟む余地はない。むしろ、挟んではいけない世界だ。だからこそ、そこに僕の心が置いていかれている気がするときがある。誰かの人生の大事な節目に立ち会っているはずなのに、僕はそれを「一件処理」として流している。それが虚しくて、机に向かう自分が機械に思えてくることもある。
「本人希望欄」に書けない願い
「本人希望欄」ってあるでしょ?あそこに、もっと本音を書けたらいいのにって思うことがある。「寂しい」「助けてほしい」「誰かに気づいてほしい」——そんな声は、どこにも届かない。もちろん僕だって書けない。「独身です。仕事ばかりで、話し相手もいません」なんてこと、書いたって誰にも処理してもらえない。それでも、そういう気持ちを隠したまま、今日もまたひとつ、申請書を完成させる。
申請書が片付くたび、積もる孤独
業務をこなすことに達成感はある。でも、その達成感が積もれば積もるほど、どこかに穴があいていくような感覚もある。書類の山を片付けるたびに「今日も一人だったな」と思ってしまう。誰かと笑い合ったわけでもなく、深い会話を交わしたわけでもない。なのに、事務所の外では夕暮れのチャイムが鳴っている。その音が、やけに胸に響くのだ。
完了のハンコが押されても終わらない
「完了」と書かれた書類には、しっかりと印鑑を押す。でも、そのハンコを押したところで、僕の中の孤独は終わらない。依頼者から「ありがとうございます」と言われても、それは手続きに対する感謝であって、僕という人間への関心ではない。何百件と完了印を押しても、僕の中の「誰かに必要とされたい」という本音には届かないのだ。
誰とも話さず終わる長い一日
事務員さんが外出している日などは特に、朝から夕方まで一言も声を発しないことがある。電話も来客もない日、時計の針が進む音だけが聞こえる。そんな日は、「僕って社会と繋がってるんだろうか」と不安になる。元気そうに働いているように見えて、実は誰にも気づかれていないんじゃないかと思うと、息が浅くなる。
司法書士という肩書きの重みと空虚
司法書士という肩書きは立派に見える。でも、実際には誰にも言えないプレッシャーや寂しさがある。法務局のカウンターで丁寧に説明していても、心の中では「誰か、僕の話を聞いてくれないかな」と思っている。肩書きがあるからこそ、弱音も吐けず、ただ「ちゃんとした人」でい続けなきゃいけない。そんな窮屈さの中に、僕はずっといる。
「先生」と呼ばれても心は空腹
「先生」と呼ばれることは多い。だけど、実際にはご飯を食べるのも一人、昼休みもスマホをいじって終わる。呼び方と実態がかけ離れているほど、空しさが広がっていく。誰かと目を合わせて笑いながら食事をする日が、もうずっとない。心の空腹はコンビニのパンじゃ満たされないし、呼ばれ方ひとつで自尊心が保てるほど、もう若くもない。
信頼されても、頼られても、ひとり
お客さんに「先生がいて助かりました」と言われることもある。それは嬉しい。でも、事務所のドアが閉まった瞬間、その言葉の余韻だけが残って、誰もいない部屋に戻る。信頼や感謝の言葉は確かにあるのに、それを一緒に分かち合える相手がいない。そんな毎日が続くと、「誰のためにやってるんだろう」と立ち止まってしまう。
仕事帰りに寄るスーパーが唯一の会話の場
夜、スーパーに寄る。レジの店員さんに「袋いりますか?」と聞かれる、それだけがその日最初の会話だったりする。別に話したいことがあるわけじゃない。でも、誰かに声をかけられると「まだ存在してるんだな」と少しだけ安心する。スーパーの照明が温かく感じる夜は、ちょっとだけ泣きそうになる。
孤独を埋める方法を模索して
最近は、どうやったらこの孤独を少しでも和らげられるかを考えている。SNSを見たり、本を読んだり、散歩したり、色々試してみるけれど、どれもしっくりは来ない。だから、こうして文章にして吐き出すようになった。「誰かに届くかもしれない」という期待が、わずかでも心を支えている。
元野球部の癖で肩を回す昼休み
僕は元野球部だった。その名残で、今でも昼休みに無意識に肩を回している。体は覚えてるんだなと思う。あの頃は仲間がいて、勝敗があって、打てなければ怒鳴られ、打てば抱き合った。今の僕には、そういう瞬間がない。仕事でミスすれば自分で抱え、うまくいっても誰にも報告しない。喜怒哀楽が均一な毎日だ。
書類とキャッチボールはできないけれど
キャッチボールって、相手がいて初めて成立するものだ。だけど僕の机の上には、相手の見えない書類ばかり。投げても返ってこない、返事のないボールをずっと投げ続けているような気分になる。時々、自分の存在意義が揺らぐ。けれど、それでも今日もまたボールを拾って、投げる。
空振りばかりでもバットは捨てない
この年になっても、どこかで「ホームランを打ちたい」と思っている。誰かにちゃんと気持ちを届けたい。仕事も、人間関係も、人生も、空振りばかりかもしれない。それでも、バットを捨ててしまったら何も始まらない。だから今日も机に向かい、申請書に向かう。それが僕にとっての「打席」なのだ。
それでも今日も申請書に向かう
どれだけ孤独でも、どれだけ報われなくても、僕はまた申請書を受け取り、机に向かう。誰かのための書類を、黙々と作る。そこに自分の気持ちを乗せることはできないけれど、せめて「この人の人生が少しでも良くなりますように」と願いながら。そんなふうに働くことが、僕のささやかな抵抗であり、希望なのだ。
名前を書いて押印する、それが誰かの一歩になる
名前を書いて印鑑を押す。その小さな行為が、誰かの人生を動かす最初の一歩になることもある。僕が携わった書類で、相続が終わり、新しい暮らしが始まり、心の整理ができる人もいるかもしれない。そう考えると、自分の孤独も、少しだけ意味があるように思える。
孤独と戦う誰かへ、心の余白を残すコラムを
僕のように、誰にも言えない孤独を抱えながら働いている人はきっとたくさんいると思う。司法書士じゃなくても、誰でも。だからこのコラムでは、そんな人たちに「わかるよ」と言いたい。申請書には書けないけれど、ここには書ける。そんな場所を、これからも作っていきたい。