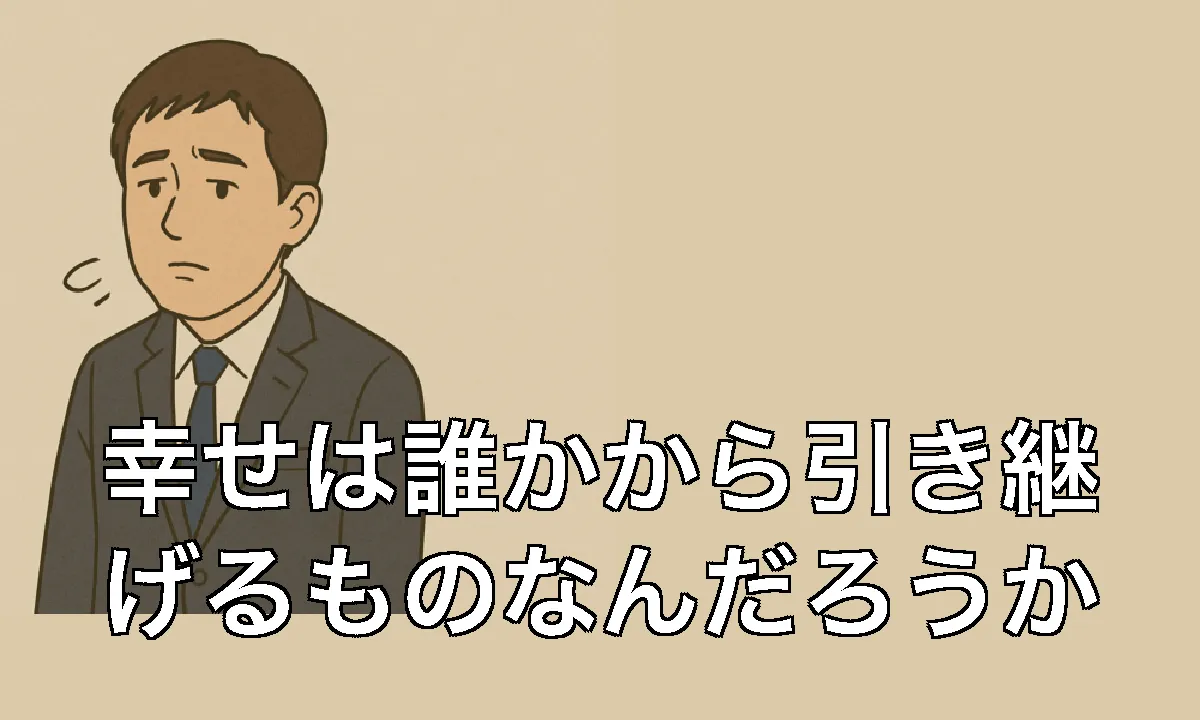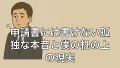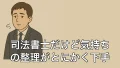あの人が残したものは財産だけじゃなかった
僕が司法書士として携わったある相続案件で、ふと胸に残った出来事がある。依頼人は、地方の一軒家に住む高齢の女性の息子さん。淡々と進める予定だったその手続きのなかで、思いがけず心に刺さる言葉を聞くことになった。「母の笑顔だけは、どうしても手元に残せなかったんです」。その瞬間、財産や登記では測れない“幸せの記憶”というものが存在するのだと痛感した。
相続の現場で垣間見る家族のかたち
手続きの場にいると、家族の本音や関係性が、あぶり出される瞬間がある。それは冷たいわけではなく、むしろ温かさが溢れ出てしまっているような不器用な優しさの形かもしれない。ある時は、おばあさんの形見のぬいぐるみを巡って姉妹が涙ぐみながら譲り合ったこともある。財産の大小ではなく、記憶や心の象徴こそが「本当の価値」になることがある。
遺産分割協議書の裏にある感情のやりとり
遺産分割協議書は、表向きは冷静で合理的なものだが、その裏にはさまざまな思いが絡み合っている。「この家は兄に任せたい」「あの茶箪笥だけはどうしても持ち帰りたい」——そんな言葉の奥にある感情は、紙には書ききれない。形式的な文章ではなく、対話の中で少しずつお互いの“思い出”を整理しながら進める。僕たちはその過程の中で、無言の気配りや遠慮を、できるだけ丁寧にすくい取る努力をしている。
目には見えないけど確かに存在するもの
「先生、形見分けって法律で決まってるんですか?」という質問をされることがある。法律上は明確なルールなどない。けれども、そこには“譲り合い”や“思いやり”という無形の価値が存在している。通帳の残高よりも、ある人にとっては使い古された椅子の方が大切なこともある。その椅子には、亡き人と過ごした穏やかな時間が染み込んでいるのだ。
書類とともに流れてくる空気感
書類作成の業務は、いわば淡々とこなすものだ。しかし、依頼人の語るエピソードや部屋の空気に、ふと“重み”を感じることがある。たとえば仏壇の前で、誰かが無言で手を合わせていたとき。そこには何も言葉がなくても伝わる“想い”があって、僕はそれを感じ取ることしかできないけれど、それが実はいちばん大事な何かなんじゃないかと思ってしまう。
通帳の残高よりも重たい沈黙
「結局いくらくらいもらえるんですか?」と聞く方もいれば、一方で通帳を前にして黙り込む方もいる。特に、亡くなった方と確執があった場合や、逆に深い愛情を抱いていた場合、その沈黙は金額以上の意味を持つ。数字では表せない時間の重さが、そこにはある。沈黙の中に立ち会う僕は、ただそっと見守ることしかできないけれど、その沈黙こそが“本音”だったりする。
兄妹げんかの火種は相続とは別のところに
兄妹で揉めている事例も多いが、その火種はほとんどの場合、相続財産の問題ではない。幼少期のわだかまり、両親の扱いへの不満、連絡を取ってこなかった後悔——そうした感情の集積が「相続」をきっかけに噴き出すのだ。「あんたはいつも親の近くにいて…」「なんで私に何も相談してくれなかったの?」と、財産よりも心の整理が必要な場面に立ち会うこともある。
司法書士としての僕の立場
仕事として関わるうちに、司法書士である自分が「何を支えているのか」を考えるようになった。登記の手続き、遺言書の確認、それだけじゃない。目の前の人の“気持ちの整理”に、僕もほんの少しだけ関わっているのかもしれない。いや、正直なところ、書類を前にして黙ってうなずいてるだけなんだけど。でも、それでもいいと思っている。
幸せなんて仕事に関係ないと思っていた
昔は「司法書士の仕事に感情なんていらない」と思っていた。目の前の書類をこなし、正確に登記を終える。それがプロの仕事だと信じていた。でも、ある日「先生に話せてよかった」と涙を浮かべた方の言葉が、胸に残った。「自分の人生に意味があった気がしました」——そんな大げさな、と思いつつ、僕の方が救われていたのかもしれない。
目の前の手続きに集中していたあの頃
独立してすぐの頃は、ただひたすら“効率”と“正確さ”を追いかけていた。事務員もいなかったから、書類作成から提出まですべて自分でやっていた。正直、相談者の話を聞く余裕なんてなかった。でも、それは逃げだったのかもしれない。感情を受け取るのが怖かったから、機械のように処理することで自分を守っていたんだと思う。
心を動かされた一通の手紙
ある日、亡くなった依頼者の娘さんから手紙が届いた。「父の相続手続きに関わってくださって、ありがとうございました。先生がいてくれて、気持ちが軽くなりました」。そんなふうに思ってもらえるなんて、思ってもいなかったし、嬉しいよりも、なんだか申し訳ない気持ちになった。でも、その手紙は今でも僕の机の引き出しにしまってある。
気づかされたのは自分の欠落だった
相続の手続きを通して、ふと自分自身を見つめ直すことがある。仕事は充実している。でも、どこかぽっかりと空いている気もする。たぶんそれは、誰かと「幸せ」を共有した記憶が少ないからだ。僕は結婚していないし、子どももいない。休日もほとんど仕事。そんな自分が人の“人生の整理”に関わっていることに、矛盾を感じることもある。
相続されないまま置いてけぼりの思い出
僕にも父がいて、母がいる。家族の思い出がないわけじゃない。だけど、仕事に追われて連絡も取らず、気づけば季節が何度も過ぎている。人の相続には関わっていても、自分の家族とは向き合えていない——そんな後ろめたさを抱えながら、今日もまた登記簿とにらめっこしている。僕の「思い出」は、誰に引き継いでもらえるのだろう。
自分の人生には何が残っているんだろう
法務局の帰り道、ふと考えることがある。僕がこのまま死んだら、誰が僕のことを整理してくれるんだろう。事務員の〇〇さんだろうか。彼女には迷惑をかけたくない。でも、そう思ったとき、初めて「誰かと生きること」の意味を考えたのかもしれない。財産じゃない。登記じゃない。誰かの記憶の中に、僕という存在が残ること——それが「幸せを引き継ぐ」ことなのかもしれない。
僕にとっての幸せとは何か
幸せは相続できるものじゃない。でも、人から人へ伝わることはあると思う。日々の会話や、優しい気持ちや、誰かのために働くこと。そんな積み重ねが、誰かの心に残るのだとしたら、それは小さな“幸せの相続”なのかもしれない。そして、それは僕にもできることだと、今なら思える。