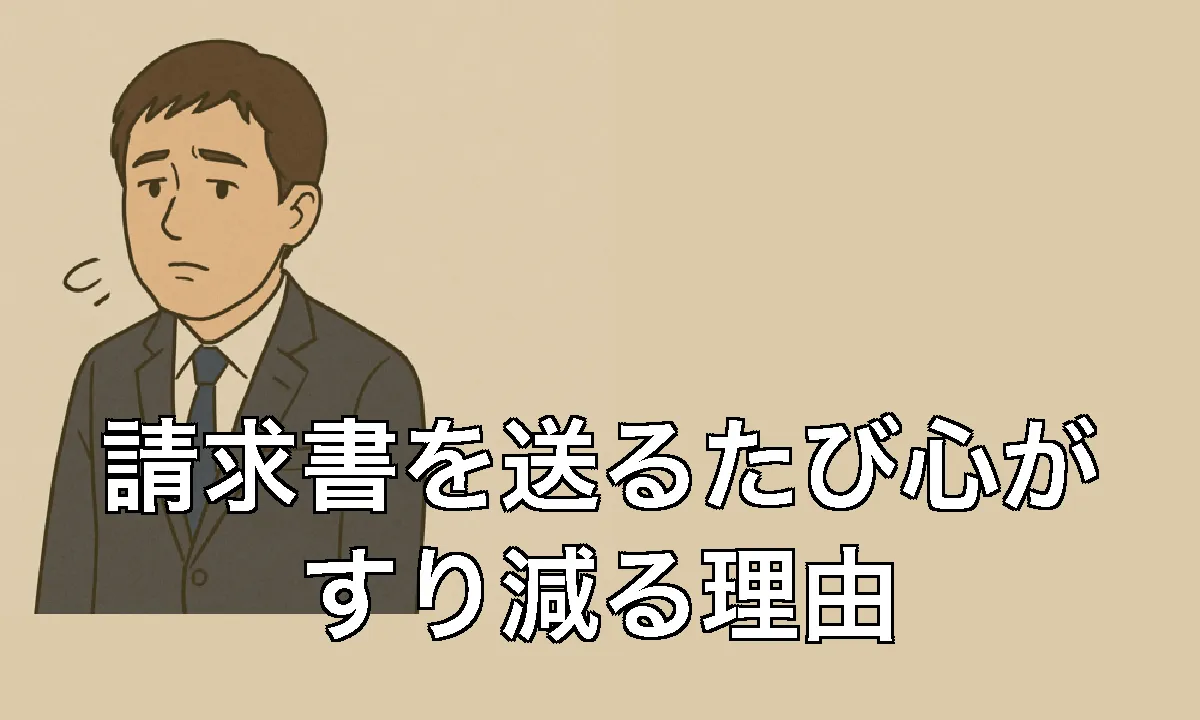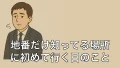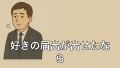仕事なのに心が追いつかない日がある
司法書士として日々業務に追われていると、仕事が単なる「作業」になってしまう瞬間があります。そのなかでも「請求書を送る」という業務は、単純であるはずなのに、どうにも気が重いのです。これは昔からそうでした。20代のころは、請求できることにすらありがたみを感じていたはずなのに、年を重ね、経験を積み、人との距離や関係性に敏感になってくると、請求書を出すたびに妙な孤独感が胸をよぎるようになりました。まるで自分の存在を確かめる代わりにお金を差し出しているような、そんな気分になるのです。
請求書を送るたびに感じる違和感
請求書をメールで送信する瞬間、わずか数秒の行為なのに、心がぎゅっと締め付けられることがあります。仕事だから当たり前、生活の糧なのだから当然——頭ではそう理解しているのですが、感情は別の動きをします。「お金の話ばかりして、嫌なやつだと思われたくない」「またお願いしづらいって思われるんじゃないか」そんな考えが頭をよぎり、手が止まることもしばしばです。私は基本的に優柔不断なタイプではありませんが、請求に関してだけは、今でも迷いが残ります。
ただの事務作業なのに気持ちが重い
一枚のPDFを添付し、「ご確認のほどよろしくお願いいたします」と書くだけ。それだけなのに、なぜか気持ちが沈むのです。学生時代、野球部で監督に怒鳴られていた頃は「やれと言われたことを素直にやる」ことが美徳でした。でも今は、自分の意思で動き、責任を背負い、そしてお金のことも含めてすべて自分で完結させなければならない。そこに妙なプレッシャーがあるのかもしれません。「これ、嫌がられてないだろうか?」そんな思いが、毎回少しだけ心をすり減らしていくのです。
「またお願いしづらい」と思ってしまう心の壁
請求するたびに、「次も依頼したい」と思ってもらえるのかが不安になります。依頼をこなしたのに、こちらが何か負い目を感じてしまうというのは矛盾しているようですが、実際そうなのです。相手にとっては「サービスを受けたら支払う」のは当然の流れのはずなのに、自分の中では「請求すること=嫌われる可能性」という図式ができあがっている。たとえ相手が何も気にしていなくても、自分の中で勝手に壁を作ってしまっている。その心の壁が、毎回ひとりでいる寂しさと妙にリンクしてしまうのです。
断られることより無反応がつらい
請求書を送ったあと、返信がなかなか来ないと、必要以上に心配してしまいます。「届いてないのか?」「不満だったのか?」と考え始め、結果的に自己嫌悪に近い状態になります。20代の頃の自分なら「まあそのうち来るだろ」と気にもしなかったでしょうが、今は返信が遅れるだけで、どこか自分の仕事の存在価値まで疑い出す。そんな自意識過剰な自分にもうんざりするけれど、それが現実なのです。
通帳残高よりも心残高の方が気になる
お金の出入りは帳簿で管理できますが、心の出入りは記録が残りません。売上があっても、手応えがないと空虚です。請求書を出して振り込まれても、それが“人としての繋がり”に感じられないと、数字だけが虚しく映るのです。通帳の数字が増えていても、誰かと信頼を築けた実感がなければ、心残高はマイナスに傾いていきます。「稼げた=満たされた」ではないのが、この仕事のややこしさでもあります。
なぜ「請求」が孤独につながるのか
本来、請求とは正当な対価を得るための行為です。でも、そこに感情が入り込むと、話は複雑になります。自分が“お金をもらう立場”になることで、相手と水平だった関係がどこか「上下」になった気がしてしまう瞬間があります。特に士業の世界では、「先生」と呼ばれることも多く、言葉の端々に上下のニュアンスがにじむ。そのたびに、「対等でいたかったのに」という想いがこぼれ落ちていくのです。
感謝と対価のバランスが崩れていく瞬間
「ありがとうございました」と言ってもらえたときの温かさと、「このたびはお世話になりました、添付にて請求書をお送りします」と書く冷たさ。そこに感情のギャップが生まれるのです。心のどこかで「ありがとう」が欲しいと思っている自分がいる。それに気づくたびに、「自分は何を求めているんだろう」と情けなくなります。プロである以上、感情を持ち込むなという声もありますが、それができるなら、こんなにすり減ってないはずです。
ありがとうの言葉と請求のタイミングのズレ
面談が終わり、業務が完了し、「助かりました」と言ってもらえたその直後に、請求書を出す——この流れにいつも違和感があります。感謝の余韻に水を差すようで、何とも言えない気持ちになります。それが商売なのですが、気持ちの上では「もう少し余韻を味わわせてほしい」と思ってしまうのです。感謝が「支払い義務」にすり替わってしまうような、このタイミングのズレが、孤独を生む要因なのかもしれません。
自分だけが「お金のことを言う側」になる苦しさ
こちらから「お金の話」を持ち出すとき、どうしても一方的な立場になります。相手から「いくらですか?」と聞かれるほうが、むしろ楽です。でも、士業という立場上、自分から提示するのが当然。言いづらさに耐えて金額を伝え、そのあとにくる沈黙に耐える。この一連の流れが、毎度地味にこたえるのです。相手は何も悪くないのに、自分の中でだけプレッシャーが膨らんでいく。この「一方通行感」が、孤独の根っこなのかもしれません。
請求書のメールを見返してため息をつく日々
送ったメールを見返して、「もう少し柔らかい文面のほうがよかったかな」とか「最後に一言添えればよかったかな」とか、あとになって反省することがよくあります。でも、そうやって自分の言葉をいちいち気にしていたら、業務が前に進みません。それでも気になってしまうのが、この仕事を“ひとり”でしているという事実を強く感じさせるのです。誰かと一緒に働いていれば、「これで大丈夫だよ」と言ってもらえるのに——そんなことを思いながら、またひとりで深夜に請求メールを見返してしまいます。
それでも仕事を続ける理由
そんなふうに、請求書一通でも心がざわつく日々ですが、それでも仕事をやめようとは思いません。なぜなら、誰かの役に立てたという実感が、どこかにちゃんとあるからです。声に出されなくても、メールの一言に救われることがある。自分の存在が、たしかに誰かの問題解決に貢献できた。その事実がある限り、また次の案件に向き合おうと思えるのです。心がすり減ることがあっても、そのぶん誰かの負担を軽くできたと思えば、少しだけ救われます。
小さな救いを見つける力
「丁寧なご対応ありがとうございました」「またお願いしたいです」——そんな一言をもらえるだけで、心は大きく持ち直します。人間って単純だなと思うけれど、そんな単純さに救われることが多い。自分の存在が誰かにとってプラスだったという実感。それが次の一歩を踏み出す勇気になります。孤独な時間があるからこそ、その一言の重みが身に沁みるのです。
たまにある「丁寧な返信」が心の支えに
請求書を送った後、相手から「こちらこそありがとうございます」と返信があった日は、不思議と眠りが深くなります。そんな小さな出来事が、日々の心の支えになっている。たとえ事務的な文章でも、「人」とのやりとりを実感できる瞬間に、心が癒やされます。事務員が一人しかいない職場では、誰かと分かち合えることが少ないからこそ、外からの言葉が貴重なのです。
ひとりじゃないと信じたい瞬間
司法書士は基本的に「ひとりで完結する」仕事です。でも、だからこそ、人とのつながりを信じたくなります。メール一通、言葉一つでも「この仕事は無駄じゃなかった」と思わせてくれる瞬間がある。そんな希望を手繰り寄せながら、今日もまた一通、請求書を送信するのです。