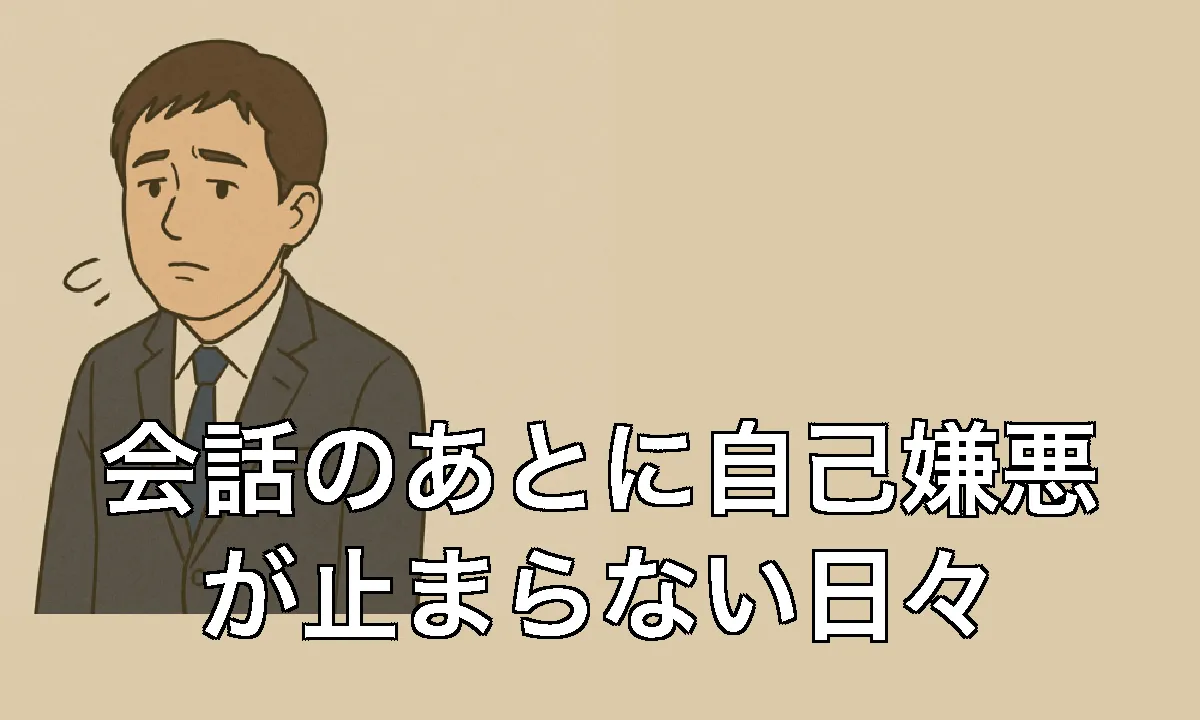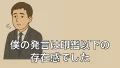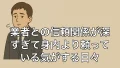会話のあとに自己嫌悪が止まらない日々
会話のあとに頭の中で再生されるセリフたち
誰かと会話したあと、自分の発言がずっと頭の中でリピートされることはないだろうか。私は昔からこの「反省癖」に悩まされてきた。たとえば依頼者との面談後、「あの説明はまわりくどかったかもしれない」とか、「もう少しやさしい言い方ができたのでは?」など、とにかく終わったことを何度も見直しては自己嫌悪に陥る。言葉を扱う仕事だからこそ、責任を感じすぎてしまうのかもしれない。だがこの癖、放っておくと精神的にも結構キツいのだ。
「あれ言わなきゃよかった」が夜中にやってくる
夜、布団に入ってようやく一息ついたころ、「今日あのとき、変なこと言ってなかったか?」という疑問がよみがえる。たった数秒の発言が、数時間にわたって頭の中を占拠する。しかも、たいてい相手は気にしていないことが多い。それなのに自分だけが延々と自己採点を繰り返す。過去の会話を思い出しては、採点、減点、反省。気がつけば午前2時。眠れぬ夜がまた一つ増えていく。こんな日々に、私はもう何度も「自分をやめたく」なった。
司法書士という職業柄、言葉に慎重になるクセ
司法書士という仕事は、言葉に重みがある。ひとつの説明ミスや、曖昧な表現がトラブルのもとになりかねない。だからこそ、私は常に「正確に」「丁寧に」「わかりやすく」を意識して話している。それでも、完璧にはならない。お客様の反応が少しでも曇ったように見えると、「今の説明、まずかったか?」と不安が走る。そしてその不安は、事務所に戻ったあとや帰宅後に何倍にも膨れ上がっていく。反省というより“強迫観念”に近いものがある。
何気ない一言で相手を傷つけたかもしれない不安
「お疲れ様です、今日は暑いですね」そんな日常のひと言ですら、私には地雷になることがある。もしかしたら、相手は気分が悪かったのに「暑い」なんて軽く言ったのが無神経だったかも…。こんなふうに、なんでもない言葉があとからじわじわと心を侵食する。考えすぎなのはわかっている。だが一度スイッチが入ると止まらない。どこかで「人に嫌われたくない」という気持ちが強すぎるのかもしれない。それがこの癖の根っこにあるのだろう。
反省というよりも“自責ループ”に近いもの
反省すること自体は悪いことではない。しかし私の場合、もはや「反省」の域を超えて「自責ループ」に入ってしまっている。頭の中で何度も「もっといい言い方があった」「あの表情は嫌がってたんじゃないか」と問い詰め続ける。これは反省ではなく、自分を責める行為だ。しかも出口がない。誰にも相談できず、自分の中でぐるぐると考え込んでしまう。結果として、自信が削がれていくのだ。
過剰に自分を責めてしまう思考回路
何かミスをしたわけではない。誰かに文句を言われたわけでもない。それでも「自分のせいだったかもしれない」と考えてしまう。これは、長年のクセというより、ある種の「思考パターンの固定化」かもしれない。反省ではなく、自動的に自分を悪者にしてしまう。そしてそれを繰り返すうちに、「何を話しても、また後悔する」と思い込んでしまう。まるで会話そのものが怖くなってくるのだ。
自己肯定感の低さと仕事のストレスの関係
自己肯定感が低いと、何をしても自信が持てない。私は日々、登記や相談業務に追われながら、「自分はちゃんとやれているのか?」という疑念を抱えている。依頼者の笑顔ひとつで安心したり、逆にちょっとした無表情で落ち込んだり…。そのアップダウンに疲れてしまうこともある。もしかしたら、この反省癖は、ストレスと自己評価のバランスの崩れから生まれているのかもしれない。
元野球部のくせにメンタルが弱すぎる問題
「元野球部」と言うと、よく「メンタル強そう」と言われる。でも実際はその逆だった。打てなかった日の夜、ベッドの中で「なぜ打てなかったのか」を反芻し、眠れない日も多かった。そのクセが今も続いているのかもしれない。体は大人になったが、心のクセは当時のまま。しかも司法書士になってからは、ひとつの発言が責任に直結するから、ますます慎重になってしまった。反省というより、「自分を守るための過剰防衛」になっている気がする。
事務員さんとの会話すら後で反省してしまう
うちの事務員さんは本当にしっかり者で、支えられてばかりだ。でも私のこの反省癖は、彼女とのやりとりにまで及ぶ。ちょっとした指示の言い方がきつかったかもしれない、余計なこと言ったかもしれない…。気にしていない素振りでも、私は心の中で「あの言い方、まずかったかな」と反省しっぱなしだ。相手が優しい人だと、余計に申し訳なくなってしまうのがこの性格のつらいところである。
気を遣わせたかもと勝手に落ち込む日
「何か気になることがあれば言ってくださいね」と声をかけたとき、事務員さんが「大丈夫です」と返した。その瞬間、私は「本当は何か我慢してるのでは?」と考えてしまった。完全に深読みの域だとわかっていながら、気になって仕方ない。帰宅後も、「もしかして自分の態度が冷たかったかも」と反省会を始めてしまう。本人が気にしていないのに、自分だけが勝手にダメージを受けている。非効率極まりない感情消耗戦である。
冗談が通じなかったかもという不安
事務所の雰囲気を和らげようと、軽く冗談を言ったときがあった。本人は笑ってくれたが、その笑顔が作り笑いだったような気がしてならない。「あれ、笑ってたけど、本当は傷ついたんじゃ?」と疑い始めると、もう止まらない。翌日もそのことばかりが頭をよぎり、「あんな冗談、言わなきゃよかった」と自己嫌悪に包まれる。職場で気を遣うのは当然だが、それが行き過ぎると、会話することすら怖くなってくるのだ。
相手のリアクションを深読みしすぎて疲弊
人の表情や間の取り方、目線ひとつで「あ、今のまずかったかも」と勝手に判断してしまう。たとえ相手が何も思っていなくても、私の中では「反省材料」がどんどん蓄積されていく。そのうち、話していても楽しくなくなってくるし、言葉を選びすぎて不自然になってしまう。これはもう、職業病なのか、性格なのか…。いずれにしても、日々の疲労感の原因のひとつには間違いない。
誰にも迷惑をかけていないのに苦しい理由
誰かに怒られたわけでも、トラブルが起きたわけでもない。それなのに「苦しい」と感じるのは、たぶん“自分で自分を追い込んでいる”からだ。完璧主義と自己責任感が強すぎると、こうなってしまうのだろう。無意識に「人に迷惑をかけてはいけない」と思い込んでいて、会話のすべてを精査してしまう。気がつけば、普通の雑談すら一大プロジェクトのような緊張感を持って臨んでいるのだ。
“完璧な受け答え”を目指すクセがついてしまった
司法書士という立場上、「言い間違い」「誤解を生む表現」は致命的だと教えられてきた。そのため、いつの間にか「完璧な受け答え」を常に目指すようになっていた。だが人間である以上、完璧は無理だ。わかっていても、ミスが怖くてたまらない。普通の会話ですら、“模範解答”を用意しようとする。だから少しでもズレた瞬間、すぐに自己嫌悪に襲われる。これはもう、心のクセになってしまっている。
仕事モードがオフにならない弊害
仕事中に気を張るのは当然だが、それを家にまで持ち帰ってしまうのが私の悪いクセだ。プライベートな会話でも、つい“業務的な目線”で発言をチェックしてしまう。そして「あの表現、曖昧だったな」「もっと丁寧に伝えればよかった」といった思考が始まる。気づけば、休日も仕事脳のまま。これでは心が休まらない。会話すら業務化してしまっては、人生の楽しみが薄れてしまうのに。
自分で自分の粗探しをしてしまうクセ
周りの人は私にそれほど期待していないのに、自分だけが「もっとよくできたはず」と責めてしまう。いわば、自分で自分の粗探しをして、勝手に減点しているようなものだ。このクセが続くと、自己肯定感がどんどん下がっていくし、新しい挑戦にも臆病になる。反省ではなく、単なる“心の消耗”になってしまうのだ。
反省癖とうまく付き合うために
この反省癖は、急には治らない。けれど、うまく付き合うことはできると最近思えるようになってきた。大事なのは「自分を責めすぎないこと」「完璧を求めすぎないこと」。ちょっとした失敗や後悔も、長い目で見ればどうってことない。そう考えられるようになってきたのは、自分なりに失敗を重ねてきたからだろう。今後も、反省はする。でも、“自責”は手放していこうと思っている。
「まあいっか」の口ぐせを意識的に取り入れる
最近、反省が始まりそうになったら「まあいっか」と口に出すようにしている。最初は無理やりだったけれど、言葉に出すことで少し気持ちが軽くなる。これを繰り返すうちに、「完璧じゃなくてもいい」と思えるようになってきた。自分に対しても、他人に対しても「まあ、そんなもんだよね」と思えるだけで、ずいぶん楽になった。
心の中の“ひとり裁判”を中断する方法
会話のあとに反省が始まると、まるで自分を被告人として裁く“ひとり裁判”が始まる。でもそれ、だれが求めてる?誰にも迷惑かけてないなら、審理打ち切りでいい。私はそう決めて、「その裁判、終了です」と心の中で宣言するようにしている。思考を止めるというより、止める“決定権”が自分にあると気づくだけで、気持ちが変わるのだ。
完璧主義よりも“まあまあ主義”でいこう
もう一つのコツは、「完璧主義」から「まあまあ主義」への転換だ。誰かに嫌われたっていい。冗談がすべらたっていい。相手がちょっと不機嫌でも、それが自分のせいじゃないこともある。自分にできるだけのことをしたなら、それで十分。司法書士という職業柄、真面目になりがちだけれど、ときには“テキトーさ”も必要だ。そうでないと、心がもたない。