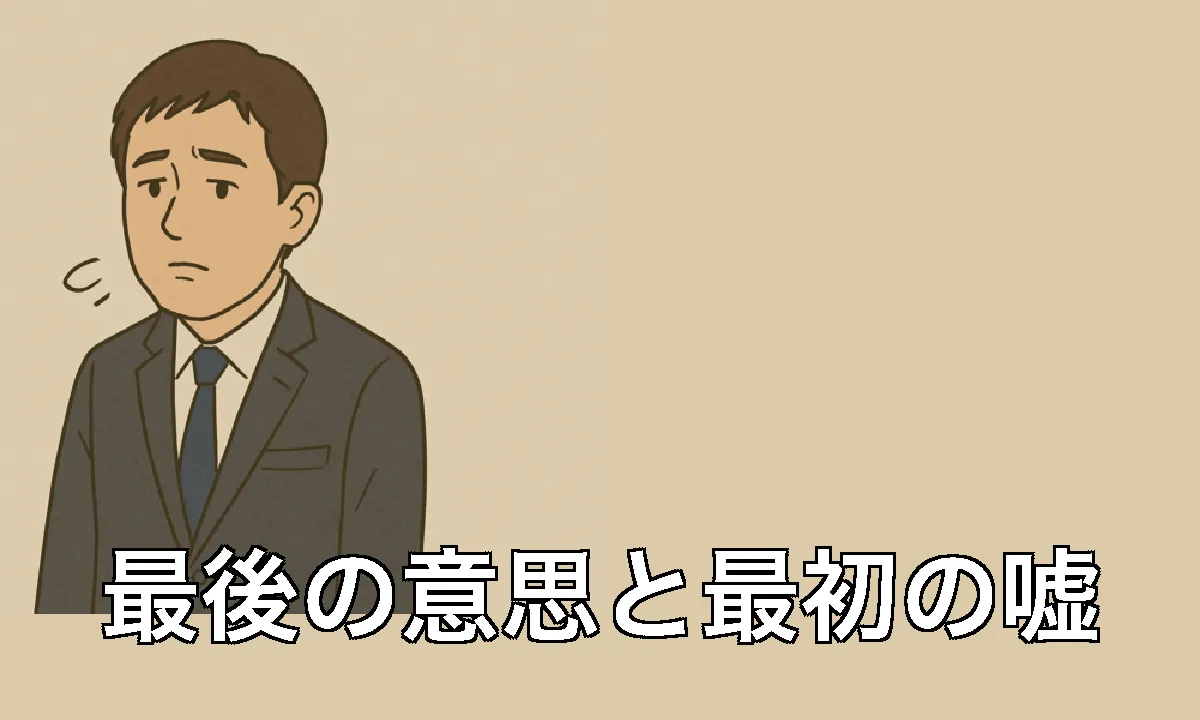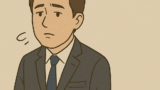午前九時の相談者
夏の光がまだ柔らかい午前九時。事務所のドアが控えめに開き、初老の女性がゆっくりと入ってきた。手には古びた封筒を持っており、少し緊張している様子だった。 「遺言と、生前贈与について、ご相談がありまして…」と、小さな声で告げた。
遺言か生前贈与か悩む女性
話を聞けば、亡き夫から受け取ったという不動産と預金について、自分の姪に託したいという。だが遺言で済ませるか、生前に贈与するか決めかねているようだった。 「昔、公証役場に行ったこともあるんですが…どこまで有効なのか」と彼女は眉をひそめる。
封筒に挟まれた古い契約書
彼女が差し出した封筒の中には、30年前の公正証書と、手書きのメモが挟まれていた。筆跡は乱れていたが、そこには「死後、全てはミキに渡すように」とだけ書かれていた。 しかし、法的にはそのメモは遺言とみなされない。
相続人の影
午後、若い男が事務所に現れた。「あの土地、俺の親父のものだったんですよ」と言って、驚くほど詳しく状況を語り始めた。 その男は、女性の亡夫の息子だと主張していた。
息子と名乗る男の訪問
その男、佐々木と名乗ったが、戸籍上の繋がりが曖昧で、認知された形跡はなかった。だが、妙に自信満々だった。 「生前に口約束があったんですよ、全部俺にくれるって」と言い残し、書類の写しを置いて帰った。
登記簿から消えた名前
こちらでも確認したが、佐々木の名前はどの登記にも記録されていない。父親の名義のままになっていた土地は、現在、相談に来た女性の名義に変更されていた。 何かが引っかかる。記録と証言が噛み合わない。
生前贈与の落とし穴
生前贈与には贈与契約書が必要で、場合によっては贈与税の対象にもなる。だが、今回のように意思が明確でなく、相手が複数いる場合、むしろ争いの火種になる。 公正証書だけでは、確実な遺言にならないのだ。
公正証書が語る真実
30年前の公正証書を精査すると、財産を「妻に託す」と書かれていたが、個別の財産名は一切記載されていなかった。 つまり、一般的な相続の話に過ぎず、贈与とは呼べない。
一通のFAXが示す別の遺志
サトウさんが黙って一通のFAXを差し出した。そこには、亡夫が5年前に金融機関に送った書面が印刷されていた。「資産の管理は姪に任せる」と書いてある。 しかしそれも、単なる依頼に過ぎなかった。
やれやれ、、、探偵役はいつも僕だ
座ったまま伸びをして、僕はコーヒーに手を伸ばした。「やれやれ、、、こんな面倒な話、誰が得するんだろうな」とぼやいた。 すると、サトウさんが冷たく「得したい人が、動いてるんです」と呟いた。
サトウさんの冷たい推理
「息子さんの話、正確すぎるんですよ。生前の会話を録音でもしてたような…」と彼女は睨む。「たぶん、口約束を録音して、証拠にするつもりだったんじゃないですか?」 言われてみれば、妙に詳細だった。
振込履歴が鍵を握る
金融機関に確認したところ、亡夫から佐々木への送金履歴が複数確認された。だが、名目はすべて「貸付金」となっていた。 贈与ではなく、あくまで貸し。つまり返済義務が残っている。
境界を越えた贈与
贈与と遺贈。生前と死後。その線引きは簡単ではない。だが、佐々木の主張は、すべて「もらった」と思い込んでいるだけだった。 法的根拠がない限り、感情だけでは境界は越えられない。
名義変更のタイミング
登記の名義が変更されたのは、亡夫が亡くなる数ヶ月前。その時点で、すでに認知症の兆候があり、判断能力に疑問が残った。 サトウさんは静かに「それ、後で問題になりますよ」とだけ言った。
預金口座から消えた百万円
決定打となったのは、預金口座の出金履歴。亡夫が亡くなる直前に、100万円が引き出されていた。 そのお金が、佐々木の口座に現金で入金されていたのだ。
真実と嘘の境界線
法的には、証拠がなければ「贈与」は認められない。遺言書がなければ「遺贈」も成立しない。 つまり、思い込みや感情がいくら強くても、事実には勝てない。
封筒の裏に書かれた日付
最初の封筒の裏には、鉛筆で書かれた日付があった。それは亡夫が亡くなる前日だった。 サトウさんは言った。「これ、相談者が書いたんじゃないですか?」
証言を変えた証人
公証人に確認をとると、実際に立ち会った人物は相談者の妹だった。だが、彼女は後日「あのとき姉が勝手に書いた」と証言を変えた。 つまり、姪に託すという遺志は、姉の思い込みだった可能性が高い。
遺言の正体
結局、法的に有効な遺言は存在しなかった。あるのは「託したい」という漠然とした思いと、それを利用しようとする者の影。 書類は嘘をつかないが、人間はつくのだ。
依頼人の本当の願い
相談者は最後にこう言った。「私はただ、ミキにちゃんと残したかっただけなの」 その言葉に、僕は少しだけ迷ったが、登記の手続きを淡々と進めることにした。
公証人が握る最後の鍵
数日後、公証人から届いた書面にはこう書かれていた。「本件は遺言ではない。本人が『願望として』述べたものである」 つまり、法的拘束力はゼロだった。
終わりと始まりの境界で
事件は終わった。だが、誰も満足していない。佐々木は去り、相談者は泣き、ミキは何も知らないままだ。 「やれやれ、、、」と、僕はまた一つ書類を閉じた。
登記完了と、静かな涙
登記完了通知が届いた日、相談者はふと「これで夫も安心できるかしら」とつぶやいた。 その目には、静かな涙が浮かんでいた。
サトウさんのやさしくない笑顔
「なんだか、やるせないですね」と僕が言うと、サトウさんは珍しく笑った。 「人って、最後に自分を正当化したくなるんですよ」とだけ言って、机の引き出しを閉じた。