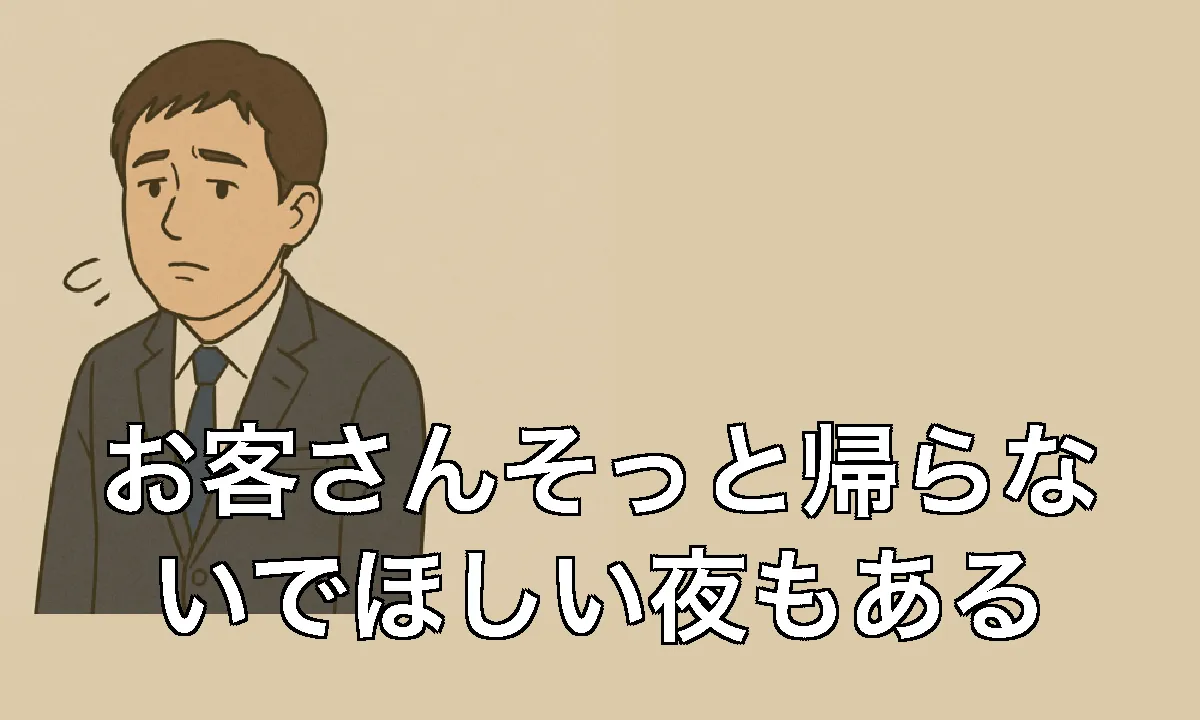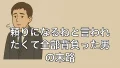玄関の音だけが教えてくれるお別れの気配
司法書士という仕事柄、書類を整えて登記が終われば業務としては一段落。しかし、ふと気づくと「ありがとうございました」とだけ言って、そっと帰っていくお客さんがいる。こちらとしては、まだ話したいことも、伝えたかったこともあるのに、空気を読んでか、遠慮してか、足早に去っていくその背中が寂しくてたまらない。玄関の引き戸の閉まる音だけが、すべてを終えたことを教えてくれる。やるべきことは果たしたのに、どこかやり残したような気持ちが胸に残る。
気づけば静かに姿を消すお客さん
ある日、忙しさのあまり目の前の書類整理に没頭していたら、お客さんが「じゃ、これで」と言って立ち上がった。顔を上げたときには、すでに靴を履いている。引き止める間もなく、軽く頭を下げて帰っていった。その瞬間、まるで“会話の途中で通信が切れた”ような気持ちになった。こちらがもっと親身になっていれば、もう少し話してくれたんじゃないか、と反省が渦巻く。
言葉のないさよならが胸に残る
世の中には、必要最低限の会話だけで済ませたい人もいる。それはわかっている。けれどもこちらは、仕事以上に“人として”関わりたかったと思ってしまう。無言のさよならほど、印象に残る別れはない。何も言わずに帰っていくお客さんの姿が、数日後もふと脳裏によぎるのだ。「あの方、満足してくれただろうか」と。
こちらの未熟さを突きつけられる瞬間
こういう別れ方に出会うたび、自分の力不足を感じる。「忙しそうだったから早く帰った方がいいと思いました」なんて言われると、なんとも言えない気持ちになる。お客さんに気を使わせてしまうような空気を出していたのだとしたら、それは完全にこちらの責任。司法書士としてだけでなく、人として未熟だなと落ち込む。
そっと帰られるたびに自己否定が顔を出す
ただの業務処理ではない、人の人生に関わる仕事をしているのに、相手との心の距離が遠いと感じると、自分の存在意義に疑問が湧いてくる。言葉を交わす時間も、気持ちを通わせる余裕もないまま終わる面談に、自己肯定感がズタズタになる日もある。そんな日は、事務所の照明を落とした後、一人でため息をつくことが多い。
忙しさにかまけて本音を見落としていた
数年前のこと、相続の相談で来られた女性がいた。何度か来所され、淡々と手続きが進み、無事に完了。そのときも「ありがとうございました」と言って静かに帰られたが、後日別件で来られたとき、「あのとき実はけっこう辛かったんです」とポロリと本音をもらした。その一言に、胸が締めつけられた。私は何を見ていたんだろう、と。
「あの対応で良かったのか」と夜中に反芻
あの時こう声をかけていたら、もう少し話を聞けていたら。終わった案件に思いを馳せて眠れない夜がある。業務的には正確で、ミスなく処理しているはずだ。でも、それだけで本当に良かったのか。誰にも文句は言われていない。けれど、自分の中で納得できていない。こうしてまた、思考は深夜の暗がりに潜っていく。
気配に敏感になりすぎてしまう日々
最近は、お客さんの靴の向きや荷物の置き方、座る姿勢にまで神経を使うようになった。ちょっとした視線の動きや沈黙に、「もしかして不満なのでは」と敏感に反応してしまう。気を使いすぎて空回りすることもある。でもそれでも、帰り際に少しでも笑顔が見られれば、それだけで今日は報われたと思える。
「また来ます」と言われることの尊さ
「また来ますね」と言われると、こちらとしては思わず顔がほころんでしまう。たとえその後一度も来なかったとしても、その一言には「ここにいていいんだ」と思わせてくれる力がある。仕事柄、リピーターが多いわけではないけれど、それでも「また」という言葉に込められた信頼の余韻は長く残る。
たった一言で救われる気持ちがある
あるとき、面談が終わった直後に「先生、来てよかったです」と言われたことがある。その一言で、それまでの疲れがスッと溶けていった。手続きの煩雑さ、役所とのやり取りのストレス、全部吹き飛ぶくらいの威力だった。どんなに多忙な日でも、あの瞬間だけは「やっててよかった」と思える。
心の距離を埋めるために必要な一歩
結局のところ、どれだけ正確に処理できても、人としての関係が築けないと虚しさは残る。事務的なやり取りだけで終わってしまう日々に、少しでも心を寄せる努力をしなければ、機械でもできる仕事に成り下がってしまう。ほんの一言、目を見て伝えるだけで、その距離はぐっと縮まる。
言葉がなくても伝わるものがあるとは思うけれど
全てを言葉で伝えるのは難しい。表情や仕草で伝わるものもある。でもやっぱり、口に出してくれるとこちらは安心するし、励みになる。「そっと帰らないでください」とは言えないけれど、「またお会いできると嬉しいです」とこちらから伝えることはできる。少しずつ、こちらから歩み寄っていくしかないのかもしれない。
仕事はこなしても心は置いてきぼり
司法書士の仕事は、言ってみれば書類で完結する。でも、人の心はそんなに単純じゃない。登記が終わっても、そこには必ず誰かの背景がある。大切な人を亡くした悲しみ、家を買った喜び、離婚を決めた決意。そこに寄り添えなかったと思うと、自分の存在が希薄に感じてしまう。
登記完了の報告メールだけじゃ足りない
「登記が完了しました」というメールを送って、はい終わり。そんな簡単な話じゃない。特に相続や離婚など、人生の転機に関わる手続きは、形式的な終わりだけでは片付けられない。相手が「ちゃんと受け止めてもらえた」と思えるような終わり方をしたい。効率重視のやり方に、どこか違和感を覚えてしまうのだ。
顔を見て「ありがとう」と言いたいだけなのに
「また来ますね」と言われなくても、せめて「ありがとうございました」と笑顔で言いたい。でもその機会すらないまま、そっと帰られることが多い。こちらが話しかける隙もなく、扉が閉まる音だけが残る。何のために頑張ってきたのか、自問してしまう夜もある。
誰かの役に立つってこういうことじゃないのか
誰かの役に立ちたくて司法書士になった。でも今、目の前にいる人の“心”には触れられていないのではと感じる。役所に提出するだけの書類なら、正確でさえあれば誰が作っても同じかもしれない。でも、こちらがその人の人生の一部に関わったと感じられる瞬間、それがこの仕事の醍醐味だったはずだ。