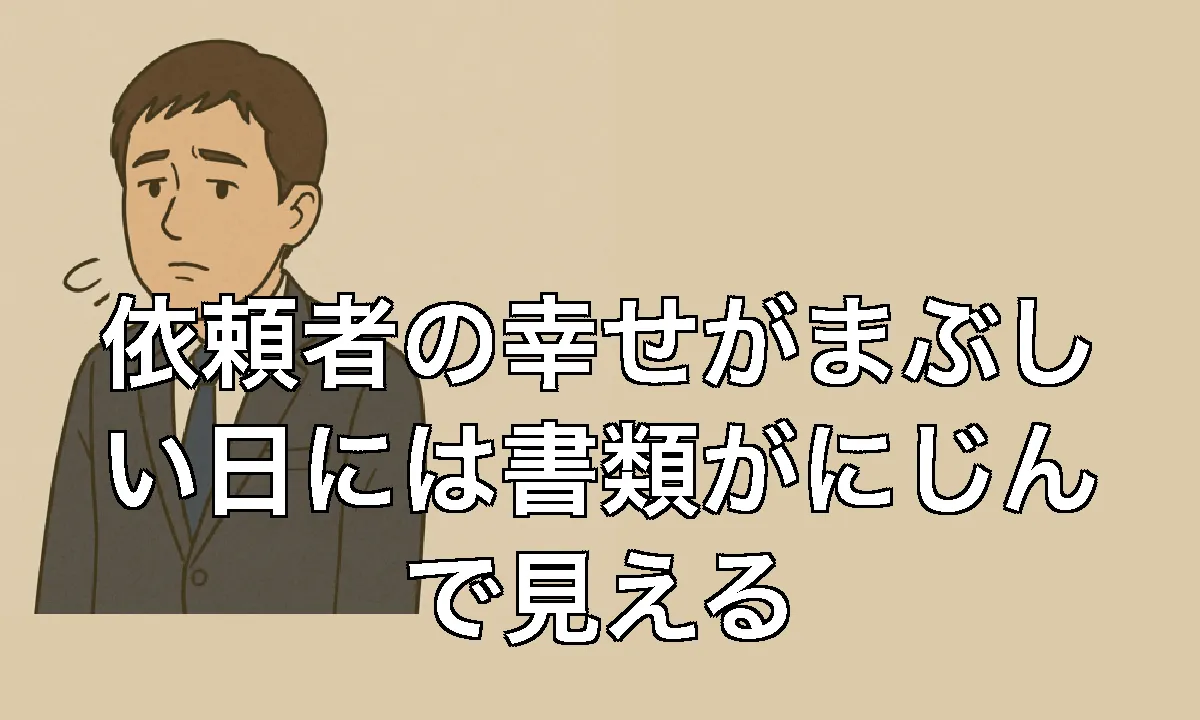笑顔の先にあるものを見てしまう癖
登記の相談を受けるとき、相手がカップルだったり新婚さんだったりすることがある。そんなとき、私は決まって笑顔で応対するが、心のどこかでは「またか」と思ってしまう。二人で並んで「よろしくお願いします」と言われた瞬間に、こちらの胸がちくりと痛む。まるで、自分がその幸せの外に取り残されているかのような感覚になるからだ。仕事なのだから当然だし、祝福されるべき相手なのもわかっている。それでも、つい見えなくていいものまで見てしまうのだ。
手続きを終えた依頼者の晴れやかな表情
「これでようやく新居の手続きも完了ですね」と伝えると、依頼者は満面の笑みで「ありがとうございます」と頭を下げる。何度も見てきた光景だ。それでも、心がざわつくのはどうしてだろう。何かを終えた達成感と、これから始まる人生への希望が、その表情にはにじんでいる。私はその場にいながらも、まったく別の場所にいるような気がしてしまう。まるで試合に出してもらえなかったベンチの選手みたいに。
婚姻届のついでに登記の依頼というリアル
「役所に婚姻届出した帰りなんです」と話してくれたカップルがいた。幸せそうに肩を並べて、書類にサインする二人。私はその横で淡々と確認作業を進めていたが、書類に手を添えるその指先が、なぜか震えていたのを覚えている。自分でも驚くくらい、羨望と疎外感が入り混じった気持ちになった。書類がにじんで見えたのは、蛍光灯のせいではないと自分でもわかっていた。
「お幸せに」と言いながら胸がチクリとする
書類が揃い、印鑑を押し終えたとき、「お幸せに」と言葉をかける。何百回も言ってきたそのひと言が、どうにも自分には似合わない気がしてしまう。口では笑っていても、心は正反対の方向を向いているような居心地の悪さ。独身で、彼女もいない自分には、その言葉の重みすら分かっていないのではないかという不安まで感じる。優しさの仮面をかぶりながら、自分の居場所を探しているのかもしれない。
祝福の言葉が口をすべるようになった理由
司法書士として長く仕事をしていると、言葉選びにもある程度の型ができてくる。「おめでとうございます」「良いスタートになりますように」——そんな定型文のような言葉が、自然と口をついて出るようになった。だが、それは果たして本心から出ているのか、時々自問する。慣れとは怖いもので、本心を隠すのにも便利な道具だ。
司法書士としての慣れと不器用な優しさ
「気持ちがこもっていない」と思われたくなくて、つい声のトーンを上げてしまったり、笑顔を無理に作ってしまう。そんな自分が、時々嫌になる。だが、依頼者にとってはたった一度の大事な手続きの日。プロとして接するしかない。優しさとは、時に不器用さと表裏一体で、それが逆に自分の心をすり減らしていく。
「おめでとうございます」そのひと言が苦い
「おめでとうございます」と言った直後、自分の心の中で「何が?」とつぶやいてしまうことがある。心がささくれているのだろうか。そんな自分に後味の悪さを感じながらも、また次の依頼へと移っていく日常。まるで自動販売機のように、同じフレーズを吐き出し続ける自分に嫌気がさす瞬間だ。
ふとした瞬間に湧き上がる孤独感
事務所に戻ると、事務員が淡々と仕事をしている。その姿を見て、安心しながらも、急に静寂が重たく感じることがある。誰かの幸せを手伝った帰り道、自分の存在が薄く感じてしまう。夜の帳が下りるころ、その孤独感はますます色濃くなる。
事務所に戻れば山積みの書類と自分だけ
依頼者が帰って静かになった事務所に、再び書類の山が待っている。その紙の重さが、なぜかいつも以上に肩にずっしりくる。こんな日に限って、なぜかプリンターまで紙詰まりを起こす。些細なことがやけに腹立たしく思えるのは、きっと心がすり減っている証拠だ。
事務員の気遣いに救われつつも空回り
「お昼、買ってきましょうか?」と事務員が気を遣ってくれる。その気持ちは嬉しいのに、「大丈夫」と言ってしまう自分がいる。誰かの優しさを素直に受け取れない。たぶんそれが、今の自分の限界なのだ。自分の感情を処理しきれず、相手にどう返していいのか分からないまま、また一人で昼ご飯をかきこむ。