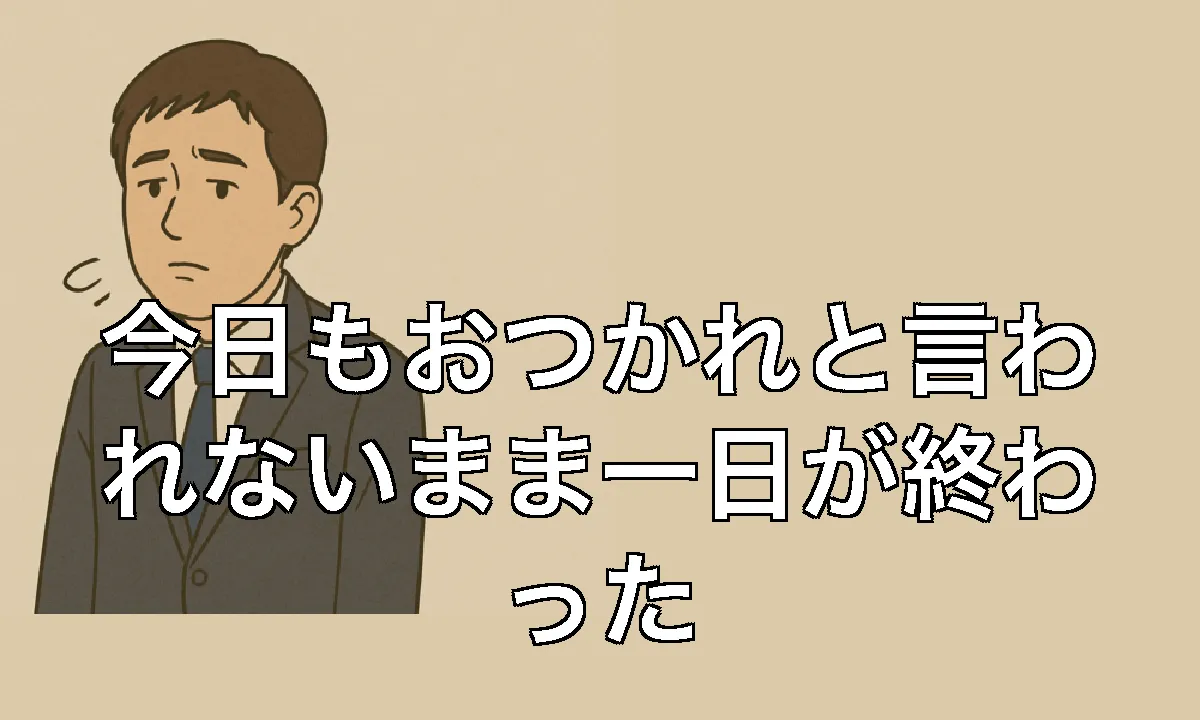今日もおつかれと言われないまま一日が終わった
誰にも気づかれない疲れが積もっていく日々
司法書士という仕事は、人の人生の節目に立ち会うものだ。登記や契約書、遺言に相続……手続きを淡々とこなし、感情を込めることなく処理していくのが仕事の基本。でも、ふと気づいたとき、誰からも「おつかれさま」と声をかけられないまま今日も終わっていた。仕事が終わるたび、あの一言があればどれほど救われるか。ひとり事務所に残って書類をまとめる音だけが響く。静けさが、疲れをごまかすことを許してくれない。
おつかれさまの一言が心のバロメーターだった
昔は「おつかれさま」が日常の中にあった。コンビニでバイトをしていた頃も、野球部の練習の後も、友達と飲みに行った帰り道も、自然と誰かが言ってくれていた。たった5文字のあいさつが、自分が誰かとつながっていた証だった気がする。いまの生活には、その5文字がごっそり抜け落ちている。誰かにねぎらってもらうことで、「自分は今日もちゃんとやれた」と確認できたのに、今はその判断を自分だけでしなきゃいけない。
昔は当たり前にあったねぎらいの会話
野球部の頃、練習が終わると決まって「おつかれ」と声が飛び交っていた。ミスした日も、走り込んだ日も、グラウンドから更衣室へ向かうその短い時間に、互いの存在を認め合うような「おつかれ」があった。今思えば、それがどれだけ心を軽くしていたか。仕事では結果が出ても誰も拍手をくれるわけじゃないし、うまくいかなかったとしても誰かが寄り添ってくれるわけでもない。あの頃の「声」は、もうどこにも残っていない。
事務所に戻っても誰もいないという現実
登記の提出を終えて事務所に戻ると、時計はもう19時を過ぎている。事務員は定時で帰っているし、依頼人からの電話も鳴らない。デスクには朝のコーヒーの空き缶だけが残っていて、それを片付けながら、自分で自分に「今日もよくやったな」と言ってみる。けど、なんだか空しい。言葉は出ていても、耳がそれを他人の声として認識しない。自己完結では、感情に折り合いがつかないこともある。
一人でやって一人で終わる仕事のむなしさ
独立してから、良くも悪くもすべてが自己責任になった。喜びも苦しみも、成果も失敗も、自分ひとりの中で完結する。誰かと分かち合う機会は少ない。忙しさにかまけて気づかないふりをしてきたが、ふと立ち止まると「今日、自分は誰と話した?」と疑問が浮かぶ日もある。法律を扱う職業なのに、感情の整理には不器用な自分がいる。
登記が無事に通っても誰も知らない
何件もの書類を仕上げ、法務局に提出し、無事に登記が完了したときの安堵感は、それなりに大きい。でも、その喜びを誰かと分かち合うことは、ほとんどない。依頼人からの「ありがとうございました」はあっても、それは感謝であって、労いではない。仕事として当然という空気がある以上、「おつかれさま」と言ってもらえる立場ではないのかもしれない。
成功が積み上がっても孤独は減らない
売上が伸びても、顧客が増えても、孤独感には変化がない。数字では満たされない何かが確実にある。かつては人と競い、人と励まし合うことが当たり前だったのに、今は競う相手も、励まし合う仲間もいない。司法書士という仕事の本質に孤独が含まれていることは、分かっていたつもりだった。でも、慣れることと麻痺することは違うと最近ようやく気づいた。
事務員との会話すら業務連絡止まり
うちの事務員は、よくやってくれている。ミスも少ないし、時間内にしっかり帰る。その姿勢には敬意を持っている。でも、会話はどうしても業務連絡に終始する。「書類できました」「こちら送付しました」──それ以上踏み込むとお互い気まずくなる空気がある。自分が壁を作っている自覚もあるが、それを壊す余裕もないのが現実だ。
仕事はできるが心が交わらない距離感
こちらも歳を取ったのか、妙に気を遣うようになってしまった。年下の女性事務員に対して、余計なことを言ってセクハラ扱いされたらどうしよう、そんな思いが先に立ってしまう。結果、必要最低限の言葉だけが飛び交う日々。業務はスムーズでも、心がまったく通っていない気がしてならない。なんだかロボットと一緒に働いているような錯覚さえある。
ありがとうとは言えるがおつかれとは言いにくい
「ありがとう」は口に出せる。でも「おつかれさま」は、なぜか言いにくい。自分が言えば、相手も返してくれるだろうとは思う。でも、その言葉を交わすことで、妙な距離が縮まったように感じてしまう。そんな感情が、今の事務所には似合わない気がしている。変な話だけど、感情をやりとりすること自体が、少し怖いのかもしれない。
結局のところ自分の仕事にしか興味がない
こうして毎日を過ごしていると、自分が誰にも興味を持たれず、そして自分も誰にも興味を持てていないことに気づく。効率を求めた先に、人間関係の乾きがある。お互いに最低限の役割をこなすことだけで回っている事務所。それはそれで正しいのかもしれない。でも、そこに「おつかれさま」の余白は、存在しない。
過去の声を思い出してしまう夜
夜、ひとりでコンビニ弁当を食べているとき、不意に昔の誰かの声を思い出すことがある。「おつかれ」って言ってくれたあいつ、あの頃は何の苦もなかったなと。もう会うこともない人たちとの記憶が、疲れた頭にふわりと浮かんでくる。言葉は、記憶に残る。だからこそ、今それがないことが、余計にしんどく感じる。
野球部時代は毎日誰かがおつかれと言ってくれた
高校の野球部。毎日しごかれて、ヘトヘトになったけど、最後のミーティングで「おつかれ」と先輩に言われるのが妙に嬉しかった。走るのも、投げるのも、ただの練習なのに、誰かと一緒だった。それが救いだった。いまは全部ひとりでこなす。一言の「おつかれ」が、こんなにも大切な言葉だったとは、あの頃は気づけなかった。
チームで過ごしたあの時間が今になってしみる
チームってすごかったなと今更ながら思う。誰かが調子悪ければ、カバーするやつがいた。ミスすれば、肩を叩いて笑ってくれるやつもいた。今の職場では、自分がミスしたら誰も気づかない。カバーもしてくれないし、叱ってもくれない。だからこそ、当時の「おつかれ」が骨身にしみる。あれは言葉じゃなくて、気持ちの共有だった。
一人で頑張ることを選んだはずなのに
独立を選んだのは自分だ。誰にも指図されずに働きたくて、ひとりで自由にやりたかった。でも自由と孤独はセットだった。いまさらながら、「おつかれ」と言ってくれる誰かの存在を、強く求めてしまう自分がいる。それでも明日もまた、声なきまま、書類とにらめっこをするのだろう。結局、今日もおつかれと言われないまま、一日が終わる。