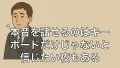法務局でしか人に会ってない気がする日々
気づけば法務局が一番の社交の場になっていた
仕事柄、法務局には頻繁に通う。週に一度どころではない。気づけば毎日のように訪れ、受付の方の顔を自然と覚え、向こうもこちらの名前を憶えてくれている。そんな関係になったのはいつからだっただろう。世間話のひとつも交わせるようになった頃には、もはやコンビニより親しみがある場所になっていた。人との接点がここしかないという現実に、最初は笑っていたが、最近では少し切なさすら感じる。
平日毎日のように顔を出す場所
登記関係の仕事が集中する時期には、1日に何度も足を運ぶ。午前中に1回、午後にも1回。申請、補正、事前確認。出入りしている間に「またお会いしましたね」と言われることもしばしば。まるで出勤しているかのような錯覚に陥る。人と話す機会がない一人仕事の中で、この法務局への出入りが、唯一の「外との接点」になってしまっているのが現実だ。
書類と一緒に挨拶も交わす
「お疲れ様です」と言って申請書類を差し出す。その一言が、思った以上にありがたい。誰かと交わすたった数秒の会話が、精神的な支えになっている自分に気づく。窓口の方に名前を覚えられ、「今日は多いですね」と言われるたび、ああ、自分はここでしか存在を認識されていないのかもと感じてしまう。仕事であっても、人と人のやり取りに救われているのだ。
常連同士の無言の気まずさ
他の司法書士さんともよく顔を合わせるが、なぜか言葉は少ない。互いに忙しいのもあるし、どこか照れくささもある。何より、皆同じように疲れた顔をしているのが印象的だ。法務局という公共の場で、互いに「また来たか」と思いながら、あえて言葉にしない。無言で待合の椅子に並び、目も合わせずにスマホをいじる。不思議な共通認識のある空間だ。
結婚相談所の資料を見た日と法務局での雑談
ある日、友人から「いい加減、婚活でもしたら?」と結婚相談所のパンフレットを手渡された。半ば冗談かと思ったが、ちらっと目を通すと、現実が突きつけられてくる。しかしその後、法務局の窓口で「今日も暑いですね」と言われた瞬間、妙にホッとした。なんだかんだで、そっちのやり取りの方がリアルで、心が動く。婚活の世界は、どうも他人事のように感じてしまう。
高すぎる理想より現実のやり取り
パンフレットには「理想の相手像」を書く欄がある。「優しくて家庭的で…」と並べようとしたが、そもそも自分自身がどんな人間かすらよくわかっていない。法務局でのやり取りのように、日々の中で自然に誰かと会話し、笑ったり困ったりする関係の方が、ずっと大事な気がする。現実の世界では、プロフィールの条件よりも、ほんの一言の言葉のほうが重みがある。
ちょっとした世間話に救われる
「雨降ってきましたね」「ここの窓口、最近混んでますね」。たったそれだけの会話が、どれだけ心のバランスを保ってくれているか。孤独な仕事だからこそ、こうした日常のかけらが、心の栄養になる。婚活より先に、まず人と自然に話すスキルが落ちていないか心配になる今日この頃だ。
出会いの場がズレているという感覚
世間の人たちが出会いを求めて街コンやアプリで動いている中、自分は法務局で人に会っている。しかも恋愛感情なんてものは一切なく、ただの業務の一環。でも、ふとした瞬間に「もしかして、この出入りが自分の社交のすべてなのでは」と思うことがある。そしてそれが何だか、少し悲しい。
婚活より登記のほうが数をこなしている
年に何件、何十件と登記を処理しているのに、出会いの数はゼロに等しい。これだけの人の人生に関わっていながら、自分の人生は誰にも関わられていない気がする。婚姻届じゃなく、登記申請書ばかりを見ている日々に、妙なギャップを覚える。
でも成果はゼロに近い
出入りの数だけなら婚活イベントに参加している人より多い自信がある。でも、そこに芽生えるものは何もない。会話はあっても、関係性は生まれない。目的が「登記」である以上、感情は持ち込めないし、持ち込んではいけない。プロとして、あくまでドライでなければならないのだ。
優しさは登記簿に書けない
どれだけ丁寧に仕事をしても、そこに「優しさ」という項目はない。名前も住所もはっきりしているのに、自分の存在だけがふわっとしているような不思議な感覚になる。「この人、優しいですね」と言われたことはあっても、それが何かに残るわけではない。優しさは見えづらいし、記録もされない。
事務員との日常とそれ以上にならない距離
事務員さんとは毎日顔を合わせるが、そこにはしっかりとした線が引かれている。職場としての秩序は保たれているし、何よりお互いに変な気を使ってしまう。気を使いすぎるあまり、ちょっとした雑談すらぎこちない。気まずくない程度に距離を取り続けるのも、地味に疲れるのだ。
気を遣いすぎて余計に疲れる
「飲み物買ってきましょうか」と聞かれても、「あ、じゃあ…いや、大丈夫です」と答えてしまう。気を遣われているのが分かるからこそ、素直に甘えられない。仕事上のやり取りは問題なくても、人間関係となると途端にぎこちなくなる自分に、情けなさを感じる。
話しかけるタイミングが読めない
忙しそうにしているとき、話しかけるべきか迷う。そして、迷っているうちにその瞬間を逃す。結局、気づけば1日中ほとんど会話を交わさないまま終わっていることもある。こんな毎日が積み重なると、「話さないこと」に慣れてしまう。それが一番怖い。
昔はモテた気がする元野球部の思い出
高校時代、野球部だった頃は多少なりともモテた記憶がある。引退試合の後に応援してくれた女子生徒に手紙をもらったこともあった。でも、それはもう遠い過去。今はユニフォームも着ていないし、筋肉もすっかり落ちた。鏡に映るのは、疲れた中年の司法書士である。
ユニフォームの魔力と現実
あの頃は、野球部のユニフォームを着ているだけで少し誇らしかった。土にまみれた姿も、なぜか清々しく見えた。でも今は、スーツに汗じみ、ネクタイがずれている姿のどこに魅力があるのか。ユニフォームの魔力は確かにあったが、それを維持するための努力は、あの時で終わってしまった。
応援してくれたあの子は今どこに
あの時、声援を送ってくれた子は、もうどこかで家庭を築いているのだろうか。ふと、登記簿の「所有者名」に見覚えのある名字を見つけて、まさかと思うこともある。そんな偶然が現実になることはない。でも、時々そんな妄想に逃げたくなる夜もある。