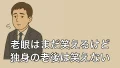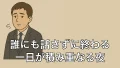朝の印鑑と心のスイッチ
朝、事務所のドアを開けると、あの静かな空気と、書類の山が待っている。毎日同じような始まりだが、そこでまず手に取るのが「印鑑」だ。実はこの瞬間が、私にとって一つのスイッチのようなものになっている。目覚めたばかりのぼんやりした心を、ぐっと仕事モードに切り替える役割を果たす。だけど、実はこのスイッチ、時々うまく入らない日もある。眠れなかった夜、うまくいかなかった手続き、妙に心に残る依頼者の言葉。そういうものが残っていると、印鑑を持つ手に一瞬の迷いが生まれるのだ。
ハンコを押す手に迷いは映らない
司法書士という仕事は、決断と責任の連続だ。書類に押す印鑑ひとつにしても、そこには重みがある。だが、依頼者から見れば、我々が押すハンコはただの「確認作業」に過ぎない。正直、そう見られるのは少し寂しいが、表に出すわけにはいかない。何度も読み直した書類も、見えないところで調整を重ねた案件も、最終的には「ハンコ一発」で片付けられるのだから、やるせないこともある。でもそれがプロだ。迷いを見せずに押す。それが役割。だけどな、心の中では何度も何度も「これでいいのか」と問うている自分がいる。
迷いは机の引き出しにしまうもの
迷いが生まれるのは当然のことだと思っている。特に相続の登記や遺言の相談など、依頼者の感情が絡む場面では、正解なんて一つじゃない。それでも最終的には手続きを進めなければならない。そういうとき私は、心の迷いを一旦「机の引き出し」にしまうような感覚になる。しまって、鍵をかけて、今日の業務に集中する。誰にも見せず、誰にも言わず。ただ、夜になって誰もいない事務所で、その引き出しをそっと開けて、ため息をつくこともある。消化できていない迷いが、じっとそこに残っていることに気づく。
それでも時々、あふれ出してしまう
どんなに感情を押し殺しても、時々どうしようもなくなる日がある。特に、連日忙しさが続いた週の金曜なんかは危ない。ふとした瞬間に、依頼者の何気ない言葉が胸に突き刺さって、溜めていたものが一気にあふれ出す。そんな日は、誰もいないトイレの個室でこっそり涙をこぼしたり、車の中で「くそっ」と独り言を言ったりして発散している。誰にも見られないように、プロの顔を守るために。迷いはつぶしこんだはずなのに、まるで地中から湧き出す地下水のように、じわじわと心を濡らしてくる。
ひとつひとつの決裁に込められた感情
決裁って、単に印鑑を押して「了承しました」ってだけじゃない。そこには、自分の価値観や、依頼者への信頼、業務上の危機感や責任感が入り混じっている。そうやって押された印は、見た目以上に「重い」。でもその重さを誰にも理解されないまま流れていく毎日が、時に虚しくも感じる。私の中では、1つの決裁に3回は迷いがある。けれど、それは誰にも言えないし、言ったところで「考えすぎじゃないですか」と言われるのがオチなのだ。
つぶしこむとは割り切りの別名
迷いをつぶしこむことに慣れてくると、自分の感情もだんだん鈍くなってくる。よく言えば「割り切りができるようになった」、悪く言えば「考えるのをやめた」状態。これはきっと、どの士業にもある共通の感覚じゃないだろうか。割り切ることで仕事は早くなるし、精神的なダメージも減る。でも、その分「心が痩せていく」感じがしてならない。かつては依頼者の一言ひとことに反応していたのに、最近じゃ「またこのパターンか」と処理してしまう自分がいる。それが果たして正解なのか、自信はない。
感情をしまっているだけで消えてはいない
割り切ったように見えても、感情というのは勝手に生きている。しまっても、いつの間にか顔を出してくる。ある日のこと、長年放置されていた相続手続きを手伝った高齢の女性が「これでやっと主人を送れます」と涙ぐんだ。そのとき、私の胸の中にずっと押し込めていた何かが、ぷつりと緩んだ気がした。やっぱり、自分の中に感情は残っているんだと。それをなかったことにして押し込めていたから、余計に苦しかったのだと気づいた瞬間だった。
ある日突然あふれる日が来る
押し込めた感情は、思わぬときにあふれる。それは、ふとした依頼者の言葉だったり、あるいはテレビのドキュメンタリーだったり、酒を飲みすぎた夜だったりする。私の場合は、ある葬儀の帰り道だった。お世話になった依頼者の死。その人と交わした何気ない会話が、車の中でふいに蘇り、堪えきれず声を上げて泣いた。つぶしこんでいたはずのものが、一気に押し寄せてきた。あれから私は、感情を完全には押し殺さないことにした。せめて、自分だけの場所では吐き出していいと、そう思っている。
事務員の前ではいつも平静を装っている
彼女は若いが、しっかり者で本当に助けられている。ただ、私の内面まではきっと見抜いていないと思う。見せないようにしているから。当たり前だ、事務所の空気を不安定にしたくないし、彼女に余計な心配をかけたくない。でも、平静を装うというのも結構しんどい作業で、ふと気を抜くと「声のトーン」で気づかれる。あの気まずい沈黙が苦手だ。心を見せるべきか、見せないべきか。正解なんて分からない。ただ、今日も無難にやり過ごすしかないのだ。
優しさと弱音は同居しないといけないのか
私のようなタイプは、たぶん「優しいけど弱い」と思われている。それでもいいと思っていた。でも最近、弱さを見せると「頼りない」と言われる場面もあって、正直ぐらついた。司法書士は「決める人」だからこそ、ブレちゃいけないのは分かっている。でも、強く見せようとするほど、内側での苦しさが増す。優しさと弱音、どちらかしか見せられないのだとしたら、それは不健全だと思う。でも、そういう不健全さで今日もなんとかバランスを取っている。
愚痴を言うことで自分をつぶしていないか
この仕事、愚痴の一つも言いたくなる。役所の対応、理不尽な依頼者、思うように進まない手続き。愚痴って、ある種のガス抜きだとは思っている。でも、言いすぎると「自分を自分でつぶしてる」気にもなるのだ。かつては信念を持って取り組んでいた案件も、愚痴ばかりこぼしていたら、どこかで「どうでもよくなる」感覚に陥ってしまう。それが一番怖い。だから、愚痴る場所とタイミングは慎重に選ぶようになった。
頼られてる感だけが支えになっている
結局のところ、今の私を支えているのは「頼られている」という実感だけかもしれない。依頼者からの「先生にお願いしてよかった」という一言、事務員の「今日もお疲れさまです」の声。それらがなければ、正直続けられていない気がする。独身で、モテなくて、仕事ばかりで、ふとした瞬間に「何やってるんだろ」と思う。でも、それでも「誰かの役に立っている」と思えることが、明日も印鑑を押す理由になる。つぶしこんでも、ゼロにはならない。残った想いが、かろうじて支えになる。