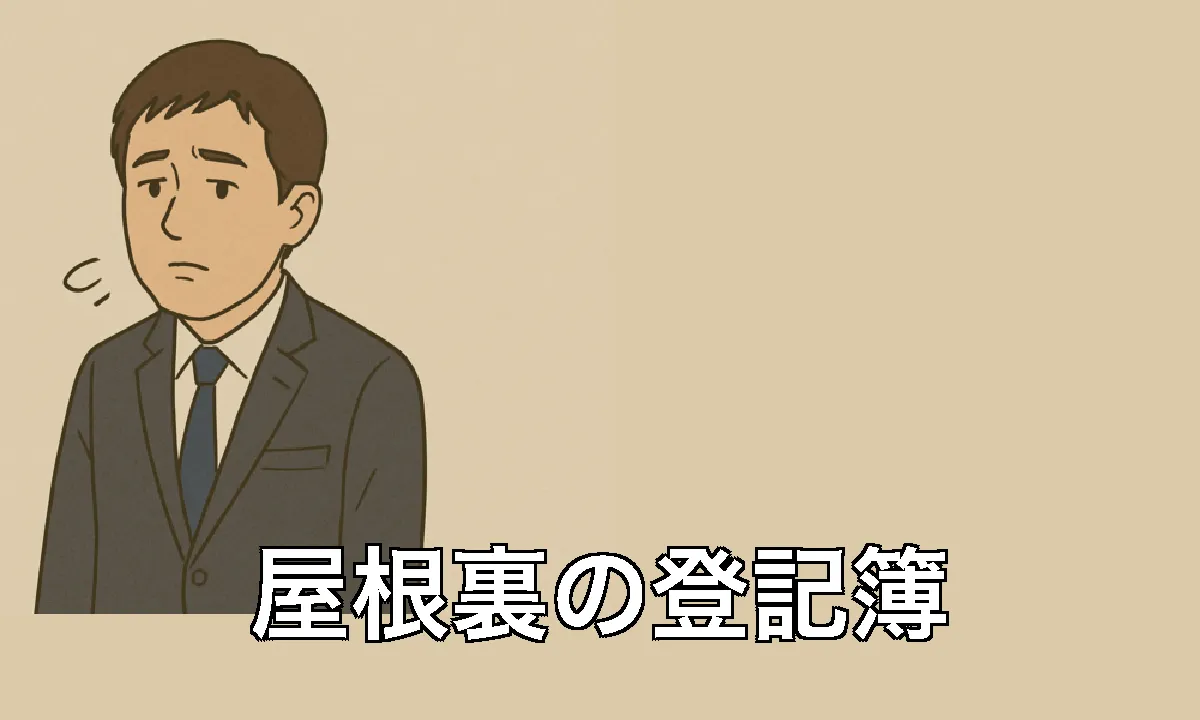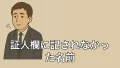はじまりは雨漏りから
朝から雨が降っていた。鬱陶しい季節の到来に、私はいつものようにぼやいていた。そんなとき、一本の電話が事務所にかかってきた。 「中古物件の購入に関して登記の相談がしたい」と、少し緊張気味の若い声だった。 どうせまた、わかってない人が『名義変えればいいんですよね』とか言ってくるんだろう、と思いながら、私はアポを取った。
ボロ家の購入相談
依頼人は30代半ばの男性で、格安の一軒家を見つけたらしい。「雨漏りはあるけど、自分で直せるから」と前向きだ。 ただ、彼が持ってきた売買契約書の写しと登記簿謄本に、なんとも言えぬ違和感があった。 土地の名義と建物の名義が違っているのだ。しかも建物のほうは、10年前に死亡した人物のままだった。
サトウさんの冷たいツッコミ
「シンドウさん、これはさすがに怪しすぎますよ。土地の上に“幽霊屋敷”が建ってるってことになります」 私がコーヒーをこぼしそうになった瞬間、サトウさんは淡々と付け加えた。 「調べないんですか? 暇なんでしょ、最近」と、塩対応にしては殺傷力が高すぎる。
登記簿の上にある謎
死んだ人の名義のままの建物。相続もされていなければ、滅失登記もされていない。 「売買契約書は誰が作ったんだ?」そう呟きながら、私は昔の登記情報を取り寄せた。 どうやらこの建物、20年前に一度だけ修繕履歴があり、それ以来手つかずのようだった。
名義人は確かに存在したはず
登記名義人の名前は「村岡重次」。昭和の雰囲気が漂う名前だ。 戸籍をたどってみると、彼は平成27年に死亡していた。だが、相続登記は放置されたままだった。 不動産屋は「元の持ち主の親族から直接買ったんですよ」と言っていたが、何かおかしい。
土地と建物が別人名義の理由
「売買できるのは名義人か、ちゃんとした相続人だけだ」と、私はひとりごちた。 しかし、土地の名義はすでに新しい人物に移っていた。数年前に所有権移転がされていたのだ。 土地は正規、建物は幽霊――この組み合わせ、どう考えても何か隠している。
不動産屋の違和感
例の不動産屋を訪ねてみた。担当者はやたら饒舌で、逆に胡散臭さが漂う。 「まあ、上モノはおまけみたいなもんですよ」などと、ぬけぬけと言う始末だ。 やれやれ、、、また妙な事件に足を突っ込んでしまったらしい。
話を濁す営業マン
営業マンは「法的に問題ない」と連呼するが、どこか目が泳いでいた。 「上物付き」と繰り返す様子は、まるで“上の空”で喋っているようだった。 私は、サザエさんの波平のようにため息をつきながら、その場を後にした。
「上物付き」の本当の意味
その夜、私は「上物」という言葉を何度もメモ帳に書き殴った。 そして、ふと思い出した。「あの家、屋根裏がやけに広かったな」と。 通常の平屋の構造にしては不自然だったのだ。そこに何かがある。いや、何かが“いた”のかもしれない。
屋根裏に忍び寄る過去
私は現地に赴き、依頼人と共に屋根裏に入る許可を得た。懐中電灯で照らすと、古い段ボールが積まれていた。 そしてその奥に、一枚の茶封筒が隠されていた。中には手書きの契約書の写し。 日付は平成10年。署名は「村岡重次」そして「斎藤千鶴」とあった。
こっそり入手した古い間取り図
法務局にある建築確認資料と間取り図を照合すると、現況と少し違っていた。 増築された形跡がある。だが、建築許可は出ていない。つまり、誰かが勝手に住んでいた可能性がある。 幽霊名義ではなく、幽霊住人。オカルトではなく、トリックだ。
屋根裏にもう一つの空間
依頼人とともに段ボールを動かすと、そこに小さな隠し扉があった。 中はまるで漫画『キャッツアイ』の隠れ家のようだった。埃にまみれた机、古い新聞、そして―― 壊れた判子が一つ、置かれていた。
発見された古い契約書
茶封筒に入っていた契約書の内容は、建物を他人に譲るというものだった。だが登記はされていない。 つまり、書類上の売却だけが行われ、そのまま放置されていたのだ。 理由は簡単――印鑑証明が取れなかった。つまり、不正だったのだ。
誰がいつ隠したのか
私はふと、印影を見比べた。どうやら故人のものに似せた偽造のようだった。 問題は、それを誰がやったのか、そしてそれが誰に渡っていたのか。 この事件、単なる相続放置の話ではなかった。
筆跡と印影の矛盾
筆跡鑑定までは行かなかったが、明らかに名前の書き方が違っていた。 くせ字の一画が異なっている。サトウさんが指摘した。「この“村”の書き方、他の書類と違う」 やっぱり、ただ者じゃないな、彼女は。
登記ミスか偽装か
不動産屋の手回しの早さと、土地だけが正規に移転している点。私はある仮説を立てた。 土地だけを合法に、建物はグレーなまま処理しようとしたのではないか。 その方が税金も安いし、相手にバレにくい。
「やれやれ、、、」とため息混じりの調査
あちこちに電話して、資料を洗って、ひたすら確認作業の繰り返し。 書類を束ねながら、私は何度も独り言を漏らしていた。「やれやれ、、、」 でも、少しずつパズルのピースは埋まっていった。
元持ち主の死亡と登記のズレ
最終的にわかったのは、土地だけを正式に相続して売却した人物が、 建物の登記を更新しないことで、ある意味“名義上の亡霊”を意図的に残したという事実だった。 書類の不備を逆手に取った、ずる賢いやり口だった。
サトウさんの推理がさえる
「つまり、これは“使える幽霊”をわざと残した事件ですね」 いつもながらに毒舌だが、真実を射抜いている。 私はぐうの音も出ず、苦笑するしかなかった。
鍵は火災保険の記録
調査の過程で、火災保険の更新記録にたどり着いた。 そこには建物の使用者として、契約者とは別の名前が記されていた。 その人物こそ、亡くなった村岡氏の甥だった。
郵便受けに残された名前
現地の郵便受けには、すでに剥がれかけたテープに「斎藤」という名前が残っていた。 これは、あの契約書のもう一方の署名者と一致している。 つまり、この物件はずっと“裏の住人”に管理されていたのだ。
真犯人は誰だったのか
すべてを仕組んだのは、村岡氏の甥だった。相続登記をわざと放置し、 建物を実質的に他人に貸し続け、土地だけを売却して利益を得ていた。 二重契約、二重構造――登記制度のスキマを突いた巧妙な手口だった。
屋根裏を使った二重契約の罠
建物内に残された書類と、郵便記録、保険契約、それらが示すのは明らかな“二重の世界”だった。 屋根裏は、証拠を隠すための“天井裏の金庫”として機能していた。 登記が追いつかない世界は、まさに“怪盗キッド”のようにすり抜けていた。
土地名義と建物名義のトリック
このトリックの恐ろしさは、合法と違法が紙一重で隣り合っている点にある。 登記制度は万能ではない。だが、それに甘える者には制裁が必要だ。 私は、関係書類一式を持って、法務局に報告書を提出した。
司法書士シンドウの一手
この事件で学んだことは多い。登記が“事実”と一致しているとは限らない。 私は依頼人に、今後の手続きの詳細と、契約の修正案を丁寧に説明した。 「難しいですね…」と苦笑する彼に、私は疲れた笑みを返した。
登記の力で嘘を暴く
たかが書類、されど書類。 真実は紙の中にある。それを読めるかどうかは、我々司法書士にかかっている。 今回は、少しだけ「やってよかったな」と思えた。
「正しい名義」に戻すということ
何が正しいかは、誰かが決めることじゃない。 でもせめて、記録だけは正しくあってほしい。私はそう願う。 だからこそ、今日もまた、書類の山と格闘している。
そして、静かな雨音だけが残った
事務所に戻ると、まだ雨が降っていた。天井からは、かすかに雨音が聞こえている。 私はコーヒーをすすりながら、今日の出来事を思い返していた。 この世で一番怖いのは、登記簿の「上」にある真実かもしれない。
あの屋根裏には誰もいない
後日、依頼人から連絡があり「屋根裏の荷物はすべて処分された」と報告があった。 その声は、どこか安堵しているようだった。 幽霊は、もういない。いるとしたら、過去の書類の中だけだ。
それでも書類は語る
どんなに古びた紙でも、そこには人の欲と怠惰が刻まれている。 そして、それを読み解くのが、私の仕事だ。 やれやれ、、、また明日も誰かが「登記って簡単ですよね?」って言ってくるんだろうな。