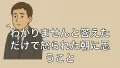笑いが遠ざかる日々に気づいたとき
気づけば、最後に心から笑ったのがいつだったか思い出せない。そんな自分にふと気づく瞬間がある。仕事に追われ、事務所でパソコンに向かう日々。登記の不備がないか確認することに神経をすり減らし、終業後にはぐったりして家に帰る。その繰り返しのなかで、自然と笑うという感情がどこかに置き去りにされていたように思う。誰かと何気ないことで笑い合う、そんなささやかな時間が、いつのまにか手の届かないものになっていた。
事務所の沈黙が心に重くのしかかる
一人で事務所を運営していると、音のない時間が長い。電話が鳴るか、事務員と業務的な会話をする以外、基本的には無音だ。BGMを流すこともあるが、それが逆に孤独を際立たせることもある。若いころは「集中できる静けさ」と思っていたけれど、今は違う。誰かとくだらない話でもして笑いたい。そんな気持ちがふいに襲ってくる。ただそれを口に出すと、弱さを見せるようで情けなくなってしまう。
話し相手がいないという現実
昔は野球部の仲間と、毎日のようにバカ話をしていた。練習帰りにラーメン屋に寄って、くだらない冗談でゲラゲラ笑った。けれど、今は違う。友人たちは家庭を持ち、子どもの話や家のローンの話ばかり。自分にはそのどれもない。仕事の話も、専門用語が多すぎて気軽には話せない。話す相手がいないという現実は、想像以上に心を蝕んでいく。
事務員の気遣いがかえってつらいときもある
うちの事務員はとても優秀で、空気を読んで無駄なことは言わない。でもその「気遣い」がときに寂しさを助長する。たとえば沈黙が続いたとき、彼女なりに気を使って話題を振ってくれるのだけど、それが逆に「気を使われてる」と感じてしまって、心苦しくなるのだ。自分が話しづらい雰囲気を作っているのだろうかと、また自己嫌悪に陥る。
日常のなかで笑いを忘れていく感覚
テレビを見て笑うことも減った。お笑い番組も、芸人たちのテンションが高すぎてついていけない。ニュースは暗い話題ばかりで、テレビをつけた後に無言でリモコンを置くことも多い。心が笑う準備をしていないのかもしれない。そんなとき、昔読んだ漫画を読み返したら、ふと口角が上がった。その瞬間、「あ、自分にもまだ笑える余地があるんだ」と気づいて、少しだけ安心した。
テレビをつけても心は動かない
テレビの中の世界は、まるで別の惑星の話のようだ。どんなに盛り上がっていても、自分の感情とはリンクしない。この感覚、まるで誰かがずっと自分の声をミュートにしてるような気分だ。笑うって、そんなに簡単だったっけ?と考え込んでしまう夜もある。
昔の自分とのギャップにふと落ち込む
高校時代の自分の写真を見返すと、驚くほど笑っていた。歯を見せて、頬をくしゃくしゃにして笑っている。今は、証明写真ですら口角が少し上がるかどうか。あの頃の自分が今の自分を見たら、どんな顔をするんだろうか。そんなことを考えて、ひとり苦笑するしかない。
仕事の中に笑える余白はあるのか
司法書士という仕事は、感情を押し殺す場面が多い。冷静でいること、正確であることが何よりも求められる。そのなかで笑いという感情は、どこか「邪魔なもの」扱いされてしまいがちだ。でも、笑わないとやってられない場面だってある。人間なんだから。
登記ミスが笑えない日常
つい最近、申請書類の一部に入力ミスがあった。もちろん再申請で対応したが、心のなかでは「またか…」と頭を抱えた。笑って済ませられるようなことではないけれど、あまりにも連続すると、逆に笑いそうになる。けれど、その笑いは悲鳴に近い。机に突っ伏して「誰か代わってくれ」と思う瞬間さえある。
笑って済ませるには責任が重すぎる
たった一つの記載ミスが、依頼者の不信を招く。この業界では、「うっかり」は通用しない。だからこそ、神経を張り詰め続ける。その結果、ちょっとした失敗が起きたときに、自分を許す余白がなくなってしまう。笑いなんて、出てくる余地がないのだ。
結局、自分の首を絞めるだけ
誰かに責められる前に、自分で自分を責める癖がついてしまっている。「もっとちゃんとやれただろ」と。だから笑うことができない。できるわけがない。そんな自分を、また自分で叱るという負のスパイラルに陥るのだ。
笑顔を作って対応する矛盾
依頼者の前では、できるだけ穏やかな表情を心がけている。でも内心は「急ぎの依頼がまた来た…」とか「なんでこんな説明を求められるんだ…」とモヤモヤしている。そういう時ほど、笑顔が仮面に思えてくる。人としての自然な笑いじゃない、職業としての笑顔。
笑顔の裏にある不安と焦燥
「先生って、いつも穏やかですよね」なんて言われたとき、内心では苦笑いしていた。穏やかというより、諦めの表情だったのかもしれない。心の中では、書類と締切に追われて常に小走りしている。笑顔なんて、演技以外の何物でもない。
「先生」なんて呼ばれたくない瞬間
「先生」と呼ばれるたびに、どこかで違和感がある。自分がそんなに立派な人間だとは思えないからだ。間違いもするし、朝はギリギリまで寝てるし、夜はレトルトカレーで済ます。そんな自分に「先生」という肩書きが、時に重たく感じてしまう。
それでも笑いたいと思える理由
何度落ち込んでも、それでもどこかで「笑いたい」と思うのは、人間の本能かもしれない。たとえ小さなきっかけでも、ふと笑える瞬間があるだけで、救われる気がする。自分自身のためにも、誰かのためにも、そういう笑いを大切にしていきたい。
この仕事を辞めない自分のために
独立してからずっと、いろんなことがあった。でも、どれも辞めるほどの理由にはならなかった。たぶん、自分のなかに「この仕事を通じて何か役に立ちたい」という想いがあるから。だからこそ、笑える日もあっていいはずだと信じたい。
たとえ一人でも続けてきた意味
「一人でよくやってますね」と言われることがある。でも別に特別なことをしているつもりはない。ただ、ここまでやってきただけだ。でもそれは、それなりに意味のあることだったと信じたい。そして、それを認めてやれるのは自分自身しかいない。
誰かに必要とされるという証明
「あなたにお願いしてよかった」と言われたとき、胸がいっぱいになる。たとえ笑っていなくても、心の奥では確実に温かい何かが広がる。その感覚がある限り、自分はまだ大丈夫だと思える。
笑ってくれる人が一人でもいれば
事務所に戻ると、事務員が「おつかれさまでした」と微笑んでくれる。それだけで少し報われる。誰かが笑ってくれるなら、自分ももう少し頑張れる気がする。笑いって、結局は人とのつながりのなかにしか存在しないのかもしれない。
事務員の「おつかれさま」に救われる夜
仕事がうまくいかなくて、へこんで帰ってきた日。事務員が何気なく「おつかれさまでした」と言ったその一言が、なぜか胸に沁みた。そのとき、自分も笑って「おつかれ」と返せた。それだけで少しだけ、世界がやさしくなった気がした。
匿名の誰かの共感が支えになる
こうして文章を書くのも、誰かに共感してもらえたらという淡い願いがあるからだ。面識もない誰かが、「わかる」と思ってくれたら、それだけで救われる。人って、そんなささいなことでまた笑えるようになるのかもしれない。