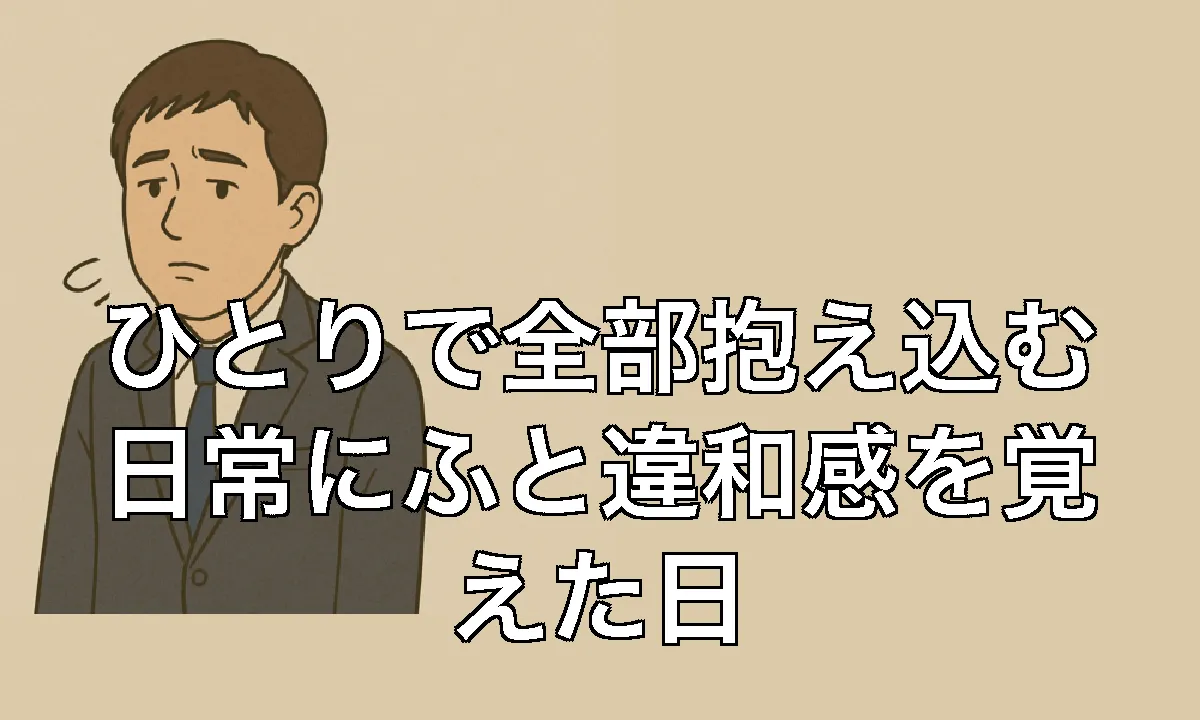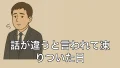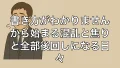気づけば全部ひとりでやっていた日々
朝、事務所の鍵を開け、掃除をして、電話対応をし、依頼者対応、書類作成、法務局への提出まで──全部ひとり。事務員さんはいる。ただ、彼女には「これは自分でやったほうが早い」と思ってしまう仕事が多すぎて、気づけば任せること自体が減っていた。何もかもがひとりで完結する日々。それに違和感を覚えるようになったのは、ある日、昼食をコンビニで買った帰り道だった。ふと立ち止まって、「これって、ひとりでやる必要あるのか?」とつぶやいていた。
電話も来客も自分ひとりで回している現実
電話が鳴る。対応中にまた電話が鳴る。ピンポンと来客も来る。そんなとき、事務員さんがいても、自分が対応してしまうのが癖になっている。お願いすればよかったと後から思うのだが、瞬間的に動いてしまうのは、元野球部の「打球を取れるやつが取れ」という反射的な思考の名残なのかもしれない。だけど、気づけば自分だけが慌ただしくしていて、事務所全体が疲弊しているのは自分の顔だけということが多い。
「他の事務所ってどうしてるんだろう?」という素朴な疑問
たまに他の司法書士さんと話す機会があると、「そんなのは事務さんに任せてるよ」と軽く言われることがある。正直、羨ましい。いや、羨ましいを通り越して「え、任せていいんだ?」とすら思ってしまう。自分の中では、依頼者対応は全部自分でやるもの、登記申請もチェックも最後まで見届けるもの、という思い込みが根深くあった。でも、これって“正しさ”ではなく、ただの“思い込み”だったのかもしれない。
事務員さんにも頼れない空気を作ってしまう自分
結局のところ、自分が「これは自分でやるから」と言いすぎたせいで、事務員さんが「これは聞いちゃいけないんだな」と遠慮してしまったのだろう。本人には悪いことをしたなと思う。頼っていい、という空気を作らなかった自分の責任だ。まるでキャッチボールを一人でやってるような感じ。投げても返ってこない、というのは自分が誰にもボールを渡してないからに他ならない。
効率はいいけど何かが足りない感覚
仕事は早い。おそらく、ひとりで全部やることで、ミスも少なく、スピード感もある。でも、ある種の「満足感」がどんどん薄れてきていた。達成感ではなく、充実感の欠如。仕事の山を越えても、そこには誰かと喜び合う瞬間がない。自分ひとりが静かにパソコンの前で「よし、終わった」とつぶやくだけ。それが妙に空しいのだ。
人に頼まないことが美徳だと信じていたけれど
昔から、人に頼るのが下手だった。特に司法書士という仕事をしていると、責任は全部自分が背負うという意識が強くなる。たとえミスが事務員であっても、最終的に責任を問われるのは自分だ。だから、人に任せるくらいなら、自分でやったほうがいいと思ってしまう。でも、それは本当に「美徳」なのだろうか?それは自分の不安からくる過剰なコントロールでしかなかったのかもしれない。
「できちゃう」からこそ誰にも頼らない癖がついた
司法書士という仕事は、独立してしまえば、正直ひとりで完結することが多い。しかも、自分はある程度こなせてしまうタイプだ。だからこそ、誰にも頼らないでいることが“当たり前”になってしまった。でも、それが当たり前になってしまうと、人との関わりがどんどん希薄になる。自分だけがやって、自分だけが疲れて、自分だけが「なんか違う」と感じてしまう。
いつの間にか自分だけが消耗していく日常
最初は「これがプロだ」と思っていた。でも、それがただの“独り相撲”だと気づくまでに10年近くかかった。人に頼らず、相談もせず、淡々とやっていく日々。まるで砂を噛むような感覚が続いて、気づけば笑うことも減っていた。事務員さんとの会話も減り、依頼者とも淡々と接している。機械的な日々に、自分だけがどんどん摩耗していたのだ。
昔の野球部ではこんなことなかったのに
高校時代の野球部では、チームワークが命だった。誰かがミスしても、みんなでカバーし合って、声を掛け合い、試合に勝つ喜びも、負ける悔しさも共有していた。それが今ではどうだろう。すべて自分で処理して、良い結果も悪い結果もひとりで抱えている。あの頃のチームのあたたかさが、いまの事務所にはない。
仲間と声をかけあって動くのが当たり前だった頃
グラウンドでは、「ナイスキャッチ」「いけるいける!」「任せろ!」そんな声が飛び交っていた。声があるからミスも恐れずに済んだし、誰かが見ていてくれるから頑張れた。今はどうだろう。書類をミスっても、誰も気づかない。自分で気づいて、自分で直して、それで終わる。誰かとつながってる感覚が、どこかへ消えてしまった。
掛け声ひとつで連携できたあの頃が懐かしい
「オーライ!」の一声で誰が捕るかが決まり、「ありがとう!」の一言で関係が深まった。そんな当たり前のやりとりが、今の事務所ではほとんどない。業種が違うとはいえ、ひとことの声かけがあるだけで、どれだけ安心できるか。掛け声ひとつでつながることの大切さを、改めて思い出してしまう。
いまや声をかける相手すらいないという現実
事務所には事務員さんがいるけど、雑談をすることはほとんどない。必要なことだけを伝えて、あとは黙々と仕事をする。声をかける相手がいないというより、声をかける関係性を築けなかった自分がいる。そうやって自分で自分を孤立させていることに、最近ようやく気づいた。
なぜ誰にも話しかけられなくなったのか
もしかしたら、周囲は遠慮しているのかもしれない。いや、自分がそういう雰囲気を作ってしまっているのか。仕事に追われているように見えるのだろうか。それとも、ただの近寄りがたいオーラをまとっているのか。どちらにしても、話しかけられないというのは、少しさみしい。
「一人で静かにやってる人」というイメージが壁になる
周囲から見た自分は、おそらく「一人で黙々と仕事してる人」だ。静かで、怒らないけど、距離も近づかない。そういう印象があるから、雑談も生まれないし、気軽に話しかけられることもない。無意識のうちに壁を作っていたことに、最近ようやく気づいた。
優しさが誤解されて近寄りがたい存在になっていた
怒らないし、理不尽なことも言わない。でも、何を考えているかわからない。たぶんそれが“怖い”のだろう。優しさは時に距離を生む。むしろ、ちょっと抜けたところがあったり、失敗を見せることで、人は安心するのかもしれない。完璧すぎると、人は近づきづらくなる。自分にそんなつもりがなくても、そう映ってしまっていたのかもしれない。
モテないのはもはや性格のせいじゃない気がしてきた
モテない歴45年。長い付き合いなので、自分でも慣れてしまった。ただ、最近ふと思うのは、性格のせいじゃないんじゃないかということ。むしろ、“関わりたくない空気”を自分で発してしまっているせいかもしれない。壁をつくって、誰にも頼らず、感情も出さない。そりゃ近寄ってこないよな、と鏡の前でひとりごちた。