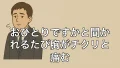人混みにいるのに寂しさが消えない日がある
法務局の帰り道、駅前の商店街を歩くと人であふれかえっていた。夏祭りだったのか、浴衣姿の子どもたちがはしゃぎ、屋台の香ばしい匂いが漂ってきた。楽しげな声、笑い声。それらに囲まれているはずなのに、ふと立ち止まってしまった。まるで透明人間になったような感覚。人の多さに比例して、なぜか胸の奥がひんやりしてくる。こんなに人がいるのに、僕は誰にも見られていない。誰ともつながっていない。その思いが、一層の孤独を呼び起こすのだった。
周囲の笑顔が刺さる瞬間
人の笑顔って、時に武器のように感じることがある。特に自分の気分が沈んでいるとき、周囲の楽しそうな姿が眩しすぎて目を背けたくなる。事務員の彼女が楽しそうにスマホを眺めていた日、「誰と話してるの?」と聞けずにいた。もし恋人でもいたら、仕事終わりに誰かと笑い合えるのだろうかと、自分の生活を省みてしまった。笑顔は本来、温かくて優しいもののはずなのに、なぜか「持っていない自分」を突きつけられる気がして、胸の奥がキリキリと痛む。
にぎやかさの中で置いてけぼりになる感覚
地元の夏の花火大会。人の波に揉まれながら歩いているとき、何度も思った。「俺、何やってるんだろうな」。誰とも話さず、一人で空を見上げる時間がこんなにも長いとは思わなかった。周囲は恋人同士や家族連れ、友人グループ。手をつなぎ、笑い合い、時には肩を寄せていた。それに比べて、手に持った缶ビールだけが自分を支えていた。こういうイベントは、誰かと来るものだったと気づいたときには、もう遅かったのかもしれない。
つながりを演じる疲れと本音のギャップ
SNSで「楽しい時間でした」と投稿する人たちを見ながら、自分もどこかで「寂しくない」と装っていた。仕事柄、人前ではきちんとした態度をとることが求められるけれど、内心では「俺だって誰かとつながりたい」と思っている。そんな思いすら恥ずかしくて、誰にも言えない。電話一本かける相手がいるだけで、救われる夜もある。でも、そんな相手すら思い浮かばない日は、布団の中で目を閉じるしかない。演じることに慣れすぎた自分が、時々怖くなる。
声は聞こえるけれど届かないという不安
司法書士という仕事柄、声を発する場面は多い。依頼人の話を聞き、登記官とやり取りをし、事務員と業務を分担する。でも、それはあくまで“仕事の声”であって、“心の声”ではない。プライベートでの会話はどんどん減っていき、電話が鳴るのも宅配の再配達ばかり。誰かに届くはずの言葉が、自分の中で行き場をなくしてしまっている。まるで、自分の存在そのものが、誰かに届かなくなっているかのような不安に襲われる。
誰とも話していないのに疲弊する理由
休日、誰にも会わず誰とも話さず、コンビニとスーパーだけで過ごした日。なぜかものすごく疲れた。心の中でずっと誰かと会話していた気がする。たとえば「もし誰かとランチに行けたら」「今この話を聞いてくれる人がいたら」といった妄想のようなもの。誰とも話していないのに、頭の中ではずっと会話が繰り広げられていて、逆に消耗してしまう。これが“孤独疲れ”というものなのかもしれないと、缶ビール片手にぼんやり思った。
雑踏の中で一人になる心のメカニズム
電車のホーム。人でごった返しているのに、話し相手は誰もいない。すれ違う人の視線も自分には向いてこない。都会に行ったときによく感じるあの感覚。つまり「自分がこの世界に存在していないみたいだ」という不安。人は群れの中で安心する生き物のはずなのに、見知らぬ人だらけの群れでは、逆に不安が増していく。誰かと関係性があってこその「群れ」なんだという当たり前のことを、雑踏の中で思い知らされた。
司法書士という仕事の性質が孤独を加速させる
司法書士の仕事は基本的に「一人作業」が多い。誰かとチームを組んで動くというよりは、個人で調査し、判断し、書類を整えて提出する。責任もすべて自分に降りかかってくる。仕事中は忙しくて孤独を感じないが、ふと手が止まった瞬間に、一気にそれが押し寄せる。相談者が帰ったあとの静かな事務所で、自分だけがポツンと残っている感覚は、思っている以上に心にくる。
一人で判断を下す毎日の重み
登記申請一つ取っても、判断を誤れば依頼者に大きな迷惑がかかる。だからこそ、慎重に進める必要がある。でも、その「慎重」を誰かと共有できるわけではない。自分の判断に自信が持てないときも、相談できる相手がすぐにそばにいるわけではない。信頼されている分、孤独にもなる。信頼は嬉しいが、同時にプレッシャーでもある。頼られているからこそ、誰にも頼れない。そんな矛盾が、日々の中でじわじわと心を蝕んでいく。
相談を受ける側の孤独という裏側
相続や不動産の問題など、依頼者は人生の岐路でこちらに相談に来る。その話を丁寧に聞き、整理し、最適な提案をする。それが仕事だとわかっているけれど、時にその重さに押し潰されそうになる。相手は涙を流し、困っている。それを支えるこちらは、涙も見せず、表情も崩さず、冷静を装う。ふとした瞬間、「誰が自分の話を聞いてくれるんだろう」と思ってしまう。相談を受ける側にこそ、癒しが必要だと気づく瞬間だった。
頼られるのに誰にも頼れない現実
事務員が帰ったあと、急な電話対応やミスの修正に追われることがある。そういうときに限って、パソコンがフリーズしたり、プリンタが言うことを聞かなかったりする。誰にも頼れず、イライラしながら自分で解決する。誰にも文句を言えないから、心の中で叫ぶ。「もう勘弁してくれよ…」。頼られている分、自分の弱さを見せられない現実。それが、知らず知らずのうちに、自分を苦しめているのだと気づく夜がある。