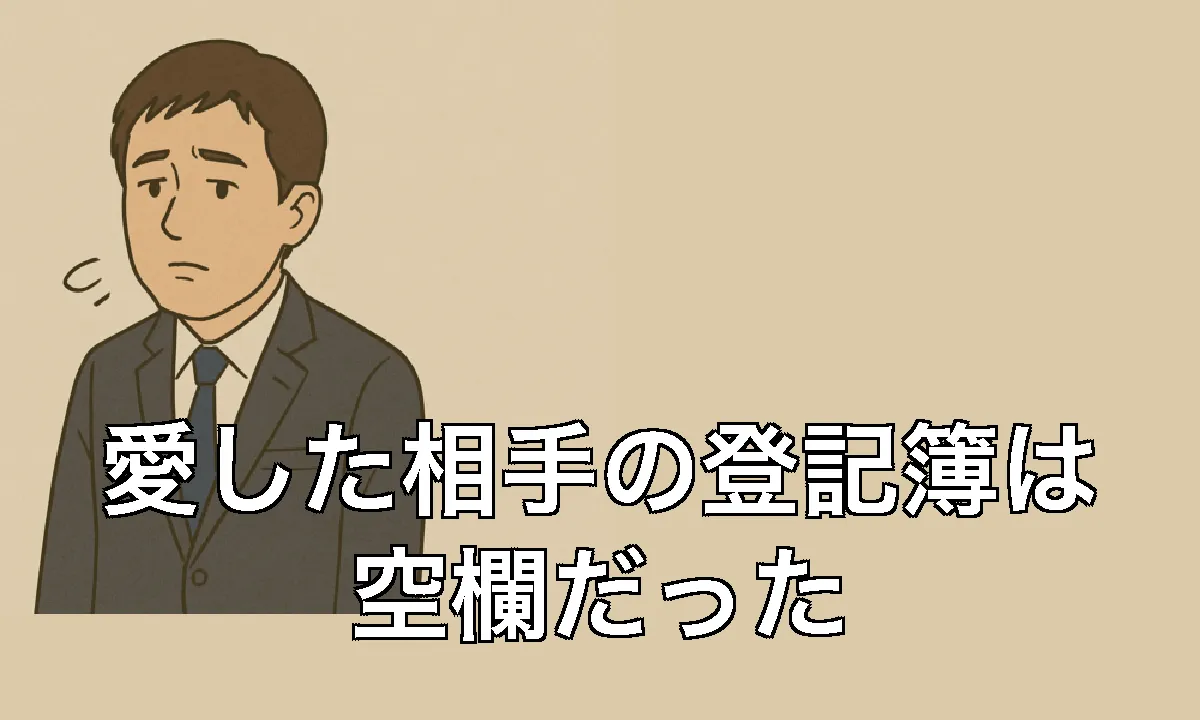第一章 不動産相談に現れた女
市役所帰りの女の影
その女が訪ねてきたのは午後4時過ぎ。雨が降る気配の空の下、黒いトレンチコートを羽織り、肩には市役所の封筒を下げていた。妙に落ち着いた声で「ちょっと登記の相談を」と言われ、ぼくは事務所のドアを開けた。
優しい声と怪しい依頼
「祖母名義の土地を、自分のものにしたいんです」──その一言で、司法書士としての警戒心が働いた。戸籍を辿るのか、それとも遺言書があるのか。質問を始めようとした瞬間、女がふと目を伏せて言った。「実は、その祖母とは連絡が取れなくて…」
第二章 運命の名前確認
登記簿にない所有者
出された住所から登記情報を取り寄せたが、女の話と一致しない。たしかに筆界の情報に類似性はあるが、所有者名義が違う。女が書いたメモの名前は、どこにも見当たらなかった。
なぜか空白の氏名欄
そして奇妙なことに、一部の書類では「所有者」欄が空欄だった。そんなことは通常あり得ない。登記官がミスをしたのか、それとも誰かが故意に削除したのか。僕の額にじわりと汗がにじんだ。
第三章 恋は盲目だった
かつての交際相手の話
顔を上げた彼女を見たとき、ふと既視感が走った。目の形、左の小さなホクロ…。ぼくが大学時代、淡い恋心を抱いた女性とそっくりだった。いや、もしかして本人か? 記憶の中の彼女はいつも斜め45度の角度から僕を見て笑っていた。
シンドウの失恋記録
ぼくの恋は、告白する間もなく終わった。彼女はいつも他の男に囲まれ、ぼくには「野球部の人」としか認識していなかった。それでも、駅のホームで偶然話した一瞬だけは、忘れられない思い出だった。まさか、ここで再会するとは…。
第四章 サトウさんの冷静な指摘
「これは詐欺に近いですね」
「シンドウ先生、これ、印鑑証明と日付が合いません」──サトウさんが冷静に指差した書類には、明らかな矛盾があった。印影のズレ、住所の違和感、そして提出日より未来の日付がある。僕がぼーっとしている隙に、彼女はすべて見抜いていた。
地番ミスか意図的か
単なる地番ミスにしては不自然すぎる。調査を進めると、その土地は別名義で売買契約が結ばれようとしていた。しかも売主として記されていたのは、件の彼女──いや、あの「元恋人」だった。
第五章 遺言書に仕掛けられた罠
形式は整っているが内容が空
提出された遺言書は公正証書で、一見完璧に見えた。しかし、財産の記載欄が「不動産一式」とだけ書かれている。明確な物件名や筆界がない。これは無効になる可能性が高い文言だった。
なぜか一致しない印鑑証明
印鑑証明は発行日が古く、既に失効していた。それに気づいたサトウさんは、すぐに法務局に照会をかけた。「こういう時は、登記よりもまず警察ですよね」と彼女はさらりとつぶやいた。
第六章 元恋人の二重生活
浮かび上がる偽名の履歴
調査の結果、彼女は複数の名義で過去に複数の不動産取引を行っていた。その中にはすでに詐欺と判断されたものもあり、現在は起訴保留中との記録があった。まさか、あの笑顔の裏にそんな一面があったとは…。
登記簿の履歴に現れた過去の住所
住所の一つには、僕がかつて住んでいたアパートの名もあった。偶然か、それとも……。ぞっとした。恋というのは本当に盲目で、時に人の判断を狂わせる。
第七章 やれやれ、、、またかよ
追い詰めたはずの相手が消えた
連絡を絶った彼女の所在は不明となった。携帯番号もSNSも削除済み。残されたのは、不自然な登記資料と偽名の記録のみ。「やれやれ、、、ほんと、またこのパターンか」とつぶやいた自分が情けなかった。
司法書士の出番はここから
しかし、登記と名義の世界には逃げ道がない。僕は関係先に通知を出し、関係各所に経緯を報告した。こういう地味な作業の積み重ねが、真実を掘り起こす。派手な探偵の活躍ではない。けれど、確実な一歩だった。
第八章 ラストページの逆転劇
鍵は別件の登記申請書
その週、別件の登記申請書の中に彼女の署名を見つけた。どうやら、彼女は別の司法書士事務所でも同様の手口を使っていたようだ。僕はその情報を元に、関係者を通じて警察に通報した。
名前のズレが語る本当の動機
新たな資料から、彼女が本当は相続放棄の手続きから逃れるため、架空名義で財産を取得しようとしていたことがわかった。つまり、「好きだった」はただの道具だったのだ。
第九章 未遂に終わった愛と犯罪
恋と嘘の代償
彼女はついに逮捕された。初犯ではなかったが、今回は証拠が明確だった。僕が感じたあの懐かしさも、すべて作られたものだったのかもしれない。そう思うと、虚しさだけが残った。
届けられなかった書類
最後に彼女が持っていた封筒には、ぼく宛の手紙が入っていた。封はされておらず、「ありがとう」とだけ書かれていた。それが何に対する「ありがとう」なのか、今となってはもうわからない。
最終章 空欄だったのは心か名前か
サトウさんの塩対応と紅茶
「だから言ったじゃないですか、信用しすぎですよ」──サトウさんがいつものように塩対応で紅茶を差し出してくる。僕は苦笑しながら一口飲んだ。少し渋かったけれど、なぜか安心した。
今日も登記は無事完了
結局、事件はひと段落し、依頼人には正しい手続きを案内した。どんな恋でも、どんな嘘でも、書類の前では真実しか残らない。司法書士とは、そういう仕事なのだ。