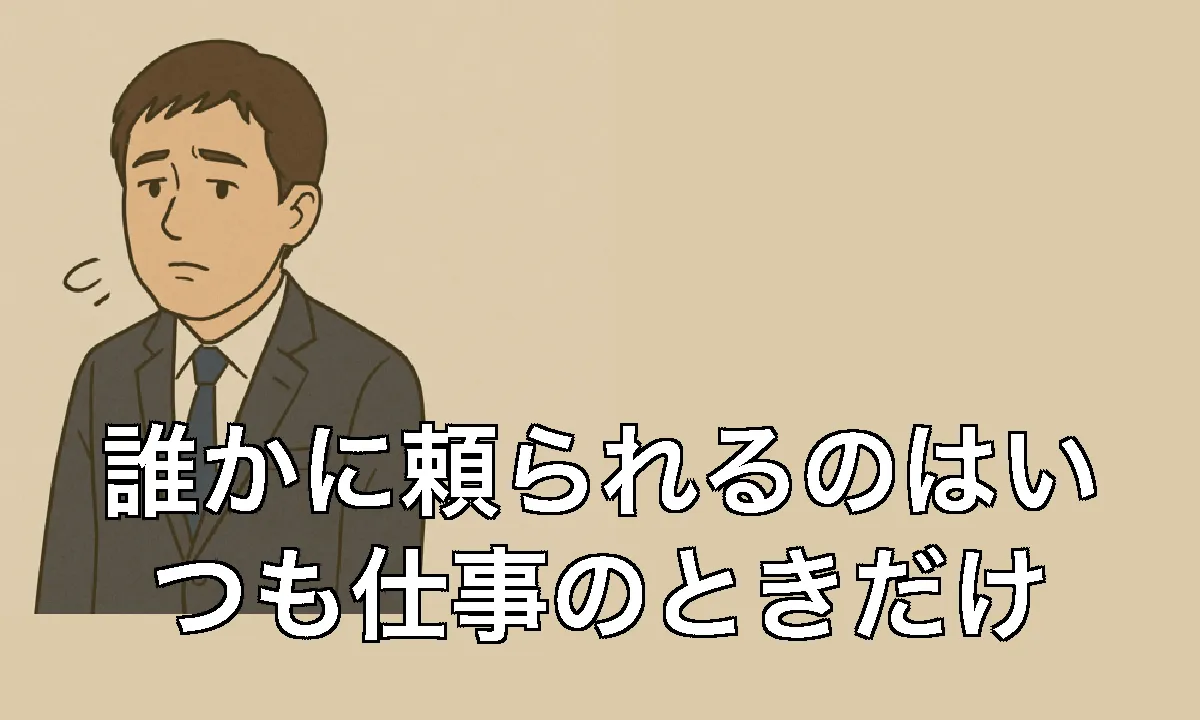肩書きが先に立つ人生に疲れてきた
司法書士として15年以上やってきた。相談されることにも、感謝されることにも慣れているはずなのに、心のどこかで「俺自身」を見てくれている人なんていないんじゃないか、と思うことがある。肩書きで呼ばれ、肩書きで頼られ、肩書きで必要とされている。そんな生活に、ふと虚しさを覚える瞬間がある。飲み会に出ても「ちょっと登記のことでさ」と仕事の話が始まり、プライベートの話にすらならない。俺の話は誰も興味ないのかと、酒が進むにつれて、余計なことまで考えてしまう。
司法書士としての役割ばかりが目立ってしまう
ある日、町内会の寄り合いに顔を出したときのこと。「お、司法書士さん!ちょっと教えて」と、またも登記の話を持ちかけられた。雑談のつもりで足を運んだのに、気づけば相談会になっていた。もう癖みたいなものだ。悪気はないのはわかってる。でも、肩書きを外した自分は誰にも見えてないんじゃないか。仕事では頼られる。でも、それ以外で頼られた記憶がない。肩を貸す相手は多いのに、心を寄せられる相手はいない。ふと、自分が便利屋になった気がした。
どこにいても「専門家」として見られる
この間、親戚の集まりで甥っ子の誕生日会に行った。子どもの話やゲームの話で盛り上がっていたが、親たちが俺のところへやってきて「相続の件でちょっと…」とヒソヒソ話。場の空気が一気に変わる。子どもたちの笑顔の隣で、俺だけが妙に真面目な顔になっていた。なんというか、俺は“親戚”ではなく“司法書士”として呼ばれているように思えて、少し寂しくなった。いつも役割でしか見られていないような感覚は、積もれば結構堪える。
雑談すら仕事の相談に変わっていく違和感
「最近どうですか?」という挨拶が、「最近の登記ってどうなってるんですか?」にすり替わる瞬間がある。悪気はない。むしろ相手は距離を縮めてるつもりかもしれない。でも、俺にとっては“俺の話”ではなく“仕事の話”だ。たとえば昔の同級生に会っても、「お前に相談したいことがあってさ」と切り出されると、懐かしさより先に警戒心が湧く。気楽な会話すら、どこかビジネスライクになってしまう。それが癖になり、気づけば“心を開ける雑談”がどこにもなくなっていた。
日常会話の中に居場所がない
誰かと話しているとき、ふと「俺、いま心から楽しめてるか?」と思うことがある。話題が盛り上がっていても、それが全て仕事に結びついていたり、情報収集の一環だったりすると、ただ“その場にいるだけ”の自分が空虚になる。昔はもっとくだらない話でゲラゲラ笑っていたのに、いつからこんなに“有益”な会話しかできなくなったんだろう。笑えるけど、笑えない。そんな会話が増えた。
頼られるのが嬉しいはずなのに
頼られるって、本来なら嬉しいことだ。間違いなく、誇らしいことだ。だけど、それが「仕事」ばかりだと、だんだん“俺じゃなくてもいいんじゃないか”って思えてくる。事務所の電話が鳴るたび、対応する事務員さんが「また先生宛てですよ」と言う。その言葉の後に、「こんなときだけ“先生”って便利ですね」と小さく笑われたとき、妙にグサッときた。笑い話のはずなのに、自分でも笑えなかった。
仕事の話をされない日は少ない
先週の日曜日、近くの喫茶店でモーニングを食べていたとき、隣の席に座った顔見知りの年配男性に声をかけられた。「司法書士さんですよね?実はちょっと相続のことで…」と、いつもの流れ。俺が誰かといるときですら遠慮がないのが、この職業の宿命なのか。プライベートが溶けていくような違和感が常にある。まるで制服を着たまま街を歩いているような感覚だ。
ただの“自分”としての価値が見えない
仕事のスキルや知識で評価されることはある。でも、じゃあ肩書きを取った“俺”には何が残るんだろう。誰かに頼られた記憶を辿っても、結局「登記」「相続」「会社設立」の文字ばかりが浮かぶ。元野球部だってことを知ってる人なんて、今じゃほとんどいない。昔はバッティングが得意だったのに、今は「打つ」のは書類の印鑑くらいだ。俺のことを、ただの“人間”として見てくれる人がほしい。それが思った以上に難しい。
独身という孤独と向き合う時間
この年齢になると、独身ってだけで少し浮く。周りは家庭を持っていて、子どもの話や住宅ローンの話が飛び交う。俺の話題はせいぜい「最近どんな登記があったか」くらいで、笑いも共感も生まれにくい。誰かに甘えたいわけじゃない。でも、誰かに「今日どうだった?」と聞いてもらえるだけで、気持ちは違う。そういう日常の小さな頼られ方を、ずっと羨ましく思ってる。
モテないことに慣れすぎてしまった
若い頃は多少の希望があった。街コンにも行ったし、紹介も受けた。けど、結局「先生って忙しそうですね」で終わってしまう。誰も“忙しさの奥”まで踏み込んでこない。モテないことに悩まなくなったら、今度は人との距離感そのものがわからなくなった。恋愛とか以前に、「この人に話しかけていいのか」すら迷うようになってしまった。孤独に慣れたというより、孤独に適応してしまったのかもしれない。
頼りたくても頼れる人がいない現実
風邪を引いたとき、たった一日寝込んだだけで、事務所の電話が溜まった。もちろん誰も文句は言わないけど、「俺が倒れたら全部止まるんだ」と改めて実感した。頼られることの重さと、頼れないことの孤独が、同時にのしかかってくる。誰かに「ちょっとこれお願いしていい?」って言いたくても、その“誰か”がいない。そんな状態が、もう何年も続いている。
元野球部の自分が支えていたのは誰か
高校時代、野球部でキャッチャーをしていた俺は、ピッチャーの心理を読むのが得意だった。試合中、ピンチのときに声をかける役目だった。「お前ならいける」って言うと、仲間が頷いてくれた。今思えば、あの頃は“信頼のやりとり”が日常だった。今はどうだろう。信頼されているけど、誰にも「お前なら大丈夫」って言われることはない。支えるだけで、支えられることがない。それがこんなにしんどいとは思わなかった。
声をかけ合って支え合うのが当たり前だった
グラウンドでは、誰かが倒れたら誰かが助けに行った。ミスをしても「ドンマイ」の声がすぐに飛んだ。頼られるのも、頼るのも、自然だった。だけど今の俺は、誰かに声をかけることすら躊躇してしまう。忙しそうだから、迷惑かけたくないから、と理由をつけて自分を黙らせてしまう。昔は助けることが強さだと思っていた。でも今は、助けられることもまた強さなんじゃないかと、しみじみ思う。
あのころの「頼る」「頼られる」が今は遠い
試合に負けたとき、全員で泣いた。勝ったときは飛び跳ねて喜んだ。あの感情の起伏と、人との一体感。今の生活にはない。仕事では感情を抑え、成果だけを追いかける。喜びも悔しさも、静かに飲み込むのが“社会人”だと言われればそれまでだけど、やっぱり寂しい。昔の自分が見たら、今の俺はどう映るんだろう。きっと、「もっと人と関わっていいんだよ」と言ってくれる気がする。
仕事以外でも誰かの力になりたい
誰かの役に立つのは好きだ。でもそれが仕事だけに偏っていると、どこか自分が一部しか使われていないような気がしてくる。肩書きじゃなくて、趣味や人生経験やちょっとした気遣いでも誰かの力になりたい。例えば、荷物を持ってあげるとか、夕飯に誘われるとか、そんな小さなことでいい。肩の力を抜いて関われる人間関係がほしい。それがこの歳になると、案外一番難しい。
名刺のいらないつながりがほしい
最近、名刺を渡すのが少し憂鬱になってきた。そこから始まるのは、いつも「仕事の話」。でも本当は、名刺なんていらない関係性を築いてみたい。たとえば近所の人に「一緒に釣りでも行きませんか」と言われるような、そんな関係が理想だ。俺という人間そのものに興味を持ってもらえたら、どんなに楽だろう。名刺のない自分をもっと表に出したい。でも、それができる場が少なすぎる。
小さな頼まれごとが嬉しい理由
先月、事務員さんから「プリンタの紙、補充お願いしてもいいですか?」と言われたとき、内心ちょっと嬉しかった。仕事の一部とはいえ、「頼ってくれた」ことが嬉しかったのだ。俺がやらなければ回らないことではないけど、誰かに“任された”という事実が妙に心に残った。頼られるという行為そのものが、人間関係の根底にあるのかもしれない。大それたことじゃなくていい。ただ、「お願い」が言い合える関係を築いていきたい。
休日に「ちょっと手伝って」と言われる幸せ
もし誰かが、「日曜だけど、棚の組み立て手伝ってくれませんか」と声をかけてくれたら、俺は二つ返事で行くと思う。仕事のことを一切抜きにして、ただの“俺”を必要としてくれる。それだけで、日曜日が特別になる気がする。頼られることは、存在を認められること。それが仕事以外でも起きたら、人生はもう少し楽しくなるんじゃないか。そんな小さな希望を胸に、また月曜日を迎えるのだ。