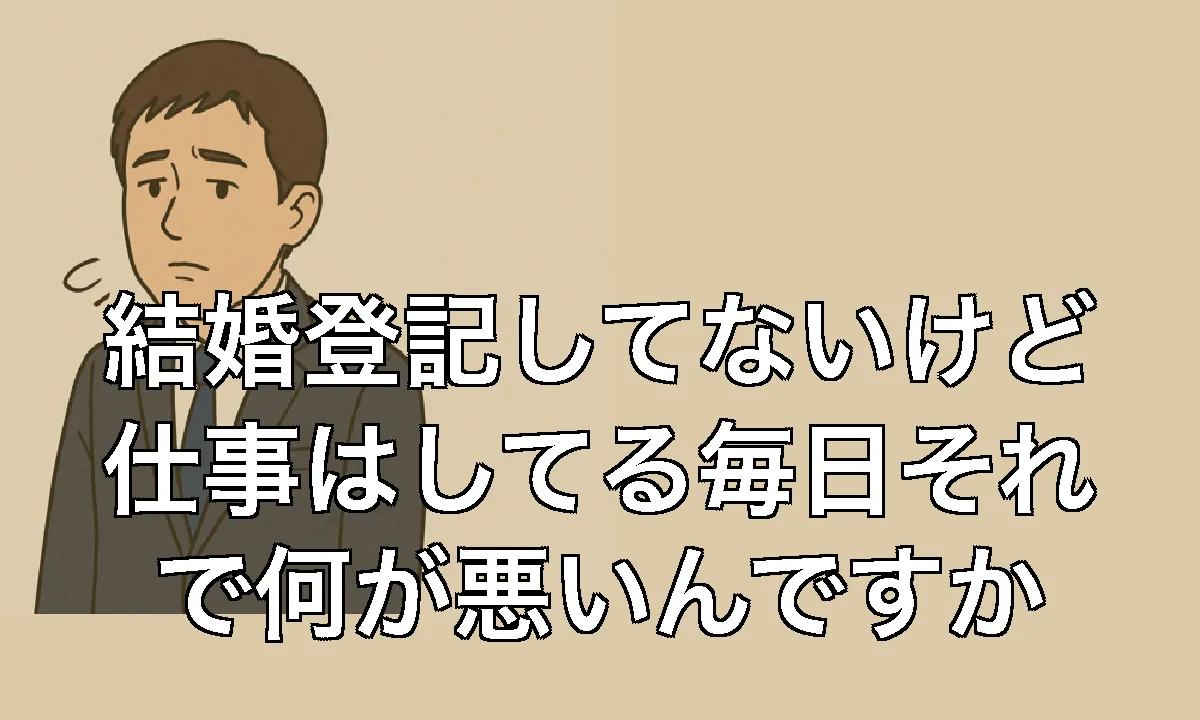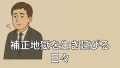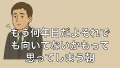結婚登記してないけど仕事はしてる毎日それで何が悪いんですか
籍を入れてないと聞くたびに始まる説教モード
「なんで籍入れないの?」
このセリフ、これまでに何度聞かれたことか。親戚、友人、たまにお客様まで。まるで何か大事な手続きが抜けてますよ、と言わんばかりの顔をされるたび、こっちはこっちで決めたことがあるんです、と心の中で小さくつぶやく。確かに籍は入れてない。でも一緒に住んで、支え合って、弁当の残りを分け合う日々は、まぎれもなく「生活」だった。それでも、登記がないと関係が不完全に見えるらしい。書類がなきゃ関係は存在しないんだろうか。そんなことを思いながら、今日も登記簿をめくる。
家族を持たない人間に対する無言の圧
独身、それもいい年した男の独身ってのは、世間にとって不思議な存在らしい。仕事の会合に顔を出せば、開口一番「奥さんは?」。いないって言うと、「まあ…仕事熱心なんですね」と返される。その言葉の奥にあるのは、どこか哀れみや心配の匂い。家族がいない=何かが欠けてる、そんな空気にいつもさらされている。自分としては、誰かと籍を入れることよりも、目の前の依頼に真摯であることを優先してきたつもりだ。でも、そういう“選択”が「可哀想」に見えるらしい。それが、ちょっと悔しい。
「それって不安じゃないの?」という悪意のない刃
ある日、馴染みの司法書士仲間との飲み会で、「将来、病気になったときに頼れる人がいないと不安じゃないの?」と真顔で言われた。もちろん悪意なんてない。でも、その言葉は、まるで自分の人生設計が“欠陥品”であるかのように響いた。そりゃ不安がゼロってわけじゃないけど、籍があるかないかで人生の備えが全部変わるわけでもない。保険もあるし、サポート制度だってある。何より、籍があっても孤独な人はいる。安心は形式じゃないんだって、そう思いたい。そう思わなきゃ、やってられない。
安心って本当に紙一枚で手に入るのか
司法書士として、毎日誰かの権利関係や財産の手続きを扱ってる。登記があるからこそ守られる権利がある。そんな現場にいながら、「自分の人生には登記がない」という皮肉。たまにふと、紙一枚で証明される関係って本当に強いのか?って考えてしまう。離婚届一枚で終わる結婚もあるのに。逆に、紙も契約も何もなくても、長年寄り添ってきた夫婦のような二人もいる。安心とは、証明ではなく、積み重ねなんじゃないか。そう信じているけれど、誰かに聞かれたら、やっぱりちょっと言い返したくなる自分がいる。
結婚してないからって不誠実扱いされる風潮がつらい
仕事上、特に相続や遺言の場面では、結婚の有無ってかなりセンシティブな話題になる。だからこそなのか、職業柄なのか、こちらが独身だと知ると「信頼していいのか」と顔に書かれることがある。もちろん口には出さない。でも態度が微妙に変わるのがわかる。不誠実って、何を持って判断するんだろう。籍がない人間=無責任というステレオタイプに、こちらの積み重ねてきた仕事への姿勢まで否定されるような気がして、やるせない。
信用力の話になると急に肩身が狭くなる瞬間
住宅ローンの審査や賃貸契約、ちょっとした書類上の手続きで、「配偶者の情報を書いてください」と求められるたびに、「あ、自分は書く人いないんだった」と小さく肩をすぼめる。それ自体は手続きのルールだから仕方ない。でも、自分が何か“足りてない存在”のように感じるのは否めない。司法書士としてはあらゆる契約の「完備性」を扱うが、自分のプライベートにおいては、常にどこか未完成扱いされる。その矛盾に、ふとため息が出ることがある。
司法書士という看板の効力と限界
「司法書士さんなんですね、しっかりしてそう」――初対面の人から言われる常套句。でもそのイメージは、結婚して子どもがいて、という“模範的な家庭像”込みのことが多い。つまり“しっかりしてそう”=“ちゃんと結婚してそう”。それって結局、職業に期待されるのは「生活の型」まで含まれているということ。こちとら、不動産の契約書は完璧に仕上げても、自分の人生設計には抜けだらけ。でも、それでいいじゃないか、と心の中で思っている自分と、やっぱり後ろめたさを感じる自分が同居している。
結局肩書きで判断される現実
司法書士という肩書きに守られている部分は確かにある。だからこそ、肩書きが“私生活の補完装置”になっている実感もある。世間的に「独身の司法書士」より「既婚の司法書士」の方が、信頼感があるように映るのは事実。それが現実なのだろう。でも、その現実に合わせて自分の生き方を変える気は、やっぱり起きない。肩書きは武器であり、同時に仮面でもある。本音では、誰かに「あなたのやり方でもいいじゃない」と言ってもらいたいだけかもしれない。
独身で仕事ばかりだとさみしいねと言われがち
夜遅くにコンビニ弁当を片手に帰宅する日々。照明のついた部屋に帰るとほっとするけど、ふと「誰かが待ってる」という安心がないのは確かだ。そんな生活をしてると、「さみしくないの?」とよく聞かれる。でも、仕事で人と関わってる時間が長すぎて、逆に一人の時間が貴重だったりする。だけど、たまに冷蔵庫に水しか入ってないとき、「ああ、自分の生活ってこれでいいのか?」と思う瞬間も、正直ある。
平日の夜に弁当とテレビとメール対応
午後9時過ぎ、事務所からの帰り道にいつものスーパーが閉まっていると、ああ今日も買いそびれたなと肩を落とす。そしてコンビニ弁当を手に家に戻る。テレビをつけても、番組よりもメールの返信に集中してしまうのがルーティン。食事中も仕事が頭から離れない。こうして誰にも邪魔されず集中できるのはありがたい…と思い込もうとしている自分に気づく夜もある。誰かと夕飯を食べる日がいつか来るのだろうか。そんな想像すら、最近はしなくなってきた。
一人の夕飯が孤独かどうかは誰にも決められない
一人で食べる夕飯が孤独なのか、自由なのかは、人による。だけど世間はそれを「可哀想」と見る傾向がある。実家の母もたまに電話で「ちゃんとご飯食べてるの?」と心配してくれる。でもそれは「誰かと一緒に」食べていることが前提のような言い方だ。たしかに一人の食卓は静かだ。でも、それが好きな時間でもある。誰にも気を遣わず、好きな味を選んで、誰にも話しかけられない。そんな時間も、案外悪くないと感じている自分がいる。
誰にも頼られず頼らずでやってきた結果
誰かに頼らない代わりに、誰にも頼られない日々。それが楽なようでいて、ふとした瞬間に空虚になる。誰かの期待に応えることもない。頼られたら頼られたで大変だけど、そのぶん誰かの役に立っている実感はあるはず。仕事ではクライアントの信頼に応えているつもりだけど、それは仕事上の責任であって、生活の中での“居場所”とはまた別のもの。気づけば、自分の人生の中心は仕事しかなくなっていた。これでいいのか、と問いかけながらも、結局また朝が来て、仕事に向かう。