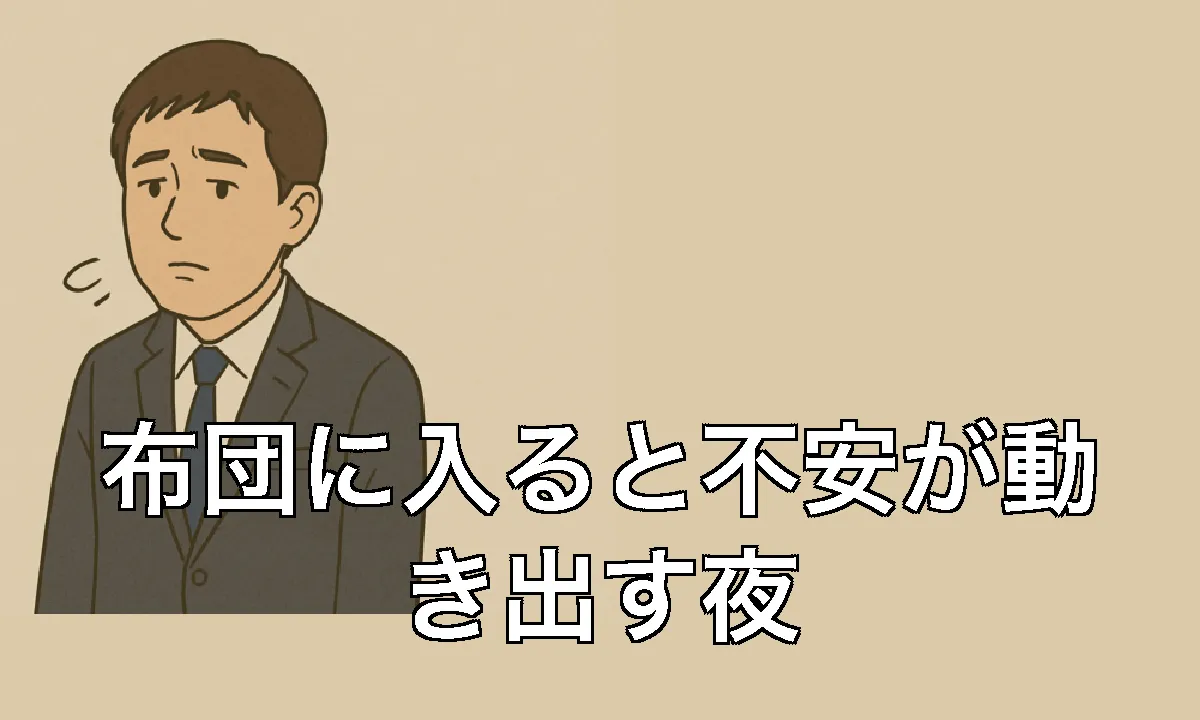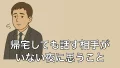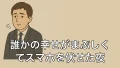静かな夜にだけ聞こえてくる心の声
昼間はなんとかやり過ごせるんです。依頼者の応対、電話、役所への提出書類、相続の確認、登記のチェック……一日中、あれやこれやに追われていると、悩む余裕すらありません。ところが夜、すべての音が止まって、ようやく布団に入ると、どこからか心の中にぽたりと落ちる音が聞こえてくる。あれ、今日のあの件、大丈夫だっただろうか。あの依頼者、怒っていないだろうか。自分はこのままでいいんだろうか。そんな問いが、止まらなくなるんです。しんとした夜の空気は、見たくなかった自分の影を浮かび上がらせてくる気がします。
昼間は気づかないノイズが夜に響く
日中は意外と「仕事の音」に助けられていたのかもしれません。キーボードを打つ音、電話のベル、ファックスの受信音、事務員さんがコーヒーを入れる音……。そのひとつひとつが、心のざわつきを上書きしてくれていた。でも夜になると、それらの音がなくなり、まるで無音の映画館でひとりだけ取り残されたような感覚になります。そんなとき、昼間押し込めていた考えが、頭の中でリピート再生されるんですよね。まるでBGMのないスピーカーから、ひとつの不安だけがやたらと大音量で響いてくるような。
依頼者対応の緊張が後を引く理由
ある日、ちょっとした確認漏れがあって、相手に迷惑をかけてしまったことがありました。もちろん謝罪し、再発防止にも取り組んだのですが、あの時の「はあ……そうですか」のトーンが頭から離れず、夜に布団の中で思い出してしまう。依頼者の表情ひとつが、数日間眠りを浅くさせる。それくらい、司法書士の仕事は人の感情に敏感にならざるを得ないのだと、身にしみて感じています。
今日の対応はこれでよかったのかという自問
「自分はあの時、ちゃんとした説明をできていたか?」と夜になると急に心配になる。しかも、不思議なことに昼間はそんなに気にしていなかったのに、夜になって急に「もっといい言い方があったんじゃないか」とか、「あの沈黙はまずかったな」などと反省モードに入ってしまう。これが毎晩のように続くと、次第に布団に入ること自体が怖くなってきます。眠れない夜は、ただの睡眠不足ではなく、自問自答地獄のはじまりなんです。
疲れているのに眠れない矛盾
今日も仕事でクタクタ。歩数計を見れば1万歩超え。体は正直で、ふくらはぎはパンパンなのに、なぜか眠れない。この矛盾が、本当に厄介です。事務所の灯りを落としたあとの静けさは、心を落ち着かせるどころか、逆に神経を過敏にする。疲れているくせに眠れない、眠れないくせに焦って、ますます眠れなくなる……。何をやっても裏目に出る感じがして、ただひとりで悶々としてしまいます。
身体は限界でも頭だけが回っている
夜遅く帰宅して、シャワーを浴び、ビールを1本飲み、布団に入る。でもそこからが長いんです。身体は休めと言っているのに、頭の中だけは目が覚めていて、午前中の登記相談の内容をぐるぐると再生している。昔、野球部のピッチング練習でミスをしたときも、家に帰ってから何度もフォームを頭の中で振り返っていました。それとまったく同じことを、今は仕事でやっている。疲労と反省がセットで襲ってきて、眠れるわけがない。
書類のチェック漏れが夢に出る
あるとき、夢の中で登記識別情報を間違えて渡してしまうという悪夢を見ました。起きてからしばらく、それが夢なのか現実なのか分からず、本気で冷や汗をかきました。まさか夢でまで書類と向き合うとは。司法書士になってからというもの、安心して眠れる夜が減った気がします。これは仕事に対する責任感の裏返しでもあるけれど、さすがに心が休まらないのは困りものです。
いつからか眠るのが下手になった気がする
若い頃は、どこでもすぐに眠れました。合宿所の硬い畳の上でも、夜行バスでも。でも司法書士として独立してからというもの、眠りが浅くなり、布団に入ってから眠るまでにかかる時間も長くなりました。たぶん、頭の中がずっと動いているからだと思います。昼間は「やるべきこと」で埋め尽くされ、夜は「やらなかったこと」が脳内で反芻される。その繰り返しが、眠りを奪っている気がしてなりません。
若い頃の眠りと今の眠りの違い
昔は、翌日の心配なんてほとんどありませんでした。寝て起きたらリセット。それが今では、翌日提出の書類や、依頼者との打ち合わせのシミュレーションが寝る前に始まり、終わらないまま朝を迎える。眠りに対する姿勢が変わったわけじゃないのに、眠りそのものが遠くなった。あの頃の「何も考えずに眠る力」が、今いちばん欲しいスキルかもしれません。
独立してからのプレッシャーの重さ
独立すれば自由だ、と思っていた時期もありました。確かに、誰にも指示されず、すべて自分で決められる。でもそれは、すべて自分が責任を背負うということでもあるんですよね。ミスひとつが信用を失い、信用を失えば仕事が減る。地方で司法書士として食べていくというのは、そんな危うさの上に成り立っています。だからこそ、寝る直前に「あれでよかったのか」と不安になる。眠りよりも安心が欲しい夜ばかりです。
事務員に言えない小さな不安の積み重ね
事務員さんは頑張ってくれているし、変に心配させたくない。だから、ちょっとした不安は口に出さず自分の中で処理するようにしているんですが、それがたまってしまう。表には出していないけれど、見えないところで小さなミスを繰り返していないか。自分の判断が、誰かに負担をかけていないか。そんな不安が夜になると膨れ上がってくる。結局、誰にも言えないからこそ、眠れなくなってしまうんですよね。
誰かと住んでいたら違ったかもしれない
たまに思うんです。誰かが隣にいたら、眠れない夜も少しは楽だったのかなって。音のない部屋でひとり、呼吸音すら自分だけ。たとえば誰かと他愛もない会話をして、あくびをして、笑って、布団に入って、「おやすみ」と言える。そんな生活だったら、眠りの質も変わっていたのかもしれません。独身が悪いわけじゃないけれど、独身の夜は、ちょっと静かすぎます。
独身の自由と夜の孤独はセットでやってくる
自由であることは、確かに心地いい。でもその自由には「誰にも相談できない夜」や「眠れないのを誰にも話せない朝」がくっついてくる。独身のままでいることを選んできたつもりだけど、こういう夜にだけは、誰かと一緒にいたら違ったのかもしれないと考えてしまう。自由と孤独の両方を引き受ける覚悟が、眠りを遠ざける原因になっているのかもしれません。
寝室の静けさがかえって心をざわつかせる
耳栓でもしてるんじゃないかと思うくらい静かな夜。そんな環境は本来、よく眠れるはずなんです。でも実際には、静けさが心のざわめきを引き立ててしまうんです。冷蔵庫の小さな音、外を走る遠くの車の音、窓の外の虫の声……それらが全部、自分の思考を際立たせてしまう。寝室の静けさは、静けさであって静寂ではない。音のない中で、不安だけがひそひそとしゃべってくるような、そんな夜です。
眠れない夜の向き合い方
眠れないことを、無理に正そうとしないほうがいいと最近思うようになりました。眠らなきゃと焦れば焦るほど、眠れなくなる。だったら、いっそ起きていよう。そう考えるようになってから、少し気持ちが軽くなった気がします。眠れない夜を「失敗の夜」とせず、「思考の整理の時間」と思えば、少しだけ眠れない自分を許せるようになった。完璧に眠れなくても、自分を責めなければ、それでいいのかもしれません。
開き直って起きているという選択
最近は、眠れなければ無理に布団の中にいないようにしています。起きて、机に向かって、日記を書いたり、翌日のタスクを書き出したりしてみる。すると意外にも、書き出すだけで安心することがある。悩みを頭の中でぐるぐるさせるのではなく、紙に出してしまう。それが一種の放電になっているのかもしれません。眠ることよりも、まずは頭の中を静かにすること。それを心がけています。
温かい飲み物と紙の日記で気持ちを落ち着ける
ホットミルクなんて気取ったことはしませんが、白湯を飲んで、A5サイズのノートに今日あったことを書き出すだけでも、頭が整理されてくる。タイムスタンプも日付もいらない。ただ思いついたことを順番に書く。司法書士としての日常では、正確性と順序がすべてですが、この日記だけは無秩序でもいい。自由に書ける場所がひとつあるだけで、少し安心できる夜になります。
眠れなくても自分を責めないことが大事
昔の自分だったら、「眠れないなんて甘えだ」と思っていたかもしれません。でも今では、「眠れない夜も、自分の一部だ」と受け入れるようにしています。眠れないのは、頑張っている証拠かもしれないし、気にしすぎる繊細さの裏返しかもしれない。どちらにしても、それは悪いことではない。眠れなかった次の日は、昼休みに5分だけ目を閉じる。そんなふうに、少しずつ自分をいたわっていけたら、それでいいと思うようになりました。