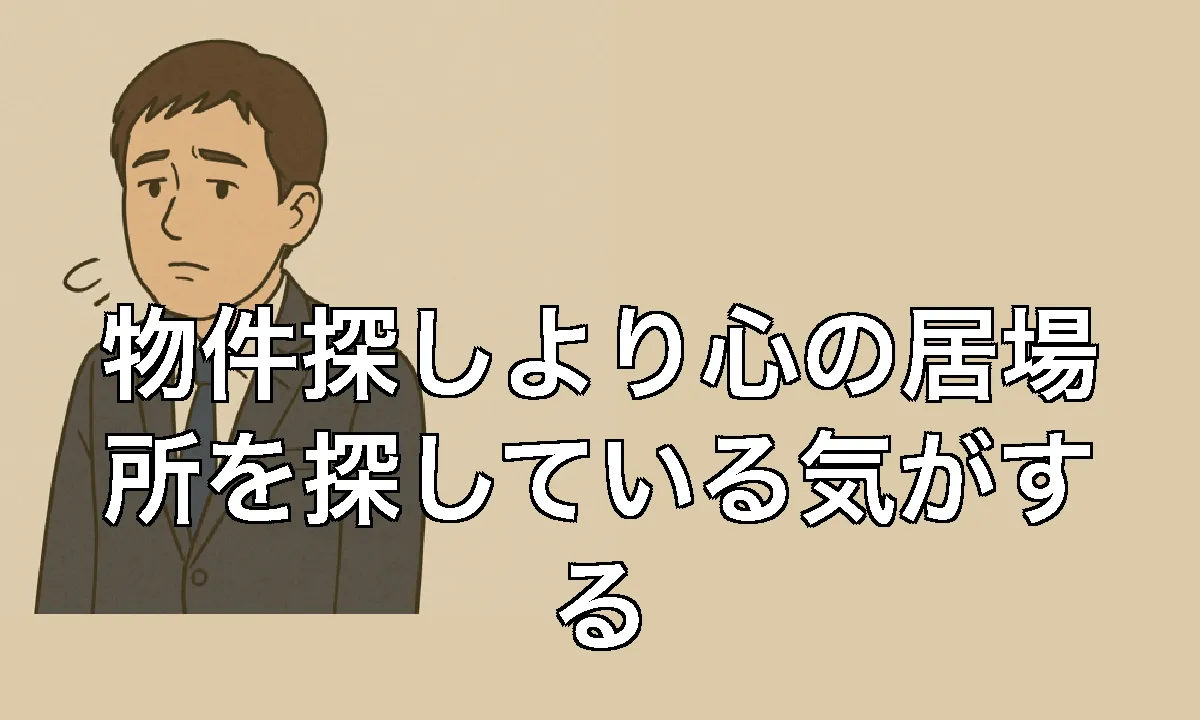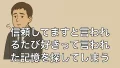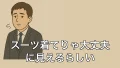物件探しより心の居場所を探している気がする
間取り図を見すぎて心が疲れてしまった
最近、夜な夜な物件情報を眺めるのが習慣になっている。仕事帰りに家に帰ると、とりあえずパソコンを開き、不動産サイトをスクロール。駅から徒歩何分だとか、築年数がどうだとか、そんな条件をチェックする毎日。だけど、画面に映る間取り図を見つめているうちに、ふと思った。「自分は本当にこの“部屋”を探しているんだろうか?」と。ふさぎ込んだ気持ちに、図面の線は冷たすぎる。
図面にあるのは壁の位置だけで心の余白は書いてない
不動産の間取り図って、実に正確だ。壁の長さ、ドアの位置、収納の広さ。だけど、そこには“住む人の気持ち”なんてどこにも描かれていない。静かに休めるか、朝起きた時に陽の光が気持ちいいか、孤独に押しつぶされないか。そんな心のスペースは図面には載っていない。なのに僕は、図面ばかりを見て、自分の心の状態を後回しにしていた。
理想の部屋を求めすぎて自分を見失う
「ここは間取りがいい」「ここは収納が足りない」そんなふうに理想を求めるうちに、何を大事にしたいのか自分でも分からなくなっていった。事務所と家の往復、日々の業務に追われる中で、本当は“安心して帰れる場所”が欲しかったのに、気づけば“条件が揃った部屋”にばかり目を向けていた。それって本末転倒じゃないかと思う。
「駅近」「南向き」「収納充実」の罠
便利さやスペックにこだわるのは悪くない。でもそれが、自分の気持ちの本質から目をそらす言い訳になっていたのかもしれない。駅から近くても、帰るたびにどっと疲れるなら意味がない。南向きでも、ひとりぼっちの食卓がつらいなら意味がない。収納が多くても、心にしまい込んだ孤独が片付かなければ、意味がないのだ。
広さより大切なものに気づいてしまった
先日、友人のワンルームに遊びに行った。決して広くはないけれど、あったかい雰囲気があった。観葉植物と、ちょっとしたお気に入りの本棚、そして落ち着いた照明。それだけで「ああ、ここに住んでいる人は幸せなんだな」と思えた。広さじゃない。どんな気持ちでその空間にいるかが大事なんだと、そのとき気づかされた。
ひとり暮らしには十二分な空間が息苦しい
僕の住んでいる部屋は、正直言って広い。荷物も少ないから、余計にガランとしている。けれど、その空間がなんだか落ち着かない。心のどこかが空っぽで、広さがその“空虚さ”を強調してしまう。ひとりには贅沢なはずなのに、贅沢であることがかえって寂しさを膨らませるという矛盾を感じている。
六畳一間でも心が落ち着く場所とは
逆に、六畳一間でも安心できる空間というのはある。学生時代に下宿していた部屋は、今思えばボロボロだったけれど、なぜか心がほぐれていた。帰れば誰かが廊下で声をかけてくれたし、壁の薄さすら「生きてる感じ」があった。あの頃は、お金もなかったけれど、心には何かしらの“居場所”があった気がする。
狭さの中にある安心感と自由
空間が限られているからこそ、そこに自分らしさを詰め込めたのかもしれない。ポスターを貼ったり、机の配置を工夫したり、手を加える余地があった。今は設備が整ってる代わりに、どこか完成されすぎていて、自分が“住まわせてもらってる”感がある。安心って、必ずしも広さや新しさじゃないんだと、今さら気づかされた。
事務所も住まいも自分の居場所にならないとき
気づけば、どこにも“居場所”がない感覚がある。事務所では相談者に寄り添いながらも、心は常に緊張していて、家に帰っても心が休まるわけではない。なんだろう、物理的にはちゃんと“ある”のに、精神的には“ない”という不思議な状態。居場所って、空間の話ではなく、気持ちの話なんだと痛感する。
「帰りたくなる場所」がない日々の重さ
「早く帰りたい」と思える場所がある人は幸せだ。僕は最近、「帰る」というより「戻る」になっている感覚が強い。ただ生活のために寝に帰っているだけ。帰りたい気持ちが湧かないから、仕事を無理に伸ばして、帰宅を遅らせることさえある。本末転倒だと分かっていても、そうしてしまう自分がいる。
仕事場が住みかより長くなる現実
独立して司法書士事務所を開いてからというもの、家よりも事務所にいる時間の方が長くなった。仕事柄仕方ないと思っていたけれど、ある日ふと気づいた。「俺、どこで生きてるんだろう」って。椅子に座って書類を作る時間ばかりが人生になってしまっていて、ふとした瞬間に空しさが込み上げてくる。
気づけばキーボードの打鍵音が生活音
朝起きて、キーボードを叩いて、夜帰ってもまたパソコンの前。生活の音が、鳥の声でもなく、湯を沸かす音でもなく、カタカタと鳴る打鍵音になってしまっている。これは果たして“暮らし”と言えるのか? 自分の人生が、タスク管理と申請書類の山でできてしまっていることに、時折恐怖を感じる。
心のスペースをつくるにはどうしたらいいのか
物件情報を閉じて、空を見上げた。その瞬間、ようやく呼吸が深くなった気がした。心のスペースって、時間や空間に比例しない。たぶん、余白は「つくるもの」なんだ。生活の中に、無理やりでも余白を差し込んでいかないと、心は窒息してしまう。じゃあ、どうやって作ればいいのか。
モノを減らすより、思考を減らす
断捨離やミニマリズムが流行っているけれど、僕にはあまり合わなかった。むしろ効果があったのは、「あれもしなきゃ」「これも確認しなきゃ」という思考を止めること。ときどき意識的にぼーっとする時間をつくる。完璧を目指さない。やることリストに「ぼーっとする」を入れてみる。これだけで、心にだいぶ風が通るようになった。
スケジュールを空けるという勇気
予定が詰まっていると、なぜか「ちゃんとしてる気」になる。でもそれが自分を追い詰めていた。週に1時間でも“予定のない時間”をつくるようにした。意外とそれだけで、次の仕事がスムーズに運んだりする。心のスペースは、誰かに与えてもらうものではなく、自分で空ける勇気が必要なのだ。
誰にも会わない時間の贅沢さ
一人で過ごす時間が好きなのに、なんとなく「孤独」として自分を責めていた。でも今は、誰にも会わない時間を“贅沢な時間”と感じられるようになった。誰の言葉にも引っ張られず、ただ静かに息をする。その時間があると、少しだけ、また人と話す元気が戻ってくる。心のスペースって、案外そんなふうにして回復するのかもしれない。
空間じゃなく心が欲しかったんだと気づいた夜
「こんな物件どうですか?」とスマホの通知が鳴ったとき、画面をそっと閉じた。もう少し、自分の心のスペースを整える方が先かな、と思えたからだ。物件探しに夢中になっていたけれど、本当に探していたのは、居心地のいい“心の居場所”だったのだと気づいた夜。きっと、それに気づけただけで、一歩前に進めた気がする。