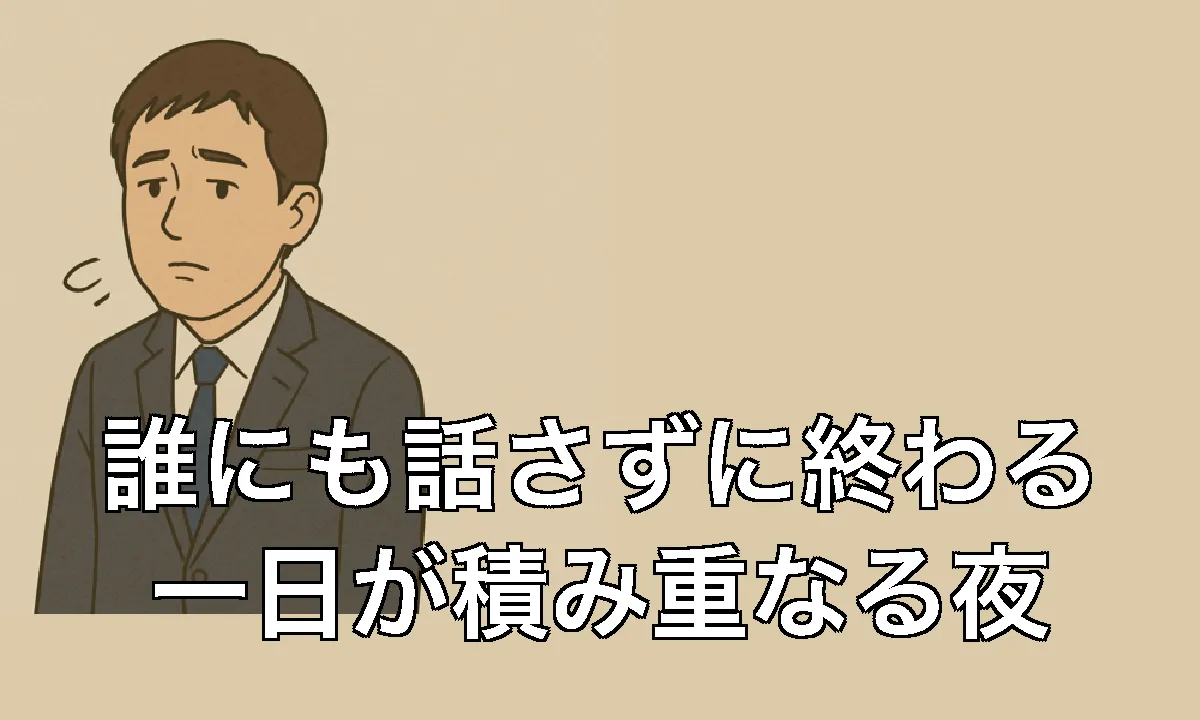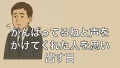仕事帰りのスーパーで誰とも目を合わさない
夜のスーパーは明るい。外がどんなに暗くても、店内の蛍光灯が現実を照らし出す。レジに並び、買い物かごを手にしていても、どこかここは現実ではないような感覚に襲われる。誰もがスマホの画面か、値引きシールにしか興味がなく、他人の存在を認識しない。まるで透明人間になった気分になる。それが不思議と心地よくなってきている自分にも、少しだけ恐怖を感じる夜だ。
「いらっしゃいませ」だけが唯一の声
スーパーの自動ドアをくぐった瞬間に聞こえる「いらっしゃいませ」は、今日一日で初めてかけられた言葉かもしれない。それは私に向けられたものではない。機械のように繰り返される接客用語にすぎないのだが、それでも少しだけホッとする自分がいる。店内を歩きながら、何を買うでもなく惣菜コーナーをうろつき、安売りシールを見つけてカゴに放り込む。それだけのことが、なんだか妙に重たい行為に思えてくる。
レジ係との数秒が今日の対話のすべて
レジでの数秒間、店員と目が合うか合わないかの一瞬。袋が必要かどうかを聞かれ、「いりません」と答えるその声が、自分でも驚くほどかすれていた。声帯が固くなっていたのか、それとも人と話していなさすぎたのか。言葉が出るまでにワンテンポ遅れるこの感覚に、寂しさというよりも「やばいな」という危機感を覚えた。誰かと日常会話を交わさない生活が、ここまで身体に影響するとは。
ポイントカードを聞かれることさえありがたい
「ポイントカードはお持ちですか?」その一言すら、今では貴重なコミュニケーションに感じる。財布からカードを出し、差し出すときに一瞬だけ指が触れた。その瞬間に、なんだか人間として認識されたような気がして、逆に恥ずかしくなった。日々の中でどれだけ人との接点が減っているのか、レジというほんのわずかな時間が、嫌でもそれを突きつけてくる。
事務所では淡々と進む仕事と沈黙
日中は日中で、仕事に追われている。登記書類のチェック、オンライン申請、電話応対、そしてお客様対応。決してヒマではない。ただ、淡々と作業をこなすだけで、そこに感情の交流はない。唯一の事務員とは、必要最低限のやりとりしかしない。気まずいわけではない。むしろ信頼関係はあるのだが、心の交流と呼べるものは存在しない。静かな時間だけが積み重なっていく。
事務員とは最低限のやりとりしかない
「これ、確認しておきました」「ありがとうございます」それだけで業務が回るのは、ある意味すごいことだ。だが、その“すごさ”が孤独を深めていく。昼休みも別々にとるし、雑談もほとんどしない。お互い悪気があるわけじゃない。むしろ気を遣いすぎて、必要以上に踏み込まないようにしているのかもしれない。その結果、まるで静かな図書館のような職場になってしまっている。
報連相はしているが心の交流ではない
司法書士という職業柄、正確さと効率が求められる。だからこそ、無駄なやりとりは減っていく。報告・連絡・相談、いわゆる「報連相」は完璧でも、そこに感情は乗らない。昔、職場で笑いが起こったり、雑談で和んだ時間があったような気がするが、今はそんな余白もない。孤独が仕事の一部のように組み込まれてしまった気さえしてくる。
誰かと話したい気持ちと話しかける勇気のなさ
話したい気持ちはある。でも、いざ誰かを前にすると何を話せばいいのか分からない。話しかける理由が見つからない。かといって、沈黙のままでいいわけでもない。いつの間にか、話すことに対して緊張するようになってしまった。元野球部で声は大きかったはずなのに、その声の出し方すら忘れてしまった気がする。
沈黙に慣れてしまった自分に気づく
静けさが当たり前になってくると、音のある世界がうるさく感じるようになる。駅のアナウンス、人混みのざわめき、ラジオのテンション。それらすべてが異世界のように聞こえてくる。そうやって沈黙に慣れた自分は、もう他人と自然に接することができなくなっているのではないか。そんな不安が頭をよぎる。
元野球部の声の大きさは今や影を潜めた
高校時代、試合中に大声で仲間を鼓舞していた自分はどこに行ったのか。今では電話に出る声ですら「え、聞こえない」と言われることがある。口の筋肉が衰えたのか、それとも心が声を小さくしているのか。誰かとつながっていた頃の自分を思い出すたび、今の自分との差に愕然とする。けれど、その過去を今さら取り戻せるとも思えない。
コンビニの店員にすら声がかけられない
コンビニで箸をもらい忘れても、もう一度声をかける勇気が出ないことがある。レジを離れたあとに「あ、箸……」と思っても、そのまま店を出る。小さなことかもしれないが、そういう些細な接触がどんどん減っていくのを実感する。人と関わることが「面倒」になってしまったのか、それとも自分が誰かにとって「迷惑」になるんじゃないかという遠慮なのか。どちらにせよ、声をかけることがハードルになっているのは確かだ。
なぜこんな日々を送っているのか考えてしまう夜
仕事帰りにスーパーに立ち寄り、無言で食材を選び、会計を済ませて帰る。その流れが当たり前になって久しい。だが、ふと立ち止まると、「なんでこんな毎日なんだろう」と疑問が湧いてくる。充実しているのか、それとも疲れきっているだけなのか。誰かと話せば楽になるのか、いや、そもそも話す相手がいないじゃないか。そんなことを、冷蔵庫の明かりを見ながら考えてしまう。
頑張っているのに空しさが残る
日中は真面目に働いている。登記も漏れなく処理しているし、相談にも親身に対応している。それでも、家に帰って一人で食事をしていると、「俺、何してるんだろうな」と思ってしまう。誰のために、何のために頑張っているのか。そんな漠然とした疑問が、夜の静けさの中でじわじわと広がっていく。
やりがいと孤独は共存するものなのか
司法書士の仕事には確かにやりがいがある。困っている人の助けになれるし、感謝の言葉をもらうこともある。でも、やりがいがあるからといって、孤独が消えるわけではない。むしろ、人と深く関わるぶん、自分の心が消耗していくような気さえする。やりがいと孤独は、相反するようでいて、実は両立するものなのかもしれない。
それでも明日はまたやってくる
一人で感じる寂しさや、声をかける勇気のなさは、今日だけのものではない。明日もたぶん同じような一日が続く。それでも、生きていくしかない。仕事があることに感謝しながら、それでもどこかに「このままでいいのか?」という問いを抱え続ける。そんな日々を繰り返していく中で、少しでも誰かと心を通わせる瞬間があれば、それはきっと救いになる。
小さなやりとりが心を救うかもしれない
レジでの「ありがとうございました」、電話口の「お世話になっております」、事務員との「おつかれさまです」。その一つひとつが、思っている以上に自分の支えになっている。たとえ一言でも、そこに気持ちがこもっていれば、孤独はほんの少しだけ和らぐ気がする。そんな小さなやりとりを、大事にしていきたい。
司法書士という仕事がつなぐものもある
この仕事をしていなければ、誰とも関わらずに一日を終えることもあったかもしれない。たとえ表面的なやりとりであっても、誰かの役に立てている実感はある。それが唯一の救いだ。孤独を抱えながらも、誰かの人生に関わることができる。それが司法書士という仕事の、矛盾と魅力なのだと思う。