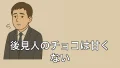訪ねてきた依頼人
古びた茶封筒と中身の遺言書
午後三時。やっと一息つけるかと思った矢先、ドアが開いて男が入ってきた。中年のその男は、見るからに緊張しているようだったが、手には分厚い封筒を持っていた。「叔父が亡くなりまして……」という前置きとともに封筒の中身、つまり遺言書をテーブルに置いた。
「なるほど、自筆証書遺言ですか」と言いながら中を確認すると、やや古びた紙に打たれた文字が並んでいた。手書き……ではない。どうやらタイプライターか、あるいはワープロ機で作られたらしい。
「これは……ちょっと変ですね」思わず声が漏れた。私の違和感に気づいたのか、男は「問題ありますか?」と不安げに訊いてきた。
手書きか機械かという疑問
自筆証書遺言の有効要件としては全文自筆であることが求められる。日付も署名も、すべて手書きでなければならない。だが目の前の書類は、署名以外すべてがタイプ文字で構成されている。
仮に署名が本物だったとしても、これでは家庭裁判所の検認手続きで揉める可能性が高い。私はそっとため息をつき、「さて、どうしたものか……」と天井を仰いだ。
その時、サトウさんがそばで腕を組んでいた。鋭い眼差しで紙面を見つめている。ああ、これは何か言われるパターンだ。
サトウさんの冷たい指摘
「これ、フォントが変です」
「これ……平成明朝体じゃないですか?」とサトウさんが言った。私は思わず「えっ」と聞き返した。フォント名なんて気にしたこともない。だが、サトウさんはパソコン画面に例の遺言書と似た文体のフォントをいくつか並べて比較し始めた。
「平成明朝体が使われるようになったのは平成の初め頃です。この遺言が書かれたとされているのは昭和63年。合いませんよね」と、冷静に指摘してくる。やれやれ、、、まるで『名探偵コナン』の毛利小五郎と本物の探偵の関係のようだ。
「ということは、日付かフォントか、どちらかが嘘ですね」と私はぼそりとつぶやいた。事態は面倒な方向へ進んでいた。
形式的には有効かという話
このような場合、法的な有効性の判断は簡単ではない。実際、ワープロ打ちの遺言書は署名と押印があっても、自筆証書としては無効とされるケースが多い。
「となると、この遺言が無効なら、相続人は法定どおりということになりますね」と私は依頼人に説明した。だが、彼の目は泳いでいた。何かを隠している。そう確信した。
「おじ様は遺言を何通か書いていらっしゃいませんでしたか?」と水を向けると、彼は一瞬沈黙し、そしてこう答えた。「……実は、もう一通、あるかもしれません」
故人の素性と相続人たち
甥と名乗る若者の違和感
聞けば、その「もう一通」は、叔父の書斎にある古い机の奥に保管されている可能性があるという。私は念のため、現地調査を申し出た。彼も渋々ながら了承した。
家に到着すると、やたらときれいに整理されすぎた書斎が出迎えてくれた。まるで誰かが捜索済みのようだ。引き出しの中からは、ホコリをかぶった小さな封筒が出てきた。封はされていなかった。
「これは……」サトウさんが小声でつぶやいた。中には、明らかに手書きで書かれた遺言書があった。しかも内容は最初のタイプ文字のものとは異なっていた。
筆跡鑑定への道のり
私たちは、発見された手書きの遺言書と、依頼人が持参したタイプ文書の署名を比較した。目視でも明らかに筆圧が違っていた。筆跡鑑定を依頼するしかない。
「最初のやつは偽物の可能性が高いですね」と私が言うと、サトウさんは「最初からそう言いましたよね」とそっけない。いつもの塩対応である。
甥と名乗っていた依頼人が本当に相続人なのか。さらに調査が必要だと感じた。
もう一通の遺言の存在
机の奥から出てきた封筒
手書きの遺言には、全く別の人物の名前が受遺者として記されていた。名前は女性。しかも、家政婦のような立場だった人物らしい。にわかに「火曜サスペンス劇場」の雰囲気が立ち込める。
サトウさんは「これ、女性の名前が旧姓で書かれてますね。調べますか?」とすでに次の行動に移っていた。行動が早すぎる。さすがに司法書士アシスタント界の峰不二子だ。
その結果、家政婦は故人と事実婚に近い関係だったことがわかった。これはもうひと波乱あるなと確信した。
筆跡とタイプ文字の逆転
依頼人の持参した文書と、新たに見つかった手書きの遺言は、署名の形も日付の字体も全く異なっていた。しかも、先ほどの「平成明朝体」は故人の所有していたワープロの機種では使用できないことも判明。
つまり、最初の遺言は誰かが作成した偽物であり、唯一の手書き遺言こそが真実だった。証拠は整った。
やれやれ、、、また余計な手間を背負ってしまった。
事件の結末とその後
本物の遺志を尊重して
私は依頼人に淡々と告げた。「あなたが提出された文書は、正式な遺言書として認められません」。顔色が変わった彼は、「そんなはずは……」と繰り返したが、もはや言い逃れはできなかった。
真実は、故人が遺した手書きの文にあった。それは家政婦であり伴侶でもあった女性に向けた感謝の気持ちと、ささやかな遺産の譲渡だった。
私はその遺言の検認手続きを進め、淡々と終わらせた。結局、正しいものが残るのがこの仕事だ。
帰り道の自販機前でため息
その帰り道、自販機の前で缶コーヒーを買い、一口すすった。「にしても……平成明朝体なんて、よく分かったな」
「基本です」とサトウさん。やっぱり冷たい。そして強い。
私は空を見上げた。「やれやれ、、、今日はビールがうまそうだ」