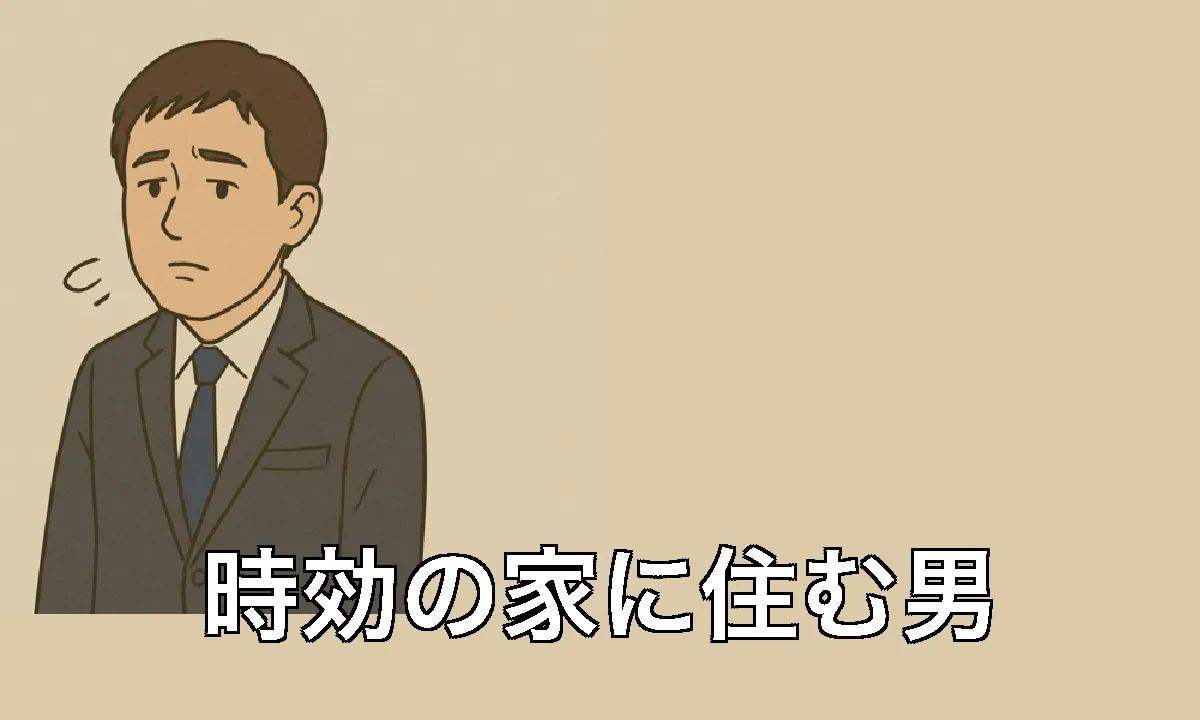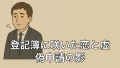奇妙な依頼はいつも突然に
「ここ、私の家なんですけどねぇ、正式な登記がされてないって言われてしまいまして…」
午後3時、天気はどんより曇り。よくある相続かと思って話を聞くと、どうも様子が違う。
男の語る内容は、まるでサザエさんのエンディングのようにズレていて、微妙に笑えなかった。
ボロ家に住む男の登記相談
依頼人は、年齢不詳でやけに手の甲が日焼けした男。住所を確認すると、たしかに法務局の登記簿には空白のまま。
「20年住んでますよ。水道も電気も自分で払ってます」そう言うが、名義は一切彼のものではなかった。
つまり、時効取得を主張するには、それなりの証拠が必要ということだ。
境界線と占有の謎
サトウさんが持ってきた公図と照らし合わせると、家の敷地と筆界が微妙にズレていた。
「おかしいですね。この塀、地番からはみ出てます」淡々と告げるサトウさん。
占有の事実が揺らげば、男の主張も怪しくなる。やれやれ、、、面倒なやつがきたな。
現地調査は雨の中で
週明けの火曜日、天気は最悪の土砂降り。現地は雑草に覆われていて、長靴なしでは進めない。
「この家、築年数も不明ですね」私はメジャー片手に塀の長さを測りながら呟く。
サトウさんは黙ってスマホでパシャパシャ写真を撮っている。まるで探偵だ。
サトウさんの完璧な地図
「建物の配置、測量図と照合完了しました」
彼女が提出してきたスケッチは、アニメ「キャッツアイ」の予告図並みに精密だった。
これを見れば、どこからどこまでが彼の“占有範囲”だったか、一目でわかる。
隣人が語る過去の持ち主
「あの人、勝手に住み着いたのよ。最初の頃は誰もいなかったの」
隣の老婦人は、やたらと話したがるタイプだった。
彼女の証言が時効取得の“平穏・公然”性を崩しかねない内容で、私は頭を抱えた。
消えた登記簿と残された鍵
法務局で閉鎖登記簿を取り寄せたところ、なんと最後の所有者は30年前に亡くなっていた。
相続登記もされておらず、登記簿の履歴はぽっかり空白。
「おおっと、これはサザエさん的な“来週も見てね!”展開ですね」と私が言うと、サトウさんは無言でため息をついた。
六年前の登記簿謄本の空白
さらに調査を進めると、6年前に登記されたはずの仮登記が失効していた。
「仮登記が失効してるなら、登記権利者も動いてないですね」
サトウさんは冷静に、まるでルパン三世の不二子のように、的確に核心を突いた。
古い手紙に隠された名義人の痕跡
依頼人の話を信じて家の屋根裏を調べると、古びた封筒が出てきた。
中には30年前の公共料金の請求書と、亡くなった名義人の名前が記されていた。
状況証拠としては弱いが、時効取得の一部証明にはなる。
誰がいつから住んでいたのか
ここからは心理戦だ。依頼人の言葉の端々を検証していく。
「ええっと、平成14年から住んでるって言ったけど、さっき平成12年とも言ってたような…」
時効取得は時間との戦い。どこかのタイムラインが破綻すればアウトだ。
供述と事実の食い違い
「当時の電気代が1万円超えたこともあってねぇ…」と語る男。
しかし、電力会社に確認すると、契約開始日は平成16年だった。
どうもこの男、カツオ並みにうっかりしているようだ。
サザエさん方式の家族構成に違和感
「母と弟もいたんです」と語るが、近隣住民の記憶にはその姿がない。
サザエさん一家のような人数構成を装ってはいたが、実際は一人暮らしだったようだ。
証言の裏付けがなければ、全ては“言ったもん勝ち”で終わってしまう。
決め手は電気の契約書
やっと見つかったのは、古びた電気の使用契約書。
平成15年の日付があり、名義は依頼人のものであった。
「これは…効くかもしれませんね」とサトウさんが頷いた。
使用開始日と使用者の名義
使用開始の証明があれば、占有の事実は裏付けられる。
加えて水道の検針票も揃えれば、“時効取得の証明”にぐっと近づく。
ついにこちらの手札が整ってきた。
「誰も知らなかった」電力会社の記録
驚くべきことに、電力会社には全ての検針履歴が残っていた。
「普通は5年で消えると思ってました」と私が言うと、
「それは“思い込み”です」とサトウさんに一刀両断された。やれやれ、、、本当に敵なしだな。
サトウさんの推理と確認作業
彼女は住民票の履歴を追い、郵便受けの消印も記録として整理した。
法務局の嘱託登記官に提出する資料一式をまとめる姿は、まるで灰原哀のような冷静さだった。
私は、ただその背中を見守るしかなかった。
住民票と郵便受けの微細な証拠
住民票の転入日と郵便物の消印が一致していた。
「この辺りが鍵ですね」と彼女は微笑んだ。
きっと彼女は、こういうパズルのような仕事が好きなのだ。
やれやれ、、、ようやくつながった
全ての証拠が一つの線でつながったとき、私は机に深くもたれた。
「これでいけるかもしれないな」思わず漏れた声に、サトウさんは「最初からそのつもりでしたよ」とだけ言った。
やれやれ、、、これだから彼女には頭が上がらない。
時効取得と証明責任
民法162条による所有権の時効取得には、20年間の占有が必要だ。
しかも“所有の意思”がなければ成立しない。
「この男、そこまで考えてたとは思えないが…」それでも証拠が揃えば法は動く。
占有の継続と平穏の意味
暴力や騙しがあれば“平穏”とは認められない。
男の生活はつつましく、騒ぎもなく、誰とも争っていなかった。
つまり、理屈ではすべて条件を満たしていた。
証明のための“物証”とは何か
結局、時効取得に必要なのは「見えないものを見える化」する力だ。
生活の痕跡、継続の履歴、それが“物証”になりうる。
今回は、サトウさんの情報処理能力に助けられた。
提出された証拠と反論
全てをまとめ、法務局に登記申請を提出した。
一部の隣人は異議を唱えたが、客観的証拠の前に退けざるを得なかった。
この手の案件は、感情より証拠が物を言う。
隣人の証言は信用できるのか
裁判所ではないが、法務局でも証言の信用性は問われる。
供述が変遷していた老婦人の発言は、結局採用されなかった。
「真実」よりも「証明された事実」のほうが強いのだ。
タイムスタンプ付きの写真の威力
サトウさんが撮った現地写真と、過去のGoogleマップの画像が一致していた。
今は写真一枚でも時系列を証明できる。
「名探偵コナンのような決定的証拠ですね」と言ったら、やはり無言で睨まれた。
シンドウの判断と結末
すべての証拠が認められ、無事に登記完了の通知が届いた。
私は、久しぶりに一人でラーメンをすすりながら、達成感に浸った。
たとえ依頼人がどんな人物でも、正しい筋道さえあれば、道は開ける。
時効取得の成立と登記申請
「20年の時を証明する」ことは、ある意味で記憶との戦いだ。
証明されたとき、それは法によって“真実”とされる。
シンドウとしても、忘れがたい一件となった。
実は“誰の土地”でもなかった
皮肉な話だが、相続人が誰も登記しなかったために、この土地は“無主”だった。
誰も管理せず、誰も文句を言わなかった土地。
それを20年守った男が、最終的に“所有者”になった。それが法の妙だ。
事件のあとで
「しかし、たった一人でよく住み続けたわね」
サトウさんの言葉に、私はなんとなくホッとした気がした。
誰かが認めてくれる。それだけで、頑張った甲斐があるというものだ。
サトウさんの意外な一言
「次は“空き家バンク詐欺”の件ですね」
え、もう次の事件?と私は頭を抱える。
やれやれ、、、休む間もないのが司法書士の宿命なのかもしれない。
今日もまた登記簿と向き合う
パソコンの画面には、登記情報提供サービスのログイン画面。
私はコーヒーを片手に、今日もまた登記簿とにらめっこする。
それが俺の、変わらぬ日常なのだ。