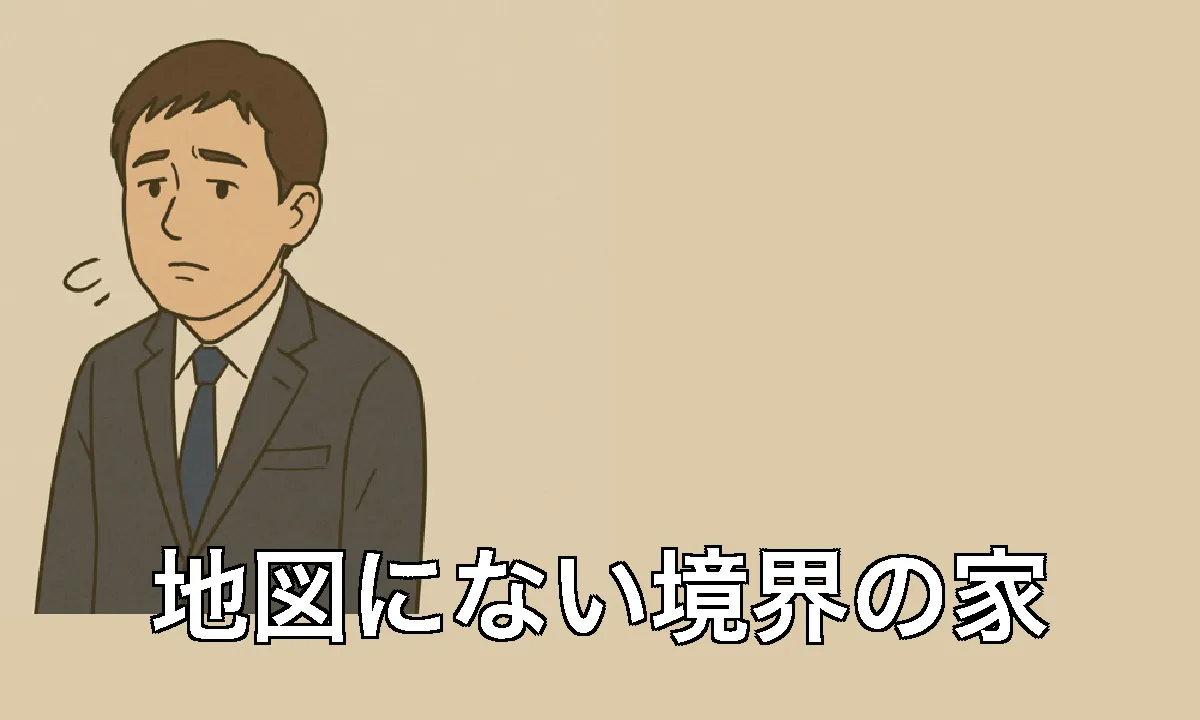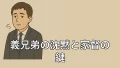依頼は境界線から始まった
「おたくの登記でひとつだけ気になることがありましてね」
そう言ってやってきたのは、年季の入ったジャケットを着た中年の男性だった。
相続による名義変更の相談だったが、話を聞いているうちに妙な一言が飛び出した。
地番調査のはずが変な違和感
問題の土地は町外れの一角にあったが、登記簿上の地番と、地元で呼ばれている場所がどうも一致しない。
「地図上では家は無いんです」とサトウさんがタブレットを指差す。
けれど、現地にはどう見ても立派な古民家が残っていた。
古地図と新地図の食い違い
昔の住宅地図を図書館で引っ張り出すと、確かにそこには家が描かれていた。
しかし、法務局の公図ではその場所は空白。
何かが消されたような不自然さに、背筋がすっと冷えた。
境界線の向こうにあった家
現地調査に赴くと、草むらの先にひっそりと佇む家があった。
朽ちかけた瓦、割れたガラス戸、その奥に誰かの視線を感じた気がして思わず息を呑む。
「まるでサザエさんで波平が忘れられてる回みたいですね」とつぶやくと、サトウさんが無言で睨んできた。
現在地になぜか家が存在しない
持参したGPSで現在地を確認しても、マッピング上には構造物なし。
Googleマップにも影さえ映っていない。
「いや幽霊屋敷とか、そういう話じゃないよな…」と一人ごちながら、建物に足を踏み入れた。
古地図にだけ記された家
壁に貼られた昭和の選挙ポスター、昭和61年のカレンダー。
時間が止まったような空間に、なぜか心がざわついた。
「この家、本当に誰にも相続されてないのか?」疑念が膨らむ。
登記簿と現地のズレ
法務局で再度調査をすると、該当する地番の履歴には“取り消し”の記録があった。
一度登記された後、なぜか地図から消されていたのだ。
「行政ミスか、それとも意図的な抹消か…?」とつぶやくと、背中が重くなる。
法務局では辿れない過去
古い謄本を目で追っていくと、ある宗教団体が一時期所有していた記録が残っていた。
だが、その後の売却記録がどこにもない。
「やれやれ、、、また厄介な匂いがしてきたな」と、思わずこぼれた。
「あの家は夢だった」という証言
地元の古老に話を聞くと、「あの家?あれはもうないはずだが」と首を傾げた。
まるで、記憶ごと塗り替えられたような反応だった。
だが、その古老の家の納屋には、例の家の表札がなぜか保管されていた。
依頼人の語らない記憶
再び訪ねてきた依頼人は、どこか怯えた表情で言った。
「登記変更はやはり取り下げたい」
理由を尋ねても、歯切れの悪い沈黙だけが返ってきた。
遺産分割で現れた奇妙な相続人
一週間後、突然見知らぬ若者がやってきた。
「僕が本当の相続人です」
証明書類は完璧だったが、あまりにも準備が良すぎた。
境界の家に眠る秘密
彼の証言では、祖父が「地図にない場所に逃げろ」と遺言していたらしい。
あの家は一族の逃げ場だったというのだ。
「それが今になって、なぜ現れる…?」サトウさんも眉をひそめた。
サトウさんの推理が動き出す
「この家、境界線をまたいで建ってますよね」
サトウさんが持参した方位磁石とレベル測量器を見せた。
どうやら家は二つの地番にまたがっていたが、登記は片方だけだったのだ。
古い家屋図面に残されたヒント
市役所の古文書室にあった建築図面には、隠し通路のような線が引かれていた。
それは、法務局ではなく、宗教団体の所有記録にのみ存在していたものだった。
「つまり、意図的に登記を曖昧にして、隠れ場所として使っていたわけか」
境界線上の虚構と事実
地図の上で家はなかった。
だが現実には存在し、しかも人が関わっていた痕跡がある。
「誰かが家そのものを、地図の裏に隠したんです」とサトウさんは言った。
やれやれの真実
結局、その家は取り壊され、登記も正式に閉鎖された。
依頼人は「ようやく父を超えた気がする」とぽつりと漏らした。
どこかほっとしたような表情が、逆に不気味だった。
誰が家を塗り替えたのか
最後まで明かされなかったのは、誰が地図から家を消したのかという点だった。
おそらく、行政か、あるいは当時の所有者の圧力か。
それでも、この事件は何か大きな「意図」に包まれていたような気がしてならない。
終わった事件と残る余韻
事務所に戻ると、サトウさんが「たまにはグーグルじゃなくて足で歩くのも悪くないですね」と言った。
ぼくは椅子に沈み込みながら、「やれやれ、、、」と呟いた。
もう地図は信じない。そんな気分だった。
境界は法の外にも存在する
この仕事、紙の上の話だけじゃない。
法とは別の、記憶と感情と、曖昧な土地の歴史が交錯している。
司法書士なんて仕事、つくづく割に合わないと思う日がある。
サトウさんが言った一言
「シンドウさん、地図に載ってなくても、ちゃんと足元に道はあるんですよ」
不意に投げられたその言葉に、思わず笑ってしまった。
そうだ、歩けるならそれで十分かもしれない。