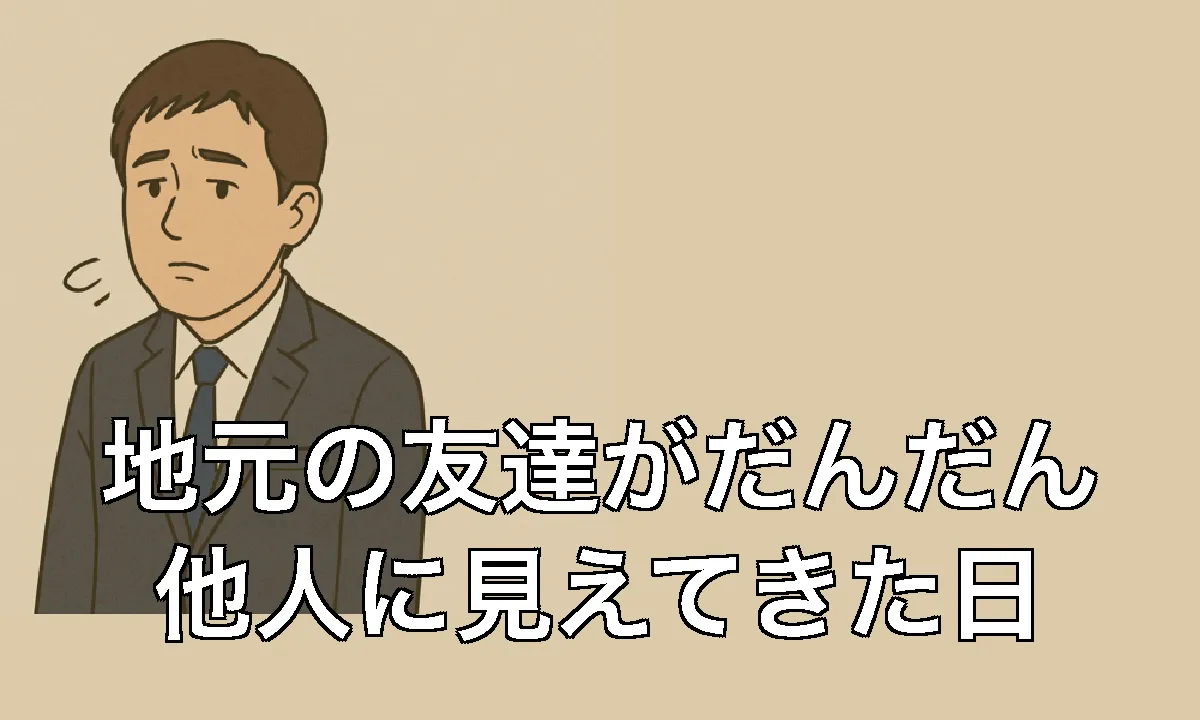地元という言葉に感じる重さと懐かしさ
「地元」と聞いて思い浮かぶのは、駅前の商店街だったり、校庭の隅っこで時間を潰していた放課後だったりする。あの頃は何も考えず、地元の仲間とただ笑っていた。気を遣う必要なんてなかった。でも今、あの道を歩いても胸の奥が少しだけ重くなる。変わったのは風景か、自分か。それとも、何も変わっていないのにそう感じてしまうほど、遠くに来てしまっただけなのかもしれない。
帰る場所はあるけど戻れない
年に一度くらい、地元に帰る。両親の顔を見に、墓参りに、あるいはただの義務のように。でも、誰かと連絡を取ることは減った。昔は「帰るから飲もう」と声をかければ集まってくれた仲間たち。今は既読すらつかないことがある。予定が合わないというより、もう「会う理由」がお互い見つからないのかもしれない。物理的には帰れるのに、心はどこか、居場所がないような感覚になる。
同じ景色が違って見える理由
地元の駅を降りた瞬間、どこか懐かしさと同時に違和感を覚える。変わったはずのない街並みが、自分の知っているそれとは少しだけズレて見えるのだ。高校の頃に通ったラーメン屋が閉店していたり、駄菓子屋がコインパーキングになっていたり。時の流れを感じるよりも、自分だけが取り残されたような寂しさが胸を締めつける。景色は変わらないのに、自分の中の「意味」が変わってしまったのだ。
コンビニの前で語っていた夜が懐かしい
夜中に自転車で集まって、何をするでもなくコンビニの前でだべっていたあの頃。将来のことなんて真面目に考えてなかったけど、なんだかんだで楽しかった。寒い冬でも誰かが缶コーヒーを買ってきてくれたり、受験の愚痴を言い合ったり。あの時間が今となっては一番「人とつながっていた」と思える。今の自分が同じことをやっても、きっと心からは笑えない。それが一番、悲しいのかもしれない。
連絡先はあるのに手が伸びない現実
スマホの連絡先をスクロールすれば、あの頃の名前がずらっと並んでいる。けれど、そのどれにも指が止まらない。返信が来なかったらどうしよう、忙しいかもしれない、今さら何の用事だと思われないか。そんな考えが先に立ってしまって、結局何も送れずに画面を閉じる。そのくせ、たまに夢に出てくるのは、やっぱりあの友達だったりする。
LINEの未読が気まずくなる瞬間
何かの拍子に送ったLINE。例えば同窓会の連絡だったり、共通の知人の訃報だったり。返事はなかった。いや、既読すらついていなかった。スマホの不具合か、それともただ「見てないふり」なのか。それを考えると余計にしんどくなる。見なければ傷つかずに済む。そう思って、こちらもまた返信しない。いつからだろう。こんなにも面倒な関係になってしまったのは。
今さら何を話せばいいのか分からない
相手の今の仕事も、家族構成も、趣味すら知らない。何を話しても、どこかよそよそしい会話になりそうで怖い。昔話だけでは5分ももたない。それを埋める努力をするほどの熱量もない。でも、きっと相手も同じことを思っているのかもしれない。だったら、お互い様か。そうやって、連絡をしない理由をまたひとつ、自分の中に積み上げてしまう。
「久しぶり」が怖い言葉になるとき
「久しぶり」って言葉、昔はもっと温かかった気がする。けど今は、そこに「気まずさ」や「距離感」が滲んでしまう。再会の一言なのに、どこか「ごめん」という意味が含まれてしまうのだ。「久しぶり」が言えないくらい離れてしまった人間関係って、一体なんだったんだろう。そう思うと、画面の向こうの名前が、どんどん遠くに感じていく。
自分が変わったのか相手が変わったのか
歳を取ると、変わるのは外見だけじゃない。考え方、価値観、生活リズム。全てが変わっていく。それを「変わったな」と感じるのは、きっと相手も同じだろう。昔は同じタイミングで笑えていたのに、今は何が面白いのか分からないこともある。けれど、それは仕方のないこと。変わっていくことに抗えない以上、それをどう受け止めるかだけが、自分にできる選択肢だ。
地元を離れた人間の孤独
司法書士という仕事を選んで地元を離れたとき、正直少しだけ「勝った」気分だった。周りよりも早く就職して、早く独立して、早く人生を動かしたつもりだった。でも気づけば、気軽に話せる相手がいない。孤独ってのは、何かが欠けた瞬間じゃなく、何かに気づいてしまった瞬間にやってくるのかもしれない。特に、誰にも見送られず帰る新幹線のホームでは、それを強く感じる。
地元に残るという選択への尊敬と嫉妬
地元に残って家を継いだ友人、地元の工場で働き続けている友人、皆、地に足のついた生活をしている。SNSで家族との写真を見て「幸せそうだな」と思いつつ、どこかで「退屈じゃないのかな」と思っていた自分が恥ずかしい。今は逆だ。何かを守るために地元に残った人の方が、よほど強い選択をしていた気がしてならない。
司法書士という職業が作った距離
司法書士として独立し、地域に根ざして働いているつもりだが、地元の友人との距離はむしろ遠くなった。仕事の話はしづらいし、誰かに何か頼まれると、どうしても「仕事」として受け止めてしまう自分がいる。学生時代のように無邪気には話せない。もしかしたら、自分自身が壁を作ってしまっているのかもしれない。
肩書きが会話を難しくさせることもある
「司法書士ってどんな仕事?」「難しそうだな」そんな言葉を言われるたび、話の流れが止まる。説明しても伝わらないだろうという諦めと、伝わってほしいという願望の板挟みになる。昔なら「へー」で済んだのに、今は職業が会話のハードルになることがある。「ただの友達」でいられた時間が、どれだけ貴重だったかを思い知らされる。
「お前は忙しそうだな」と言われて気づいたこと
久しぶりに会った友人に言われた。「お前は忙しそうだな」その一言が妙に引っかかった。確かに忙しい。けれど、連絡一本くらいできたはずだ。自分で自分の忙しさを言い訳にして、大事なものを遠ざけていたことに、ようやく気づいた。もう一度、少しだけ素直になろうと思った。
それでももう一度つながりたいと思った話
完全に途切れたように見える関係でも、どこかでまた交差することがある。たとえば、誰かの結婚式。誰かの訃報。あるいは、ただの偶然。それがきっかけで会話が生まれ、思い出話に花が咲く。そんな瞬間があるから、つながりは「完全には終わっていない」のだと信じたい。
誰かの結婚式が再会のきっかけになることもある
もう連絡もしないと思っていた友人と、結婚式で再会した。最初はぎこちなかったけれど、ビールを飲み交わすうちに、少しずつ距離が縮まっていった。過去の話ではなく、「今」の話ができた時、ようやく再会の意味を感じた。きっかけは何でもいい。ただ、会ってみないと分からないこともあるのだ。
疎遠でも完全に途切れたわけじゃない
連絡が減っても、会っていなくても、完全に終わったわけじゃない。心のどこかで、また会いたいと思っている限り、それは「つながり」だと思っていい。疎遠になることを悪いことだと決めつけず、変化の一部として受け入れていきたい。そう思えるようになったのは、たぶん歳を重ねたからだろう。